【バックオフィス業務の完全ガイド】基本から陥りがちな課題、業務改善のアプローチまで徹底解説
- 更新 -

バックオフィス業務は、企業活動の根幹を支える重要な役割を担う一方で、非効率な作業や内部統制上のリスクが生じやすいという側面も持ち合わせています。
本記事では、バックオフィス業務の基礎知識を振り返るとともに、よくある課題や業務改善に向けたアプローチをわかりやすく解説します。
バックオフィスDXカンファレンスAIをもっと活用するためにシステムと人財がともに進化する2日間

こんな人におすすめ
●AI活用を推進したいが何から手をつけていいのか分からない
●現場の関心を高めて全社的な取り組みに広げる方法が知りたい
●AIや最先端のテクノロジーの活用がしりたい方
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
- バックオフィス業務の基礎知識を再確認
- バックオフィスが抱えがちな4つの課題
- バックオフィス改革の第一歩!業務の「見える化」と「切り分け」
- バックオフィス業務の効率化に向けた5つのアプローチ
- バックオフィス業務の改革にワークフローシステム
もっと見る
バックオフィス業務の基礎知識を再確認
まずは基礎知識として、バックオフィス業務の意味やフロントオフィスとの違い、バックオフィス業務の強化が求められる背景について解説します。
バックオフィス業務とは?
バックオフィス業務とは、顧客と直接的な接点を持たず、社内から事業活動や従業員を支える業務全般を指します。「後方支援業務」や「間接業務」とも呼ばれ、組織が円滑に機能するための土台となる役割を担っています。
バックオフィスに該当する主な職種と業務内容は以下の通りです。
- 経理・財務:伝票処理、請求・支払業務、月次・年次決算、資金繰り、予算策定、財務戦略の立案など
- 人事・労務:採用活動、人材育成、人事評価制度の運用、勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、入退社手続き
- 総務:オフィス環境の整備、備品管理、文書管理、株主総会・取締役会の運営支援、社内イベントの企画・運営
- 法務:契約書の作成・レビュー、コンプライアンス遵守体制の構築、知的財産管理、法的なトラブルへの対応
- 情報システム:社内ITインフラの構築・運用、セキュリティ対策、業務システムの導入・保守、ヘルプデスク業務
フロントオフィスとの違いや関係性
バックオフィスとしばしば対比されるのが「フロントオフィス」です。
- フロントオフィス:顧客と直接関わり、売上や利益を直接生み出す部門。(例:営業、マーケティング、カスタマーサポート)
- バックオフィス:フロントオフィスを後方から支援し、会社全体の基盤を支える部門。(例:経理、人事、総務)
フロントオフィスとバックオフィスは車の両輪のような関係です。たとえば、営業部門が大きな契約を獲得しても、法務部門による契約書レビューや、経理部門による正確な請求処理がなければ、取引は成立しません。
フロントオフィスが最大限のパフォーマンスを発揮するためには、バックオフィスのスムーズで正確な業務遂行が不可欠なのです。
バックオフィス業務の強化が求められる背景
近年、バックオフィス業務の重要性はますます高まっています。その背景には、「労働人口の減少(2025年問題)」「働き方改革の推進」「DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速」といった社会的な変化があります。
限られた人的リソースで高い生産性を維持するためには、非効率な業務をなくし、従業員が付加価値の高い仕事に集中できる環境を整えなければなりません。バックオフィス業務を効率化・高度化することは、もはや単なるコスト削減策ではなく、企業が変化の激しい時代を勝ち抜くための重要な経営戦略なのです。
バックオフィスが抱えがちな4つの課題
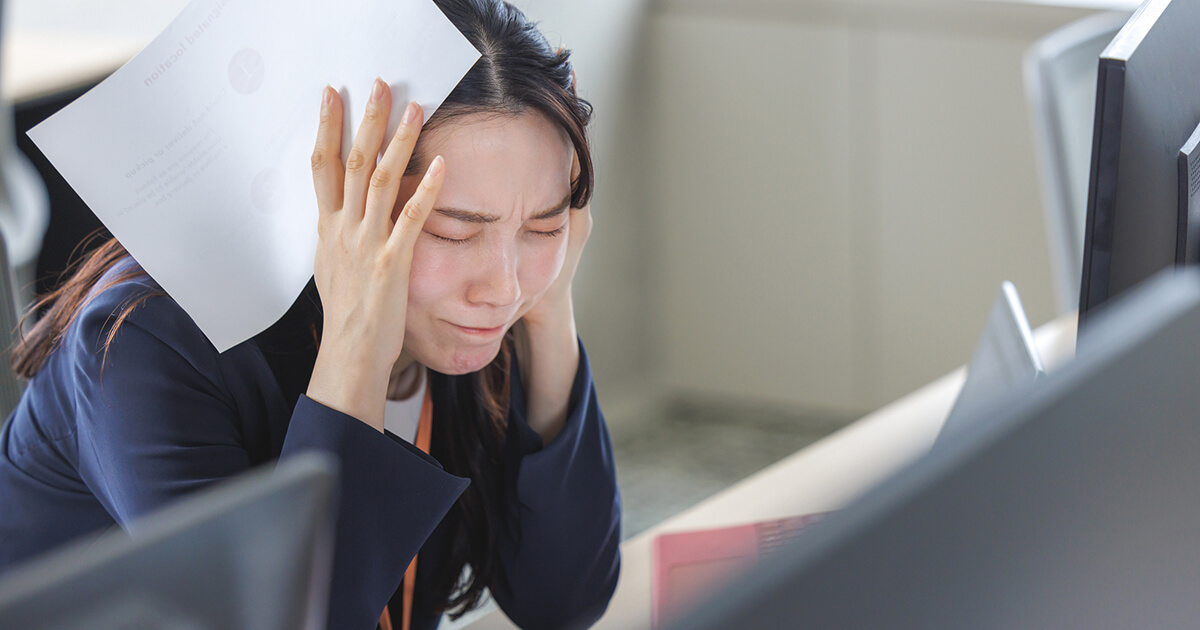
次は、多くの企業のバックオフィス部門が抱える4つの課題をご紹介します。
課題1:直接利益を生まない「コストセンター」という認識
バックオフィスは、その業務の性質上、売上を直接生み出すわけではありません。
そのため、社内では「コスト(経費)のみがかかる部門」という意味で「コストセンター」と見なされがちです。
この認識が定着すると、業務改善のためのIT投資や人材育成が後回しにされ、結果として非効率な状態が放置されるという悪循環に陥りやすくなります。
課題2:属人化しやすい業務プロセス
「この業務は〇〇さんしか分からない」といった状況は、多くのバックオフィス部門で見られます。特定の担当者の知識や経験に頼った業務プロセスは、「属人化」を招きます。
属人化が進行すると、以下のようなリスクが生じます。
- 担当者の急な休職や退職で業務が滞る
- 業務の品質が担当者によってばらつく
- 業務の全体像が誰にも分からなくなり、改善の糸口が見えなくなる
これらのリスクは、組織全体の運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
課題3:アナログ作業が多くヒューマンエラーが発生しやすい
バックオフィス業務には、依然として紙の書類やExcelでの手作業による管理が多く残っています。
- 契約書や請求書を印刷し、ファイリングして保管
- 交通費精算を経費精算書に手書きで記入し、上長が押印
- Excelの複数ファイルからデータを手作業で転記・集計
このようなアナログな業務は、時間がかかるだけでなく、転記ミスや計算ミスといったヒューマンエラーを誘発する温床となります。
課題4.ダブルチェックなどの「無駄」が生まれやすい
先述したヒューマンエラーを防ぐため、ダブルチェックやトリプルチェックを取り入れている企業も多いのではないでしょうか。
請求書の金額ミスや契約書の誤字脱字を防ぐために、ダブルチェックは有効な手段です。しかし、ダブルチェックは人的コストが2倍になる上、人が行う以上ミスを100%防ぐことはできません。また、複数人がチェックに携わることで当事者意識が薄れ、確認作業が形骸化してしまうケースも少なくありません。
そのため、システムによる自動チェックなども組み合わせつつ、ダブルチェックへの過度な依存から脱却することも重要だと言えます。
バックオフィス改革の第一歩!業務の「見える化」と「切り分け」
これらの課題を解決し、バックオフィス改革を進めるには、まず自社の業務内容を正確に把握する「見える化」と、業務の性質に応じた「切り分け」を行うことが不可欠です。
「コア業務」と「ノンコア業務」の切り分け
企業の業務は、その性質から「コア業務」と「ノンコア業務」の2つに大別できます。
- コア業務:企業の収益に直接的に結びつく、競争力の源泉となる中核業務。(例:商品開発、マーケティング戦略の策定、営業活動)
- ノンコア業務:コア業務を支えるための補助的な業務。定型的な作業が多い。(例:給与計算、請求書発行、備品管理、データ入力)
バックオフィス業務の多くは、このノンコア業務に分類されます。改革のポイントは、ノンコア業務を可能な限り省力化し、より付加価値の高いコア業務にリソースを集中させることです。
企業活動を支える「間接業務」に潜むムダ
ノンコア業務と似た概念に「間接業務」があります。
これは、直接的に売上や業績に関与しない業務全般を指し、総務や経理、人事などの業務が該当します。
これらの業務は定型的なものが少なくないため、効率化の余地が大きい領域です。間接業務に潜む「ムダ」を見つけ出し、削減することが生産性向上の鍵となります。
業務の棚卸しを実施し「ボトルネック」を特定
コア業務とノンコア業務の切り分けや、間接業務のムダを発見するためには、まず業務の「棚卸し」を行い、「ボトルネック」となっている工程を特定しましょう。
- 業務の洗い出し:部署や担当者ごとに、行っている業務をすべてリストアップします。「誰が」「何を」「どれくらいの頻度・時間で」行っているかを書き出します。
- 業務フローの作成:主要な業務について、開始から完了までの流れを図で示します。これにより、業務の全体像やボトルネックとなっている箇所が明確になります。
- 課題の整理:洗い出した業務やフローの中から、「時間がかかりすぎている」「ミスが多い」「属人化している」といった課題を整理します。
このプロセスを通じて、ボトルネックとなっている業務を特定し、改善の優先順位を明らかにします。
バックオフィス業務の効率化に向けた5つのアプローチ

ここでは、バックオフィス業務の効率化に役立つ、代表的な5つのアプローチを紹介します。
アプローチ1:業務プロセスの見直しと再設計(BPR)
BPR(Business Process Re-engineering)とは、既存の業務プロセスを根本的に見直し、再設計することです。
個別の作業を改善するだけでなく、「そもそもこの業務は必要なのか」「もっと効率的なやり方はないか」という視点で、業務全体の流れを最適化していきましょう。
アプローチ2:業務システムやRPAツールの活用
近年では、バックオフィス業務の各領域に特化したITシステムが多数登場しています。たとえば、請求書発行システムや給与計算システム、勤怠管理システム、人材管理システムなどが代表的です。
これらのバックオフィス業務に特化したITシステムを活用することで、アナログな手法で行っていた業務をシステム上で効率的に行うことができるでしょう。
とくに、バックオフィスで見られがちな定型業務の自動化には、RPAツールの活用がおすすめです。RPAツールを利用することで、システム間で発生するデータ入力や転記などの定型作業を自動化し、ヒューマンエラーの削減につなげられるでしょう。
アプローチ3:業務の仕組み化
特定の担当者しか業務を行えない「属人化」を防ぐためには、業務の仕組み化が重要です。
まずは、業務マニュアルの作成などによる「標準化」から着手し、誰が担当しても同じ品質を保てる体制を目指しましょう。
基本的な業務手順をまとめるのはもちろんのこと、注意点やよくある質問とその回答、トラブルやイレギュラーがあった際の対応方法なども明文化しておくことで、作業者の経験やスキルに依存しない仕組みの土台となります。
アプローチ4:「文書管理」のペーパーレス化
オフィスに溢れる紙の書類は、保管スペースを圧迫し、必要な情報を探す手間を増大させます。「文書管理システム」などを活用してペーパーレス化を促進することで、これらの課題を解消し、検索性の向上やセキュリティ強化、情報共有の円滑化といったメリットを期待することができます。
システム選定の際は、自社の業務フローに合うか、操作が直感的で分かりやすいか、セキュリティ対策は万全か、といったポイントを確認しましょう。
アプローチ5:煩雑になりがちな「入社手続き」の一元化
バックオフィス部門に業務が集中するタイミングのひとつに、従業員の入社時期を挙げることができます。
従業員の入社時には、雇用契約書や年金手帳、扶養控除申告書など、数多くの書類の提出と手続きが必要であり、その多くはバックオフィス部門が管轄する手続きです。これらの手続きを一元的に管理できる仕組みを整えることで、煩雑な入社手続きを効率よく行うことが可能になるでしょう。
バックオフィス業務の改革にワークフローシステム
本記事では、バックオフィス業務の基本やよくある課題、業務改善に向けたアプローチをご紹介しました。
バックオフィス業務を効率化するには、業務プロセスの見直しや仕組み化、システム活用による定型業務の自動化やペーパーレス化などが有効です。
そして、それらの取り組みを加速させるソリューションのひとつが、ワークフローシステムです。
ワークフローシステムとは、社内で行われる各種手続きを電子化するツールで、業務の可視化や標準化、ペーパーレスの推進、文書管理の一元化などを実現します。また、各種システムとシームレスにつながり、業務領域間で生じる入力作業やチェック作業の自動化にも寄与します。
なかでも、株式会社エイトレッドが提供する「X-point Cloud」と「AgileWorks」は、シリーズ累計5,000社超の導入実績を誇り、多くの企業のバックオフィス改革に役立てられています。
バックオフィスの業務改革やDX推進に取り組まれている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
AIを活用したいバックオフィス部門の方へ
バックオフィスDXカンファレンスAIをもっと活用するためにシステムと人財がともに進化する2日間
バックオフィス×AI活用に真正面から向き合い、 2日間にわたって管理部門が進化の起点となるためのヒントを届けます。
こんな人におすすめ
●AI活用を推進したいが何から手をつけていいのか分からない
●現場の関心を高めて全社的な取り組みに広げる方法が知りたい
●AIや最先端のテクノロジーの活用がしりたい方


「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。






