【意思決定プロセス改善のための完全ガイド】基礎から実践的なアプローチまで網羅的に解説
- 更新 -

企業の成長は、日々の意思決定の積み重ねによって成り立っています。
本記事では、意思決定プロセスの基礎知識や遅延を招く原因、そして改善に向けた実践的アプローチをご紹介します。
意思決定プロセスを改善!稟議デジタル化の効果とは?
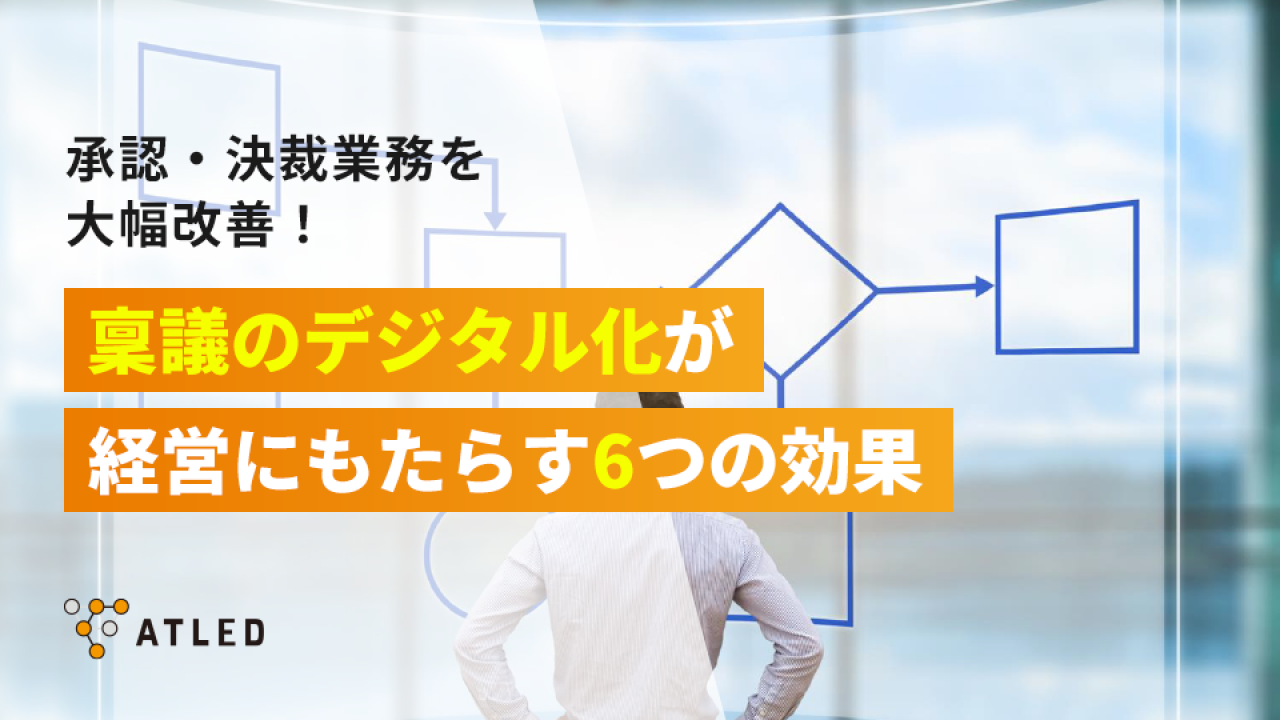
こんな人におすすめ
・意思決定のスピードを上げたい。
・バックオフィスの効率化を図りたい
・デジタル稟議の事例を見たい。
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
- 「VUCA時代」における意思決定の重要性
- 押さえておきたい意思決定プロセスの基礎知識
- 意思決定の遅延を招く6つの原因
- 意思決定プロセス改善に向けた実践的アプローチ
- 意思決定プロセスを劇的に改善するワークフローシステム
もっと見る
「VUCA時代」における意思決定の重要性
市場や顧客ニーズが目まぐるしく変化する、「VUCA時代」とも言える現代において、意思決定の遅れは致命傷になりかねません。
競合他社が新たなサービスを次々と展開するなか、自社だけが社内調整に時間を費やしていては、競争力を維持することは困難です。迅速かつ質の高い意思決定プロセスは、すべての組織に不可欠な経営基盤と言えるでしょう。
押さえておきたい意思決定プロセスの基礎知識

では、迅速かつ質の高い意思決定を実現するためにも、まずは意思決定プロセスの基礎について確認していきましょう。
意思決定の土台となる「ワークフロー」
意思決定の改善において非常に重要な概念として、「ワークフロー」が挙げられます。
ワークフローとは、直訳すると「仕事の流れ」です。具体的には、「ある業務を開始してから完了するまでの一連の手続きや担当者間のやり取り」を指し、稟議や申請も、このワークフローの一部です。つまり、自社の意思決定プロセスを見直すことは、このワークフローを最適化することと同義と言えます。
「稟議」「起案」「上申」の違い
意思決定に関する頻出キーワードに、「稟議(りんぎ)」や「起案(きあん)」、「上申(じょうしん)」といった言葉があります。
これらは混同されがちですが、厳密にはそれぞれ意味合いが異なります。
稟議とは、担当者が作成した案に対し、関係者の承認を得て意思決定を行う、日本企業で広く用いられるプロセスです。
起案とは、新たな事柄を計画し、具体的な案として文書にまとめる行為そのものを指します。稟議にかけるための元となる文書を作成することです。
上申とは、自身の権限だけでは決定できない事項について、上司や上層部の判断を仰ぎ、指示をもらうことです。
整理すると、「起案」した内容を、複数の関係者で確認して承認を得るプロセスが「稟議」、特定の上の役職者に判断を仰ぐのが「上申」と言えます。
「承認」と「決裁」の違い
意思決定プロセスにおいては、「承認」と「決裁」という工程が必ず存在します。これらも混同してしまいがちですが、意味が異なるため注意しましょう。
承認とは、提出された案に対して、内容を確認し、同意・許可することです。中間承認者が行う行為も含まれます。
決裁とは、最終的な決定権を持つ者(決裁者)が、その案件を最終的に許可・承認することです。
つまり、一つの意思決定プロセスにおいて、「承認」は複数回行われることがありますが、「決裁」は一度だけです。
意思決定の遅延を招く6つの原因

意思決定プロセスを改善するためには、まず「なぜ遅いのか」という原因を正しく理解することが不可欠です。
ここでは、意思決定の遅延を招く6つの原因を見ていきましょう。
原因1:承認ルートの煩雑化
意思決定が遅延する原因として、承認ルートが複雑化しているケースが考えられます。
本来不要なはずの承認者がルートに含まれていたり、誰が最終決裁者なのか不明確だったりと、承認ルートが煩雑化しているケースです。
このようなケースでは、不要な承認ステップが生じたり、次の承認者を調べるのに時間がかかったりしてしまい、プロセス全体の遅延を引き起こします。
原因2:不要な「回覧」によるプロセスの長期化
似たようなケースとして、不要な回覧が決裁の長期化を招いているケースもあります。
本来は情報共有だけでよいはずの相手まで承認ルートに含めてしまうことで、不要な意見や質問を誘発し、プロセスを複雑化させている場合があります。「回覧」と「承認」の区別が曖昧な組織によく見られる課題です。
原因3:職務権限が不明確
「この金額の決裁は部長なのか、本部長なのか」のように、職務権限が曖昧なケースでは、担当者は念のため多くの承認者を経由しようとします。
これにより、本来は部門内で判断できるはずの案件まで、最終的な意思決定および実行まで多くの時間を要してしまうのです。
原因4:情報不足による「差し戻し」の頻発
3つめは、承認者・決裁者が判断を下すために必要な情報(背景、目的、費用対効果、リスクなど)が不足しているケースです。
情報が不足していれば承認者・決裁者は判断ができず、結果として質問や修正依頼が増えたり、手戻り(差し戻し)が頻発したりして、意思決定が遅延してしまいます。
原因5:想定外の反対を招く「根回し」不足
事前の根回しが不十分な場合も、意思決定の遅れにつながりがちです。
このようなケースでは、公式な会議や稟議の場で初めて内容を提示し、関係者から想定外の反対意見が出てしまい、最終段階で議論が振り出しに戻ることが多々あります。
原因6:過去の意思決定の経緯がブラックボックス化
「なぜこのルールになったのか」「以前の担当者はどう判断したのか」といった、過去の意思決定の経緯がブラックボックス化しており、担当者が変わるたびに同じ議論を繰り返してしまう問題です。これも組織としての学習を妨げ、非効率を生み出します。
意思決定プロセス改善に向けた実践的アプローチ
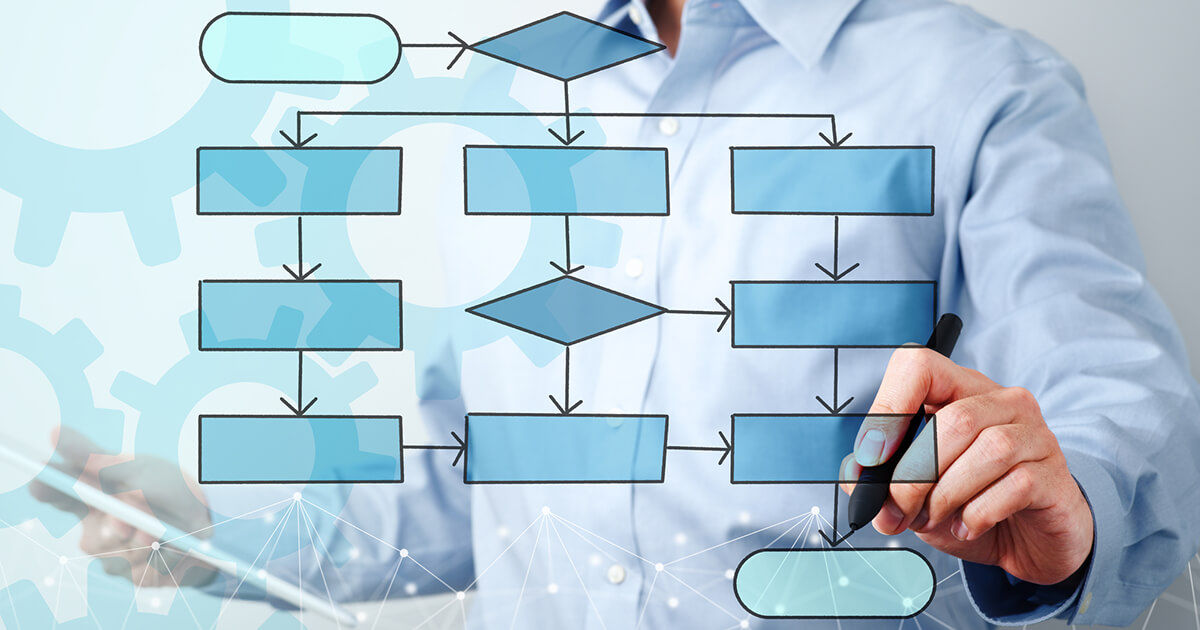
次は、意思決定プロセスを改善に導く実践的なアプローチをご紹介します。
承認ルートや回覧ルールの仕組み化
意思決定プロセスを改善するには、承認ルートや回覧ルールを見直し、仕組み化することが大切です。
先にお伝えした通り、承認ルートが煩雑化していたり、職務権限が不明瞭な状態では、起案から回覧、承認・決裁というプロセスに多くの無駄や非効率が生じてしまい、結果として意思決定の遅れを招いてしまいます。
自社の組織編成や、自社で行われる稟議の種類を整理し、承認ルートや回覧時に守るべきルールを明確化しましょう。
稟議書フォーマットの最適化
稟議書フォーマットの最適化も、意思決定プロセスの改善につながります。
たとえば、稟議書フォーマットの入力項目に不足があったり、記載すべき内容が分かりにくかったりする場合、情報の抜け漏れによる差し戻しが生じやすくなります。
また、部署部門や担当者によってはフォーマットが違ったり、古いバージョンの稟議書フォーマットを使っているといった状況も、意思決定の遅延やナレッジ活用の妨げにつながりかねません。
自社の業務プロセスに合わせて稟議書フォーマットを最適化し、一元的に管理する体制を整えることで、上記のような状況を防ぎ、意思決定の円滑化につなげることができるでしょう。
また、稟議書フォーマットの最適化と合わせて、従業員に対する教育・周知を行うことで、意思決定スピードの底上げにつながります。
どのケースでどの稟議書フォーマットを使用するのか、各入力項目には何を記載し、どんなポイントを意識して書けばいいのかなどについて、定期的に研修を行ったりマニュアルを作成したりしましょう。
ナレッジ活用の土台を整備
ナレッジ活用の仕組みを整えることも、意思決定プロセス改善につながる大切な取り組みです。
過去の意思決定が「どのような経緯で、どのように処理されたのか」といった証跡を、後から参照できるような形で記録しておくことで、組織全体のナレッジとして活用することが可能になります。
蓄積されたナレッジにアクセスすることで、新たに起案する際のアイデアの参考にしたり、承認・決裁の判断材料にしたりでき、より精度の高い意思決定につなげることができるでしょう。
紙ベースの決裁から電子決裁への移行
紙とハンコによるアナログな承認プロセスは物理的な制約が多く、テレワークなどの多様な働き方の普及も相まって限界を迎えています。
申請書を印刷し、ハンコをもらうために出社し、次の承認者に手渡しするといった一連の作業は、多くの無駄を含んでいます。
電子決裁は、これらの非効率を根本から解消し、業務生産性を飛躍的に向上させる手段として注目されています。そして、この電子決裁を実現するとともに、先に紹介した3つのアプローチを加速するソリューションが「ワークフローシステム」です。
ワークフローシステムとは、稟議などの手続きを電子化するツールのことで、業務プロセスの可視化や承認ルート・回覧ルールの標準化、稟議書フォーマットの最適化や一元管理、ナレッジマネジメントの強化などにも効果を発揮します。
意思決定プロセスを劇的に改善するワークフローシステム
今回は、変化が激しい時代における意思決定の重要性や基礎知識、意思決定の遅れを招く原因と改善に向けたアプローチを解説しました。
意思決定プロセスを改善するためのアプローチはいくつかありますが、そのなかでも本質的なアプローチが、先にも触れたワークフローシステムの導入です。
株式会社エイトレッドが提供するワークフローシステム「X-point Cloud」と「AgileWorks」は、シリーズ累計5,000社超の導入実績を誇り、業種業界や組織規模を問わず多くの企業の意思決定プロセス改善に役立てられています。意思決定のスピードや精度の向上を目指している方は、ぜひお気軽にご相談ください。
資料をダウンロード(無料)
意思決定プロセスを改善!稟議デジタル化の効果とは?
稟議のデジタル化が企業経営にどのようなメリットがあるのか解説します。
こんな人におすすめ
・意思決定のスピードを上げたい。
・バックオフィスの効率化を図りたい
・デジタル稟議の事例を見たい。
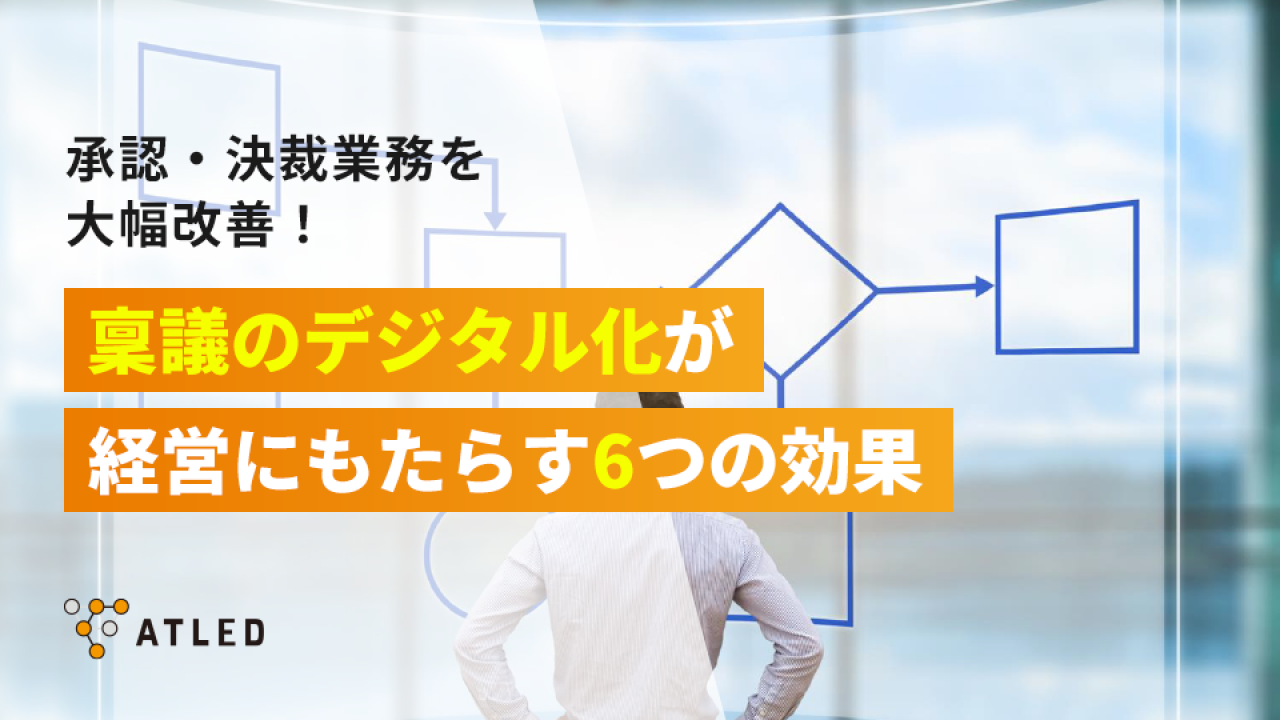

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。






