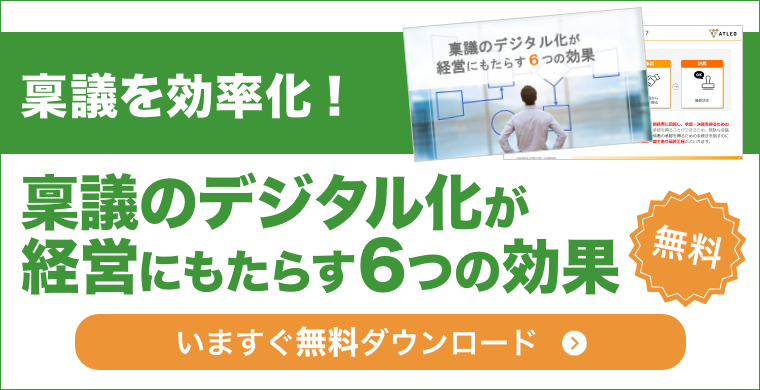ナレッジマネジメントとは?重要性や取り組み方、役立つツールを紹介!
- 更新 -
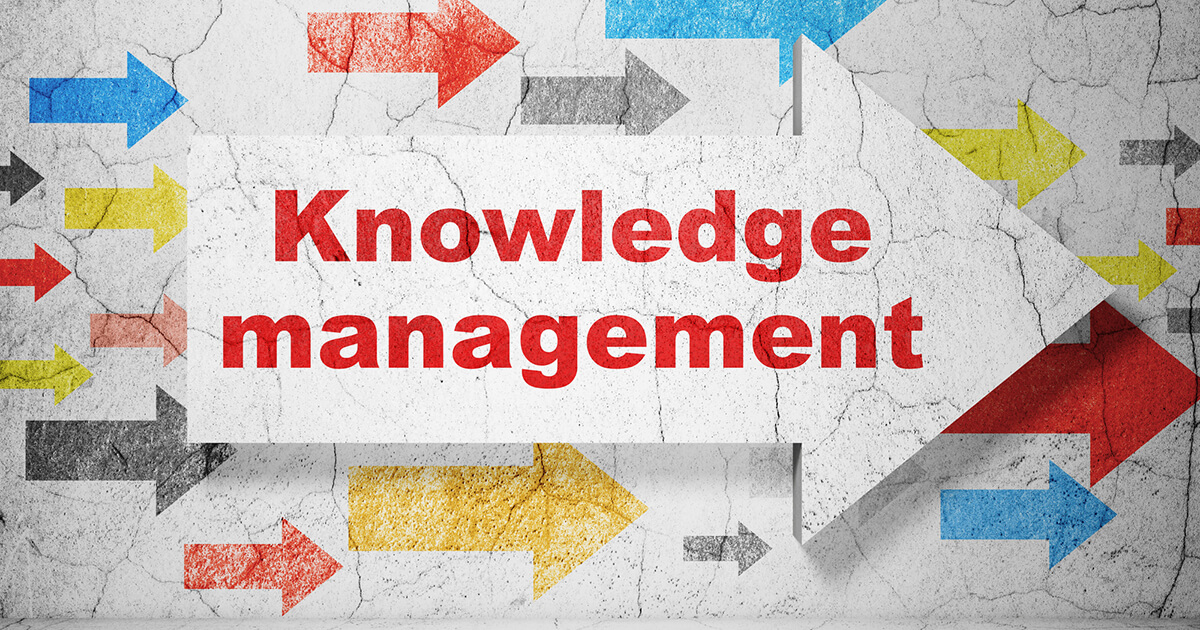
企業経営におけるマネジメント手法のひとつに、「ナレッジマネジメント」という手法があります。
ナレッジマネジメントの概念は1990年代に誕生したとされていますが、近年再び注目を集めています。
一方で、
「ナレッジマネジメントとは?」
「ナレッジマネジメントはなぜ重要?」
「ナレッジマネジメントの取り組み方は?」
といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、ナレッジマネジメントの意味や重要性、取り組み方について解説。
ナレッジマネジメントに役立つツールや成功事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
ナレッジマネジメントとは?
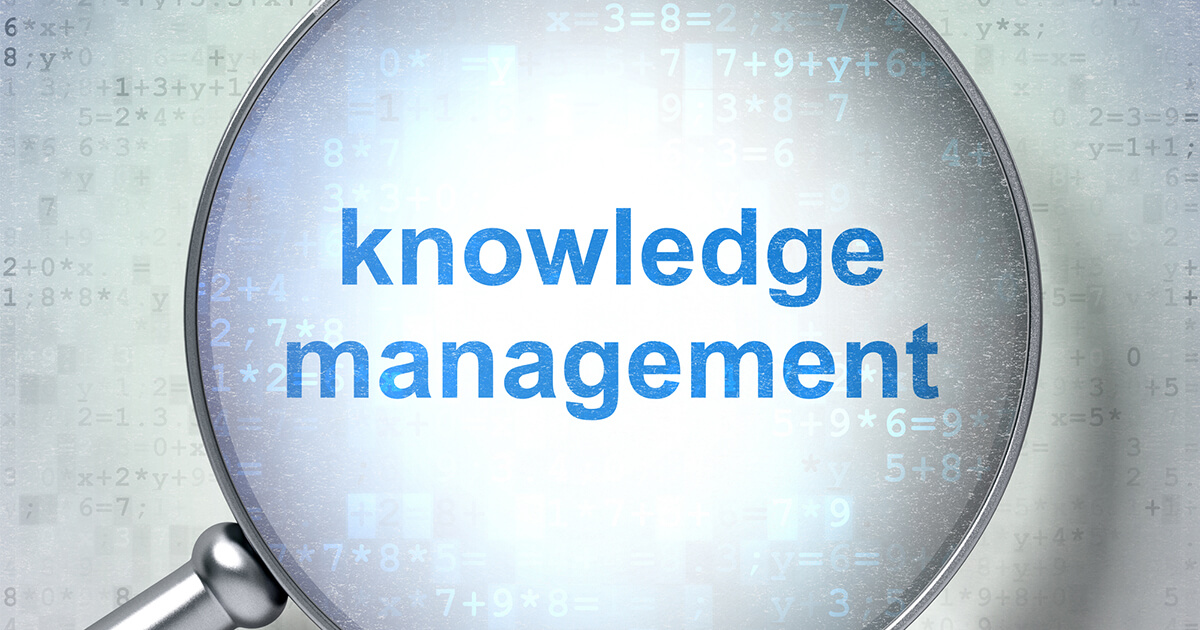
ナレッジマネジメント(Knowledge Management)とは、従業員個人が持っているナレッジ(知識)を組織内で共有・活用して、組織全体の生産性向上やイノベーションの創出を促進するための管理手法です。
日本語で「知識経営」や「知識管理」とも呼ばれます。
1990年代初頭、経営学者の野中郁次郎氏による著作「知識創造企業」のなかで、「組織的知識創造理論」と「SECI(セキ)モデル」が提唱されたことで、ナレッジマネジメント(知識経営)という概念が広く知られるようになりました。
ナレッジマネジメントにおけるナレッジには、従業員の持つノウハウやスキル、データなどが含まれます。
そして、これらのナレッジは「暗黙知」と「形式知」の2つに分類されます。
ナレッジマネジメントを実践していくうえでは、個人が持つ暗黙知を形式知へと変換し、組織全体で共有・活用していくことが鍵となります。
暗黙知とは?
暗黙知とは、個人が保有している知識のなかでも言語化・可視化されていない知識を指します。
経験や勘といった主観的な感覚に基づいており、属人化しているため共有や利活用のハードルが高いのが特徴です。 たとえば、熟練の職人技やデザイナーのセンス、あるいはベテランの営業担当者の話術などは、暗黙知と言えるでしょう。暗黙知の特徴
- 言語化・可視化されていない知識
- 経験や勘などの主観的な感覚に基づいている
- 属人化しているため共有や利活用のハードルが高い
形式知とは?
形式知とは、言語化や可視化された知識のことを指します。
形式知は客観的な情報やデータに基づく知識であり、暗黙知にくらべて共有や利活用が容易なのが特徴です。
たとえば、業務マニュアルや作業手順書、e-learning形式の社内学習コンテンツなどは、言語化・可視化されて体系的にまとめられた形式知の代表例だと言えます。
形式知の特徴
- 言語化・可視化されている
- 客観的な情報やデータなどに基づいている
- 他者への共有や利活用が容易
ナレッジマネジメントが注目を集める理由

ナレッジマネジメントが注目を集めている主な理由として、以下の3点を挙げることができます。
ナレッジマネジメントが注目を集める理由
- 人材の流動化が加速
- 生産性向上が急務
- テレワークの普及
それぞれ詳しく確認していきましょう。
人材の流動化が加速
ナレッジマネジメントが注目を集める理由のひとつとして、人材の流動化が加速していることが挙げられます。
従来、日本企業では新卒一括採用に代表されるメンバーシップ型雇用が主流であり、終身雇用を前提とした働き方が一般的でした。
しかし近年、働き方改革による多様な働き方の促進や、欧米で主流のジョブ型雇用が普及してきたことで、人材の流動性が高まりつつあります。
そのため、従来は長い期間をかけて継承・蓄積されてきた知識が、組織内で引き継がれることなく人材の入れ替わりが発生してしまうケースが増えてきているのです。
ナレッジの喪失を防ぎ、継続的な成長につなげるためにも、ナレッジマネジメントの重要性が見直されてきているのです。
生産性向上が急務
ナレッジマネジメントの重要性が高まっている理由として、国内企業の生産性向上が急務となっている点も挙げることができます。
市場のグローバル化が急速に進む一方で、日本企業の生産性は先進各国のなかでも低水準であることが指摘されています。
公益財団法人 日本生産性本部が公表している「労働生産性の国際比較 2021」では、日本の時間あたりの労働生産性はOECD加盟38か国中23位、一人あたりの労働生産性は38か国中28位であることが示されています。
※参照:労働生産性の国際比較2021 | 調査研究・提言活動 | 公益財団法人日本生産性本部
グローバル化が進む市場のなかで日本企業が競争を勝ち抜いていくためには、ナレッジマネジメントに取り組み、組織全体の生産性を高めていくことが重要だと言えるでしょう。
テレワークの普及
ナレッジマネジメントが注目を集める背景として、テレワークの普及も関係しています。
テレワーク勤務では、従来のオフィス勤務のように従業員の業務を目で見て確認することができません。従業員同士で直接顔を合わせる機会が減少するため、コミュニケーションによる知識の伝達・共有機会が減少する可能性があります。
テレワークの普及が進む昨今、業務の属人化を防ぎつつ従業員の持つ知識を組織全体で共有・利活用するためのナレッジマネジメントの必要性が増してきているのです。
企業がナレッジマネジメントに取り組むメリット
ここまでは、ナレッジマネジメントの概要や必要性が高まっている背景についてお伝えしてきました。
次は、企業がナレッジマネジメントに取り組むことのメリットについて詳しく見ていきましょう。
ナレッジマネジメントのメリット
- 業務効率や生産性の向上
- 人材育成の効率化
- テレワークの促進
業務効率や生産性の向上
ナレッジマネジメントに取り組み組織全体で知識の共有が進むことで、業務効率や生産性の向上に効果が期待できます。
属人化していた暗黙知が形式知に変換されることで、業務の改善点が見つかったり、新たなアイデアが生まれるきっかけとなるかもしれません。
また、従業員が退職や休職してしまった際も、業務に必要な知識やノウハウが形式知化されていれば、業務の停滞やトラブルを回避することができるでしょう。
人材育成の効率化
ナレッジマネジメントの取り組みは、人材育成の効率化という面でも効果的です。
暗黙知を形式知に変換する仕組みが整えば、「見て技術を盗む」「実務経験のなかで感じ取る」といった形で習得していたナレッジを、明文化・可視化されたマニュアルや学習コンテンツで伝達することが可能になります。
そのため、効率的に人材育成を行うことが可能になり、これまで人材育成に費やしていた期間やコストを削減することができます。
これは、近年注目を集めている人材育成の手法である「リスキリング」においても有効だと言えます。
テレワークの促進
テレワークの促進・定着という面でも、ナレッジマネジメントの取り組みは有効です。
先述の通り、テレワークでは対面のコミュニケーションを通じて暗黙知を共有・伝達することが困難です。
ナレッジマネジメントによって暗黙知を形式知に変換していくことで、対面のコミュニケーションではなくても、言語化・可視化された業務マニュアルや学習用コンテンツから必要なナレッジを習得することが可能になります。
組織全体でナレッジを共有できる仕組みが整えば、テレワークでも円滑に業務を遂行することができるでしょう。
「SECIモデル」とは?
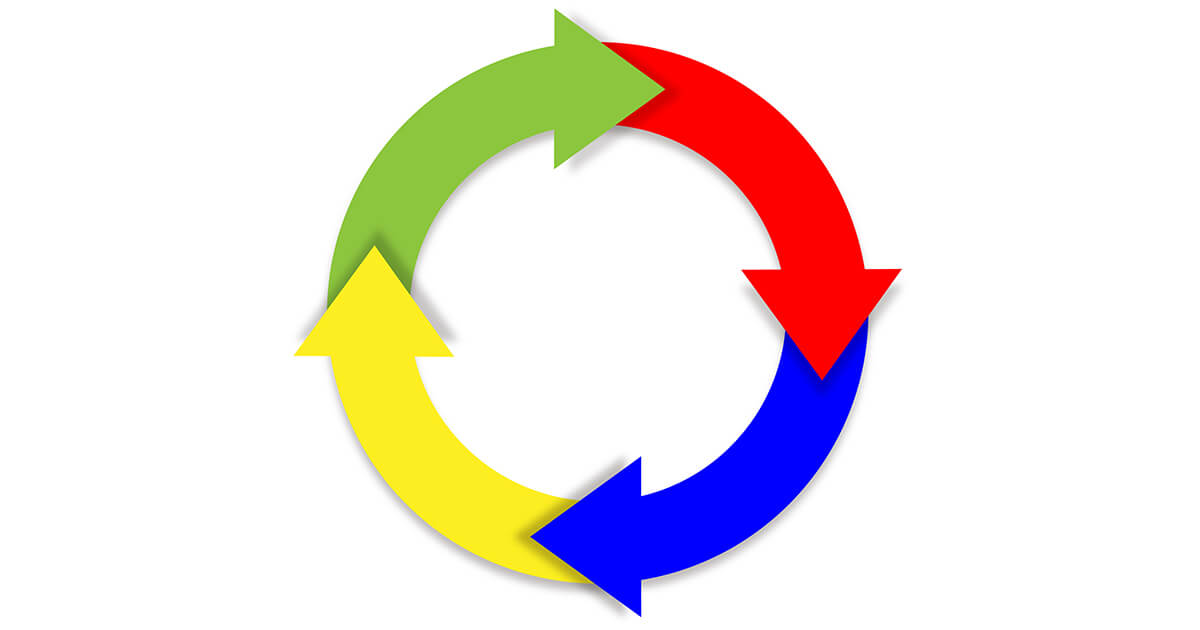
ナレッジマネジメントにおいては、個人が持つ暗黙知を形式知に変換していくことが大切だとお伝えしました。
そして、暗黙知を形式知に変換し、新たなナレッジを創造していくために役立つのが、「SECI(セキ)モデル」と呼ばれるフレームワークです。
SECIモデルは、「共同化(Socializaiton)」「表出化(Externalization)」「連結化(Combination)」「内面化(Internalization)」という4つのプロセスから成り立ちます。
SECIモデルのプロセス
- 共同化(Socializaiton)
- 表出化(Externalization)
- 連結化(Combination)
- 内面化(Internalization)
次は、SECIモデルの各プロセスについてその概要を確認していきましょう。
共同化(Socializaiton)
共同化(Socializaiton)とは、共通の体験を通じて個人が保有する暗黙知を共有するプロセスです。
共同化の例としては、OJTやロールプレイング、営業同行などが挙げられます。
共同化のプロセスは、あくまで体感・共感による暗黙知の伝達であり、形式知への変換はなされていない状態です。
表出化(Externalization)
表出化(Externalization)は、体感・共感として伝達した暗黙知を、形式知へと変換するプロセスです。
テキストベースで言語化する方法のほか、映像やグラフによる可視化などの方法を使って、他者に伝えやすい形式に変換していきます。
連結化(Combination)
連結化(Combination)は、表出化プロセスを経て変換された形式知を組み合わせ、新たな知識体系を創造するプロセスです。
たとえば、複数の部門でノウハウや事例を持ち寄ってマニュアルを作成する行為は、連結化のプロセスに該当します。
この連結化のプロセスにより、組織としてナレッジを活用することが可能になります。
内面化(Internalization)
内面化(Internalization)は、体系的に整理された形式知を実践して体得するプロセスです。
実際に形式知を活用することで新たな暗黙知が生まれ、組織全体でナレッジを共有・創造するサイクルを循環することが可能になります。
ナレッジマネジメントの強化にワークフローシステムが有効

ナレッジマネジメントに有効なフレームワーク「SECIモデル」をご紹介しましたが、具体的に何から手を付けるべきかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そのような場合、ワークフローシステムの導入から始めてみるのもひとつの方法です。
ワークフローシステムとは、組織内で行われる申請や稟議などの各種手続きを電子化するツールのことで、ナレッジマネジメントの強化に役立てることができます。
次は、ワークフローシステムがナレッジマネジメントの強化に役立つ理由をご紹介します。
業務の流れが可視化される
ワークフローシステムを導入する際は、社内で行われている業務を整理し、システム上に業務の流れを再現していきます。
その過程で「誰が」「何の業務を」「どのように行っているのか」といった点が整理され、業務上必要な情報や流れが可視化されます。
これにより、業務の属人化が解消され、ナレッジマネジメントを推進するための基盤が整います。
ナレッジを結集した意思決定が可能に
ワークフローシステムを活用することで、社内のナレッジを結集した意思決定が可能になります。
ワークフローシステムには、過去の申請・決裁に関するデータがシステム上に蓄積していくため、必要に応じて参照することができます。
さらに、申請に対して承認者がコメントを追記することができるため、決裁までの過程で起案内容をブラッシュアップしていくことも可能です。
このような特徴から、過去の決裁データやナレッジを結集した意思決定を行うことができます。
情報共有のスピードアップ
ワークフローシステム導入により、情報共有のスピードアップも見込めます。
ワークフローシステムで日報などの書類を作成・申請すると、事前に設定したルールに基づき回覧ルートが自動で判別されます。
また、閲覧権限を個別に設定することもできるので、セキュリティに配慮しつつスピーディーに関係者へと情報共有することができるでしょう。
上記に挙げた以外にも、ワークフローシステムには数多くのメリットが存在します。
ワークフローシステムについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
ワークフローシステム導入によるナレッジマネジメント強化事例
最後に、ワークフローシステムでナレッジマネジメントを強化した事例について紹介します。
SCSK株式会社様のワークフローシステム導入事例
SCSK株式会社様(当時は住商情報システム株式会社)は、「基幹情報システム(ERP)刷新」の一環としてワークフローシステムを導入しています。
そして、同社のワークフローシステム導入の目的のひとつとして、「意思決定のナレッジマネジメント」が掲げられていました。
これは、ワークフローシステムを導入することで意思決定プロセスがデータベース化され、各人の意思決定ノウハウがナレッジとして蓄積・共有されることにより、全社的な意思決定スキルの向上が期待できる、という考えです。
ワークフローシステムを導入したことで、一元的かつ電子的な意思決定プロセスを全社規模で確立することに成功。
過去の起案内容を参照して類似起案の一部に再利用したり、起案内容に工夫を加えてさらに進化させることができるなど、意思決定におけるナレッジマネジメントにワークフローシステムが役立てられています。
株式会社ソーキ様のワークフローシステム導入事例
株式会社ソーキ様は、「情報共有環境の整備」を目的にワークフローを導入しています。
同社は「ヒト」「チエ」という経営資源を最大限活用することに重きを置いており、そのためには情報共有環境の整備が欠かせないと考えていました。
そこで、承認・決裁といった業務プロセスの適正化はもちろん、現場で発生する定型・不定形の情報が細切れになることなく連動するような仕組みを構築するため、ワークフローシステムの導入を決定しました。
ワークフローシステムを導入したことで、業務の効率化・迅速化に加えて、正確さの向上にも効果を実感。
スピーディかつクリアに会社の状態を把握できる体制を構築することに成功しています。
まとめ
今回は、ナレッジマネジメントの意味や必要性、ナレッジマネジメントに役立つツールや事例をご紹介しました。
ナレッジマネジメントは、組織の生産性向上やイノベーションの促進に効果的なマネジメント手法であり、その重要性に着目する企業が増えつつあります。
そして、ナレッジマネジメントの強化に役立つITシステムがワークフローシステムです。
これからナレッジマネジメントに取り組みたいと考えている企業は、今回ご紹介した情報も参考にナレッジマネジメントの第一歩としてワークフローシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
もっと知りたい!
続けてお読みください

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。