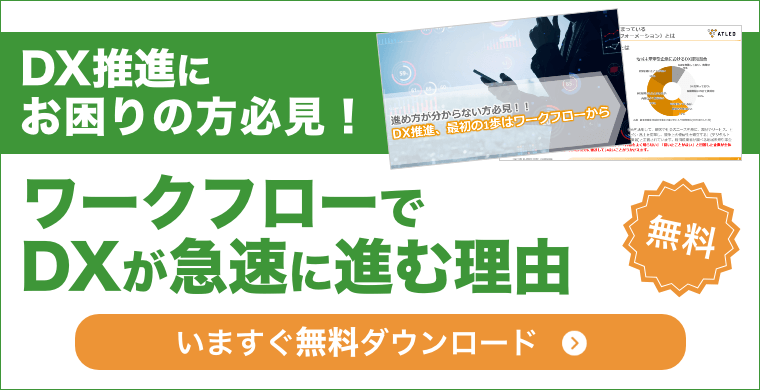自治体DXとは?急務とされる背景や国の動き、推進のポイントなどについて解説!
- 更新 -

2021年9月のデジタル庁発足、コロナ禍以降ニューノーマルへの対応など、近年さまざまな業種・業態でデジタル化が求められるなか、DX推進が急務とされる業界の1つに自治体が挙げられます。
そこで今回は、 「自治体DXってなに?」 「自治体DX何からはじめればいい?」 「自治体DX推進はどうする?」 といった自治体DXに関する基礎知識や推進のポイントなどについてご紹介したいと思います。
\DXの基礎知識について知りたい/
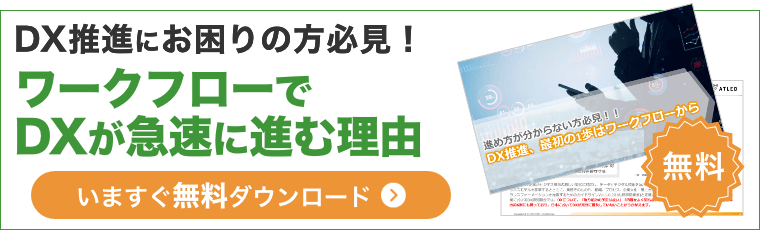
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
そもそもDXって?

自治体DXについて詳しく説明する前に、まずはDX「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」について解説します。
DXの定義は、「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドラインVer. 1.0(2018、経済産業省)」によると以下の通りになります。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
DXというと、デジタル化やIT化を思い浮かべる人も多いかと思いますが、それらは、単なる手段に過ぎません。 その本質は、業務や組織、プロセス、企業文化や風土を変革し、競争上の優位を確立することにあるということを念頭においておきましょう。
DXについて詳しく知る
自治体の課題

DXについて理解できたところで、次は、自治体DXが急務とされる背景を知るために、現在自治体が抱えている課題について整理しましょう。
1.職員数の減少
少子高齢化が深刻化するなか、自治体でも労働人口減少の傾向が顕著なものとなりつつあります。
総務省が発表した「地方公共団体の総職員数の推移」によると、2021年4月1日時点での総職員数は、ピーク時の平成6年と比較して約48万人減少しているそうです。
対応しなくてはならない業務が年々増え続ける状況下で、職員数の減少が続けば行政サービスの維持が困難になると予測されます。
2.アナログ文化
2020年の「脱ハンコ」に引き続き「FAX廃止」が昨今話題となりましたが、これらに代表されるアナログ業務は、未だ自治体に数多く残っています。
押印やFAXといった紙でのやりとりを前提としたアナログ業務は、さまざまな側面で効率が悪く、働き手の減少に輪をかけて自治体職員の負担を増やしてしまいます。
ペーパーレス推進により脱アナログを図りたい
自治体DXとは

少子高齢化やコロナ禍などを背景に、住民のライフスタイルは多様化の一途をたどる一方で、自治体が前述のような課題を抱えたままだと、住民の一人ひとりのニーズに応えることが困難になるだけではなく、行政サービスの存続自体も危うくなってしまいます。
そこで、こうした事態を打破すべく政府により打ち出されたのが自治体DXです。
つまり、自治体DXとは、少ない人数でも業務を効率的にまわし生産性を向上させる仕組みを構築することで、住民に対する行政サービスの維持・向上を図ろうとする取り組みです。
自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画
それでは、自治体DXにおける政府の具体的な動きを見てみましょう。
2020年12月25日、総務省は「デジタル化社会の実現に向けた改革の基本方針」において、目指すべきデジタル社会のビジョンとして、「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会~誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化~」を掲げました。
そして、このビジョンを実現するためには、とりわけ自治体の取り組みが重要であるとし、 「自治体デジタル・トランス フォーメーション(DX)推進計画」を策定し、2021年1月から2026年3月までの期間で自治体が重点的に取り組むべき6つの施策を示しました。
重点的に取り組むべき6つの施策
- 自治体情報システムの標準化・共通化
- マイナンバーカードの普及促進
- 行政手続のオンライン化
- AI・RPAの利用推進
- テレワークの推進
- セキュリティ対策の徹底
1.自治体情報システムの標準化・共通化
自治体における主要な17の業務について、原則2025年を目標に国が策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行することを義務付けました。
各自治体で共通の情報システムを利用することで、職員にとっては業務負担の軽減、住民にとっては、手続きの簡素化・迅速化、地域間によるサービス格差の是正などの効果が期待できます。
17の業務 住民基本台帳 (2022年開始)/選挙人名簿管理/固定資産税/個人住民税/法人住民税/軽自動車税/国民健康保険/国民年金/障害者福祉/後期高齢者医療/介護保険/児童手当/生活保護/健康管理/就学/児童扶養手当/子ども・子育て支援
2.マイナンバーカードの普及促進
2022年度末までに国民のほとんどがマイナンバーカードを保有することを目標に、出張申請受付や臨時窓口の設置など、マイナンバーの申請促進及び交付体制の充実を図る取り組みが各自治体で行われています。
これは、オンライン手続きの際にマイナンバーを本人確認の手段として用いることを想定しており、後述する「自治体行政手続のオンライン化」を円滑に進める上でも重要な施策であるといえます。
3.自治体行政手続のオンライン化
行政手続のオンライン化が進むことにより、これまで仕事や育児等の事情により、役所まで行くことが難しかった住民の利便性の向上が期待できます。
具体的な施策としては、マイナポータルが挙げられます。
マイナポータルとは、行政手続のオンライン窓口であり、マイナンバーを使用して本人確認を行います。行政に関する手続きのオンライン申請のほか、自身の情報の確認、行政機関からのお知らせ通知などのサービスを受けることができます。
4.AI・RPAの利用推進
AI・RPAを活用した実証実験をはじめ、自治体に向けてAI・RPA導入ガイドブックを作成・共有するなどの取り組みが行われています。
情報システムの標準化や行政手続きのオンライン化による業務の見直しを契機に、AI・RPAの利用を推進し、膨大な事務作業を自動化することで、相乗的に業務効率化の効果を出す狙いがあります。
RPAについて詳しく知る
5.テレワークの推進
職員それぞれのライフスタイルに合わせた多様な働き方の実現はもちろんのこと、新型コロナウイルスの感染拡大などの非常事態において、行政の機能を維持するBCPの観点からも自治体のテレワーク普及は重要であるといえます。
現在は政府主導による実証実験をはじめ、導入事例やノウハウの共有といった取り組みが行われています。
BCPについて詳しく知る
テレワークできないを解決する
6.セキュリティ対策の徹底
行政手続きのオンライン化やテレワーク推進に伴い、個人情報の流出などセキュリティ面でのリスクの高まりが懸念されることから、セキュリティポリシーガイドラインの改定(2020年)や、総務省が認定するセキュリティレベルの高いクラウドシステムへの移行支援等の取り組みが行われています。
クラウドシステムについて詳しく知る
自治体DX推進手順書の作成
「自治体DX推進手順書」とは、自治体が円滑かつ着実にDX推進に取り組むための一連の流れをまとめたものです。DX推進の手順を4つに分けた「全体手順書」や取り組み事例を紹介する「参考事例集」などからなります。
ここでは、「参考事例集」で取り上げられている事例についていくつか紹介します。
電子決裁機能付き文書管理システムの導入で行政事務を効率化(愛知県瀬戸市)
愛知県瀬戸市では、一部の部署で試行中だった電子決裁機能付きの文書管理システムについて、2022年度末までの全庁展開完了を目指しています。
これらの取り組みにより、書類の作成および回付、保存、検索に関連する業務の大幅な効率化が期待されます。
電子決裁について詳しく知る
出勤簿をペーパーレス化しテレワークを実現(京都府)
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、テレワークを実施しようとしたところ、出勤簿の紙での運用が大きな足かせとなりました。
そこで京都市では、パソコンへのログイン情報を既存システムと連携させることで職員の出勤状況を一元管理する仕組みを構築しました。
この取り組みにより、テレワークの導入が実現されたほか、出勤簿自体を廃止することが可能になり、入力の手間の削減など業務の改善にも成功しました。
業務改善について詳しく知る
自治体DX最初の1歩はワークフローシステム
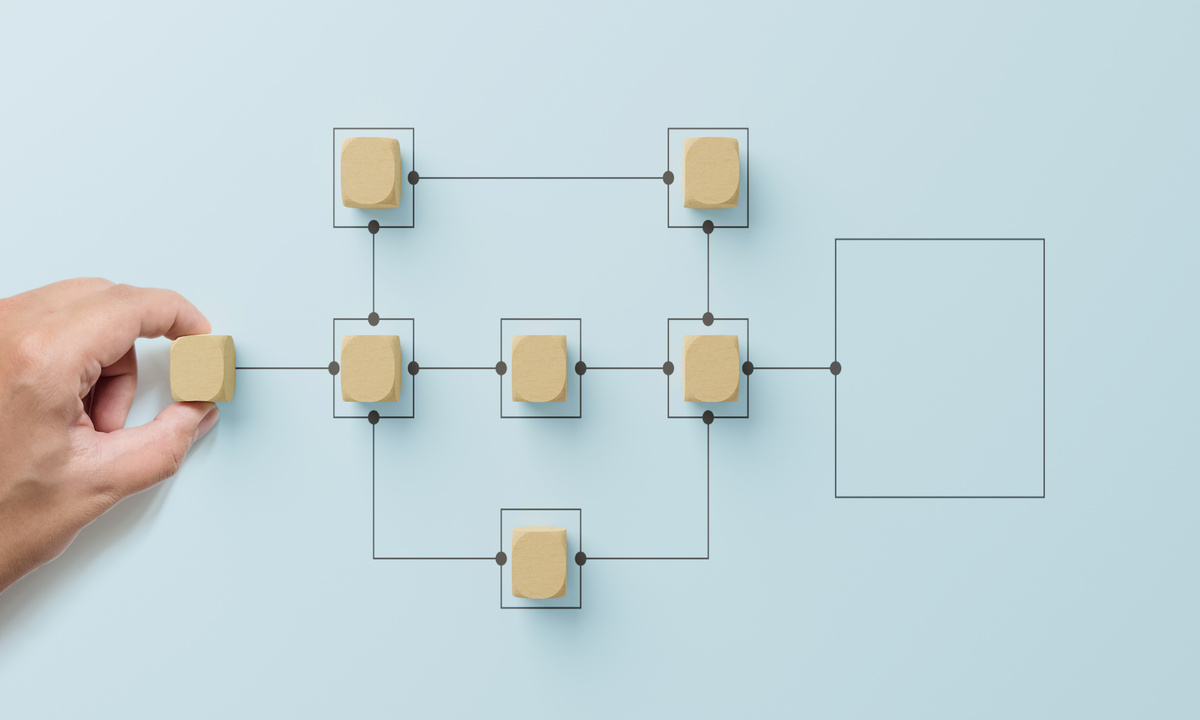
ここまで、自治体におけるDX推進の重要性について説明してきましたが、自治体DXについて、何から着手していいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、自治体DXの最初の1歩としておすすめしたいのがワークフローシステムです。
ワークフローシステムとは社内で行われる稟議・申請手続きを電子化するシステムです。
導入することで、さまざまな効果を得ることができます。
自治体DXにワークフローシステムが役立つ理由
それでは、ワークフローシステムが自治体DX推進に効果的な理由についてみてみましょう。
ペーパーレス化の推進
前述にあるように、自治体では従来より紙ベースのアナログ業務が職員の負担となっていました。
しかし、ワークフローシステムを導入することにより、これらを電子化することができるため、書類の作成や回付、承認、検索などあらゆる業務を大幅に効率化することができます。
ペーパーレス化について詳しく知る
柔軟な働き方の実現
コロナ禍における「脱ハンコ」宣言に象徴されるように、自治体はこれまで紙に印刷された申請書の回付や承認・決裁がネックとなりテレワークを実施することができませんでした。
しかし、ワークフローシステムを導入することで、決裁における時間と場所の制約を解消することができるため、テレワークをはじめとした柔軟な働き方を実現することが可能になります。
テレワーク未導入の自治体必見
セキュリティ強化
住民の大切な情報を取り扱う自治体において、経年劣化による情報の損失や、不正な持ち出し、改ざんといったリスクは可能な限り回避したいものです。
ワークフローシステムであれば、文書をデータとして取り扱うため、劣化・損失の心配がなく、閲覧権限の個別設定や証跡管理が可能なため、不正を未然に防止することができます。
自治体におけるワークフローシステム導入のポイント
総務省が、1788の都道府県・市区町村の情報通信部局を対象に実施した「地域IoT実装状況調査」(令和2年度調査)によると、IoT実装に向けた地域の課題として、「財政がきびしい(18.1%)」、「担当する人員が足りない(16.0%)」が多く挙げられました。
このことから、予算とデジタル人材の不足が自治体DXを推進するうえで大きな足かせとなっていることがうかがえます。
それでは、どのようにすれば、これらの阻害要因を取り除くことができるでしょうか。
答えは、ノーコードのものを選ぶということです。
ノーコードとは、コードを書かない開発を指します。
ITの専門知識が一切不要なため、デジタル人材がいない組織でも内製で運用することが可能であることから、開発やメンテナンスなど外注にかける莫大なコストを削減することができます。
【「システムを導入しても使いこなせるか不安」というお悩み解決します!】
コストを抑えてスピーディーに導入するならクラウド型ワークフローシステム「Xpoint Cloud」 ★ノーコードなのでITの専門知識は不要 ★紙のような入力フォームで誰でも直感的に使える ★1ユーザー月額500円だから気軽にはじめられる ★シリーズ累計3500社以上の安心の実績
→Xpoint Cloudの資料を見てみたいまとめ
今回は自治体DXに焦点を当て、その意味や急務とされる背景、DX推進におけるワークフローシステムの有効性などをご紹介しました。
自治体が少ない人数の中でも行政サービスの質を高めていくためには、既存の業務を見直し効率化を図ることが必要不可欠です。
そして、業務効率化を行うために、ワークフローシステムの導入は非常に有効な手段だと言えます。 今回ご紹介した情報も参考に、自治体DXの取り組みの一環としてワークフローシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。