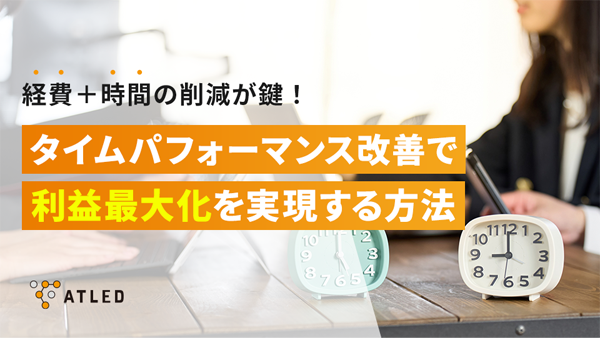医療DXとは?メリット・デメリットや政府の動き、推進の第1歩におすすめのシステムを紹介!
- 更新 -
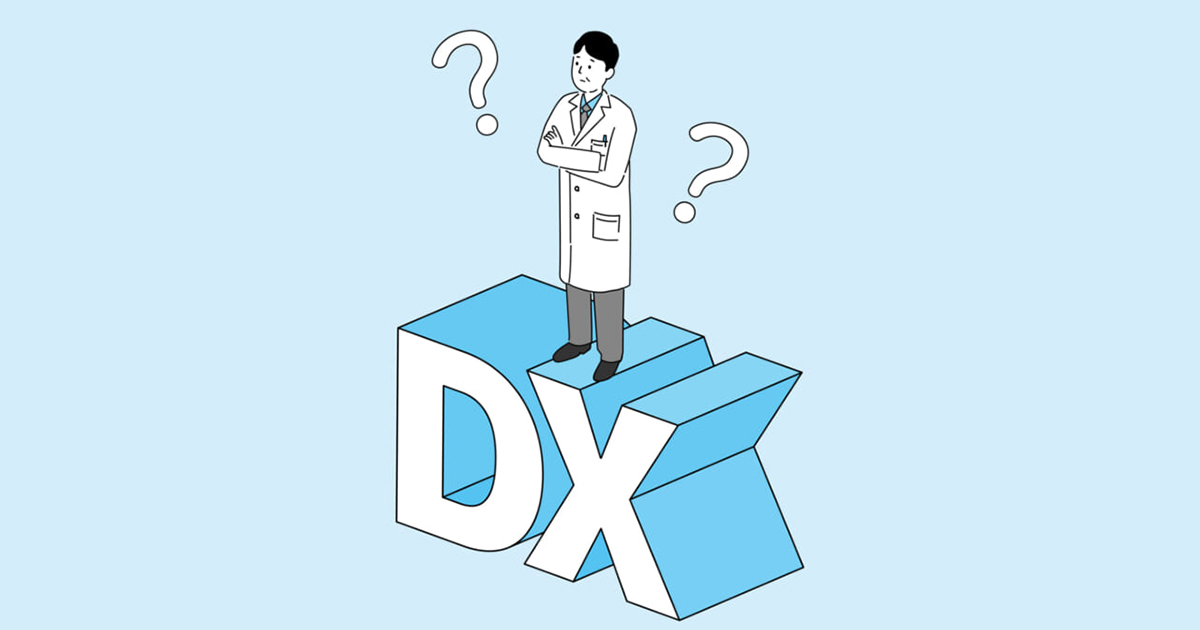
さまざまな業界でDXの必要性が叫ばれる昨今ですが、今もっとも変革が必要な業界の1つに医療業界が挙げられます。
地域による医療格差、看護師や医師の人材不足に加え、昨今では、新型コロナウイルスの感染拡大により新たな課題も次々に浮上してきました。
そこで今回は、医療業界の課題解決のヒントとして、「医療DX」に焦点をあて、現在の医療業界における課題や、政府や医療現場での取り組み、医療DXに適したツールなどをご紹介します。
医療DXの成功事例をご紹介!
【ユーザー登壇】医療バックオフィスDX
AgileWorksが切り拓く業務効率化と組織改革
実際に医療の現場から業務改革をリードする医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院様にご登壇いただき、
ワークフローシステム「AgileWorks」の活用による、バックオフィスの業務効率の改善と組織全体の意識の改革に成功した事例についてご紹介します。
こんな人におすすめ
★医療機関のバックオフィス担当者様
★医療DXに興味がある
★医療現場の業務を効率化したい
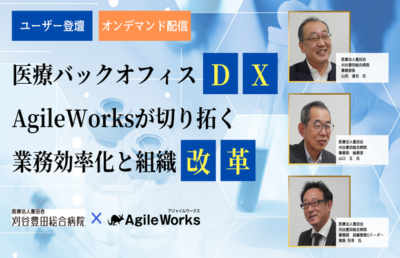
医療業界における課題
まず、現在の医療現場にはどのような課題があるのでしょうか。具体的にみてみましょう。
- 人材不足
- デジタル化の遅れ
- 長時間労働
- 医療機関の経営難
1.人材不足
近年の少子高齢化の影響により、治療を必要とする患者と、医師・看護師など医療従事者との需給のバランスが崩壊しつつあります。
とくに2025年には「団塊の世代」が後期高齢者に到達し、人口構成は大きく変化すると予想されています。これにより引き起こされる諸問題は「2025年問題」と呼ばれ、なかでも医療業界への影響が懸念されています。
厚生労働省が発表している「令和6年版厚生労働白書」によれば、2025年にかけて高齢者人口、とりわけ75歳以上の後期高齢者人口が急速に増加し、2040年に向けて高齢者人口は緩やかに増加を続ける一方で、現役世代である生産年齢人口の減少は加速していくと示されています。
つまり、高齢者の医療・介護ニーズが増加していく一方で、医療・介護現場における人材確保は一層困難になっていくと考えられます。
外来患者数は2025年頃、入院患者数は2040年頃、在宅患者数は2040年以降に最も多くなると試算されており、急激に増加する医療・介護ニーズに対し医療従事者の人材不足解消は急務だと言えるでしょう。
2.デジタル化の遅れ
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が2023年3月に発行した「DX白書2023」によると、「医療、福祉」産業のDXの取り組み状況はおよそ9%であり、他の産業と比較して大きく遅れていることが示されました。
実際に、病院をはじめとした医療機関では、カルテや問診票、処方箋、物品購入の手続きなど紙ベースのアナログ業務が残存しているところが多く、医療従事者の業務効率を著しく悪化させています。ここで、株式会社エイトレッドが公表している「医療施設の事務業務に関する実態調査」の結果を見てみましょう。
この調査では、稟議や申請・承認業務で「ワード、エクセルに記入、印刷して申請」が37.3%、「紙に手書きして申請」が19.6%を占め、約6割の医療施設で申請を紙ベースで行っていることがわかりました。
また、紙ベースの申請・承認業務の課題として、「申請から承認までのスピードが遅い」、「無駄な工程が多い」、「申請に手間がかかる」といった声が多く上がりました。
これらの調査結果を踏まえると、医療施設におけるデジタル化の遅れは深刻な状況であり、医療DXを推進していくためにもペーパーレス化などの取り組みが急務であることがうかがえます。
3.長時間労働
1.2.で挙げた要因も相まって、医療業界の長時間労働が常態化しています。
また、1.2.の解決目途が立っていないにもかかわらず、いわゆる2024年問題への対応も医療業界の喫緊の課題となっています。
2024年問題とは、これまで医師に対して猶予されてきた時間外労働の上限が2024年4月から適用されたことを指します。
これにより、医師においても時間外労働と休日労働時間の上限は「月100時間未満、年間960時間以下」が原則となりました。
現状では、病院常勤勤務医の約4割が年間960時間、約1割は年間1,860時間の時間外・休日労働をしていると言われており、この状況を打破するには医療DXは不可欠だと言えるでしょう。
4.医療機関の経営難
厚生労働省が令和6年3月が公表した「令和5年度医療施設経営安定化推進事業 病院経営管理指標及び医療施設における経営管理の実態に関する調査研究」の報告書によれば、令和4年度の医療法人立の黒字病院比率(経常利益)は一般病院で67.2%、ケアミックス病院で70.4%、療養型病院で68.2%、精神科病院で75.2%となっています。
平成30年度の76.2%(一般病院)、74.2%(ケアミックス病院)、80.2%(療養型病院)、80.2%(精神科病院)と比較すると、いずれの類型も黒字病院比率が減少しており、病院の経営が厳しくなっていることがうかがえます。
また、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大がさらに医療機関に追い打ちをかけたことはいうまでもありません。コロナ患者との接触を避けるための受診控えにより患者が激減したことが原因で、閉院を余儀なくされる医療機関も見受けられました。
医療DXとは?

現在の医療業界における課題が分かったところで、次は今回のテーマでもあり、医療業界の課題解決の鍵となる「医療DX」について詳しくみてみましょう。
医療DXとは、医療分野(病院・薬局・訪問看護ステーションなどの医療機関)におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)のことを指します。
医療の現場において、デジタル技術を活用することで、医療の効率や質を向上させることを目的としています。
医療DXの主な取り組み
医療DXの代表的な取り組みは以下の通りです。
ペーパーレス化
前述にもあるように、医療現場ではカルテや問診表をはじめ多くの紙業務が残存しています。これらの紙業務をデジタル化することで、患者の情報を正確かつ迅速に共有できるほか、文書管理に関連するコストやスペースを大幅に削減することができます。
オンライン予約/問診
診察の受付や問診表の記載といった受診手続きをデジタル化することで、医師のスケジュール管理がしやすくなり、診療時間の無駄を減らすことができます。また、患者にとっても、受診までの待ち時間を短縮できるなど利便性の向上が期待できます。
オンライン診療
オンライン診療とは、ビデオ通話や電子メール、チャット等のメッセージアプリを通じて、オンライン上で医師とやりとりしながら診断や治療を受けることができる診療方法を指します。
オンライン診療では、患者の利便性の向上や医療機関の効率化の他、遠隔地からの受診も可能になるため、地域間の医療格差の是正などの効果も見込めます。
ビッグデータの活用
医療機関が保有する大量の医療情報(診療記録や検査結果、処方情報など)をビッグデータとして分析・活用することで、疾患の早期発見や新薬の開発、健康管理のサポート、治療方針の個別化などに役立てることができます。
医療DXのメリット
医療DXの定義や取り組みについて分かったところで、次は医療DXを推進することでどのような効果を得ることができるのか、医療DXのメリットについてご紹介します。
医療DX推進のメリット
- 患者の医療体験の向上
- 医療現場の業務効率化
- BCPの強化
- コストの削減
患者の医療体験の向上
医療DXが推進されることで、患者にとってのさまざまな医療体験が向上します。
たとえば、医療情報の共有が円滑化・迅速化されることで、より適切な医療を受けることができます。
また、オンラインでの診療が可能になれば、非対面や遠隔地からの受診も可能になります。
そのことにより、院内感染を恐れる必要もなくなり、医師不足の地域に居住していても、通院負担を軽減しながら専門的な医療を受けることができるようになります。
さらに、来院する場合においても、事前予約ができるため待ち時間を軽減できるほか、面倒な書類の記入についても、オンライン上で済ますことができます。
医療現場の業務効率化
医療物品の在庫管理や診療報酬明細書の作成、経理関連の業務など、医療機関には多くの定型業務が存在します。
これらを、デジタルツールを用いて自動化することで、医療従事者の大幅な業務効率化やコストの削減、長時間労働の解消といった効果が期待できます。
問診票の受け渡しなど患者との物理的な対応が減ることで、医療従事者の業務負担を軽減することができます。
BCPの強化
医療データを紙や自社のサーバーのみで保管していると、災害の規模によっては、データを喪失してしまう恐れがあります。
いかなる状況であっても、ライフラインである医療事業を維持するために、クラウドサービスを活用し、BCPを強化しておくことは医療DXにとって不可欠であるといえます。
コストの削減
医療DXの進展により各種システムの標準化やクラウド化が進むことで、システム運用や改修における人的・財政的コストが削減されます。
また、これまでアナログな方法で行われていた間接業務・定型業務が効率化・自動化されることで、人件費の節約にもつなげることができるでしょう。医療DXのデメリット
さて、ここまでで、医療業界におけるDX推進の取り組みが不可欠であることは分かったと思うのですが、懸念点が全くないわけではありません。医療DXには、下記のようなデメリットがあります。
医療DX推進における懸念点
- セキュリティの問題
- 医療従事者のITリテラシー
- デジタル格差
セキュリティの問題
これまで紙で運用・管理していた患者の診療情報をデータ化することにより、情報漏洩やハッキングのリスクが高まります。
そのため、医療DXを実施する際はセキュリティ面を十分に考慮しながら進める必要があります。
医療従事者のITリテラシー
デジタルツールを導入する場合、同時に、システムのトラブルシューティングやアップグレード、メンテナンスなどの作業が発生します。
選択するシステムによっては、専門的な知識やスキルが必要になることがあるため、医療機関での専門人材の採用・育成や、外部ベンダーへの外注が必要になる場合があります。
デジタル格差
デジタル技術に習熟していない高齢者や、デジタルアクセスが制限されている人々は、医療DXの恩恵を受けることができない可能性があります。
医療DXにおける政府の動き
国を挙げた医療DXの取り組みも積極的に行われており、そのひとつとして「医療DX令和ビジョン2030」を挙げることができます。
「医療DX令和ビジョン2030」とは、2022年5月に自由民主党政務調査会が提言した方針です。
以下の3つの施策を同時並行で進め、医療業界における情報・データの在り方を抜本的に変えることで、医療現場と患者の双方に利益をもたらすことを目指します。
「全国医療情報プラットフォーム」の創設
オンライン資格確認システムのネットワークを拡大し、クラウド間連携を行うことで、これまでバラバラに管理・保管されてきた医療情報(電子カルテや処方箋、予防接種、特定検診情報など)について、一元管理できる体制の構築を目指します。
これにより、医師や薬剤師、自治体、介護業者などの間での情報共有がスムーズになり、患者にとってより良い医療が提供できるようになります。
また、患者もマイナポータル経由で自身のデータにアクセスできるようになるため、自発的な健康促進が期待できます。
電子カルテ情報の標準化(全医療機関への普及)
「電子カルテ情報および交換方式の標準化」と、「標準電子カルテの検討」をすることで電子カルテ導入率100%を目指します。
電子カルテ情報および交換方式の標準化について、厚生労働省が令和4年3月にHL7 FHIRを標準規格として採択し、まずは3文書6情報の交換の手順を定めました。
※3文書:診療情報提供書、退院時サマリー、健診結果報告書6情報:傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(緊急時に有用な検査、生活習慣病関連の検査)、処方情報
また、「標準電子カルテの検討」における標準電子カルテとは、標準規格に準拠した電子カルテを想定しており、関係者へのヒアリングを実施しながら、現在、小規模医療機関向けの開発が検討されています。
厚生労働省の発表によると、令和2年時点での電子カルテシステムの普及率は、一般病院で57.2%、一般診療所では49.9%にとどまり、目標である導入率100%を目指すためには、積極的な取り組みが必要であるといえます。
診療報酬改定DX
これまで、診療報酬改定のたびに限られた日数でのシステム改修が必要となり、医療機関の従業員やベンダーにとって大きな業務負担となっていたため、ベンダーが共通で利用できる「共通算定モジュール」を導入したり、作業集中を解消するために診療報酬改定の施行日を後ろ倒しにするなどの施策がとられました。
医療DX最初の1歩はワークフローシステム
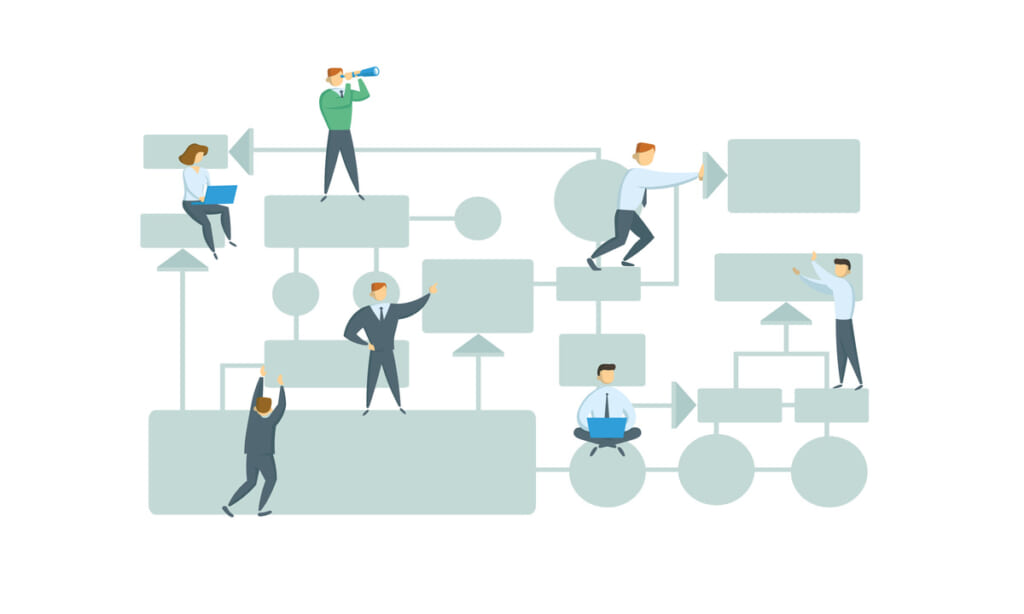
ワークフロー総研が2022年6月に実施した調査によると、医療現場が特にデジタル化の必要性を感じている事務業務として稟議決裁(41.2%)が挙げられました。
そこで、医療DXの第1歩としておすすめしたいのが、ワークフローシステムです。
/ サクッと学ぼう! 『1分でわかるワークフローシステム』 無料ダウンロードはこちら \
ワークフローシステムとは、稟議をはじめとした業務手続きをデジタル化するシステムで、導入することで医療現場にさまざまな効果をもたらします。
ワークフローシステムが医療DXに効果的な理由
- 全従業員が利用できる
- 外出先からも申請・承認を行える
- 紛失・改ざんのリスクを軽減できる
- システム連携でデジタル化の範囲を拡張できる
では、ワークフローシステムが医療DXの推進に役立つ理由について詳しく見ていきましょう。
全従業員が利用できる
稟議決裁をはじめとした業務手続きは、事務担当だけではなく医師や看護師、すべての医療従事者が行います。
また稟議以外にも、休暇や勤怠の申請や各種報告書、経費精算書など、医療機関ではさまざまな申請・承認が行われます。
ワークフローシステムを活用することでこれらの各種手続きを電子化することができ、組織全体の業務効率化につなげることができるでしょう。
外出先からも申請・承認を行える
製品にもよりますが、ワークフローシステムの中には、スマホやタブレット端末から申請・承認できるものもあります。
医療従事者のなかでもとくに医師は研修や学会、訪問診療など外出する機会が多い一方、承認者・決裁者であるケースが珍しくありません。
モバイル端末での申請・承認機能を搭載したワークフローシステムを導入することで、外出等による意思決定の遅延を回避しつつ業務効率化を実現することができます。
紛失・改ざんのリスクを軽減できる
医療機関の稟議決裁では、患者の診療情報や研究に関することなど重要な情報を記載添付することがあるため、紛失・改ざんのリスクが高い紙での運用はあまり適切であるとはいえません。
一方、稟議決裁がワークフローシステム上で行われるようになれば、証跡を残すことができるので改ざんの心配がなく、大震災などが発生した際でも書類を紛失することはありません。
システム連携でデジタル化の範囲を拡張できる
ワークフローシステムの特徴として、システム連携によりデジタル化の範囲を拡張していける点を挙げることができます。
たとえば、ワークフローシステムで処理したデータを各業務システムに連携することで、システム間での転記作業を自動化したり、マスタ管理の負担を軽減することが可能です。
また、DXの取り組みでは、各業務領域でシステム・ツールが乱立してしまい、かえって利便性が下がってしまう状況に注意が必要です。ワークフローシステムをハブに各種システムを連携していれば、各システムにおける手続きを一元化することができるでしょう。
ワークフローシステムで医療DXを推進した事例
次に、医療DX推進にもおすすめのワークフローシステムとして、シリーズ累計4,500社以上の導入実績を誇る「AgileWorks」と「X-point Cloud」を取り上げ、実際に導入・活用している医療機関の事例を見ていきましょう。
【システム連携に強いパッケージ型ワークフローシステム】
>AgileWorksの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)
【国内シェアNo.1のクラウド型ワークフローシステム】
>X-point Cloudの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)
ペーパーレスとシステム運用の内製化を促進(医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院)
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院は、紙帳票で運用していた業務の効率化を図り、「AgileWorks」を導入してペーパーレスを推進しました。
同院ではかねてより電子カルテや複数の医療系システムを導入して医療現場のデジタル化を進めていた一方、事務・管理業務では紙帳票が多用されており、帳票の回付やエクセルへの転記作業などに多くの労力を費やしていました。また、一部業務においては既存グループウェアのワークフロー機能でペーパーレス化を進めていたものの、メンテナンスに専門知識が求められるため運用が複雑で、帳票の追加・改修の際には外部ベンダーへの依頼が必要でした。
そこで同院は、豊田会全体で進められている業務効率化プロジェクトの一環としてワークフローシステムの導入を決定。多くの職員を抱えている同院においては、「ユーザー数による課金」ではなく「同時接続数ごとの課金」という料金体系であること、そしてネットワークセキュリティを厳格に保つことができるオンプレミス製品であることが決め手となり、「AgileWorks」の導入に至りました。
8ヶ月に及ぶ導入プロジェクトを経て、現在のユーザー数は約2,400名、豊田会のほぼずべての職員が利用できる環境となっており、運用開始からの半年間で約10,000件の申請を「AgileWorks」上で処理しています。
たとえば病院内設備の修理・廃棄などに関する作業依頼は年間3,000件以上に上りますが、「AgileWorks」の導入後は作業全体のリードタイムが約20%短縮され、作業進捗の見える化も実現。さらに、直感的な操作性のUIなので、専門的な知識がなくても帳票や回付ルールの作成・改修などを行えるようになりました。
医療DXの成功事例をご紹介!
【ユーザー登壇】医療バックオフィスDX
AgileWorksが切り拓く業務効率化と組織改革
実際に医療の現場から業務改革をリードする医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院様にご登壇いただき、
ワークフローシステム「AgileWorks」の活用による、バックオフィスの業務効率の改善と組織全体の意識の改革に成功した事例についてご紹介します。
こんな人におすすめ
★医療機関のバックオフィス担当者様
★医療DXに興味がある
★医療現場の業務を効率化したい
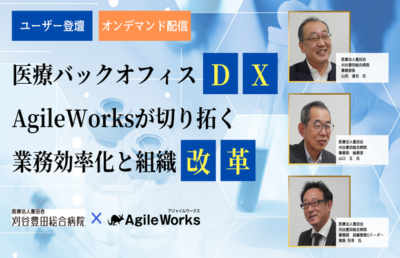
コア業務に専念できる環境を整備(医療法人健誠会 湯田内科病院)
医療法人健誠会 湯田内科病院は、「X-point」を導入して稟議・申請などの事務作業をペーパーレス化しました。
電子カルテや介護システムなど、医療や介護の現場ではITを活用して一定の成果をあげていた一方で、付随する事務業務に関しては、システム化が遅れていたという同院。
とくに、稟議決裁については、簡易的なワークフローシステムを利用していたものの、システムの機能がシンプルで、帳票画面の使い勝手なども制限があったことから、利用者に受け入れてもらえず、紙の稟議書と並行して利用せざるを得ない状況でした。
このような状況のなか、専用ワークフローシステムであるXpointを導入したところ、ユーザーに「使いやすさ」が評価され、およそ900人の職員に利用が広がり、これまで最長で10日かかっていた稟議がほぼ翌日に決裁されるようになりました。
まとめ
デジタル化の遅れが指摘されている医療業界ですが、昨今の新型コロナウィルスの感染拡大により、もともと抱えていた課題がより浮き彫りになったことや、政府が本格的に動き出したことで、今後、医療DXの取り組みは加速度的に広がるのではないでしょうか。
医療現場が変革しようとしている今だからこそ、大きな波に乗り遅れないように、まずはワークフローシステムから、医療DXの最初の1歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
医療DXの成功事例をご紹介!
【ユーザー登壇】医療バックオフィスDX
AgileWorksが切り拓く業務効率化と組織改革
実際に医療の現場から業務改革をリードする医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院様にご登壇いただき、
ワークフローシステム「AgileWorks」の活用による、バックオフィスの業務効率の改善と組織全体の意識の改革に成功した事例についてご紹介します。
こんな人におすすめ
★医療機関のバックオフィス担当者様
★医療DXに興味がある
★医療現場の業務を効率化したい
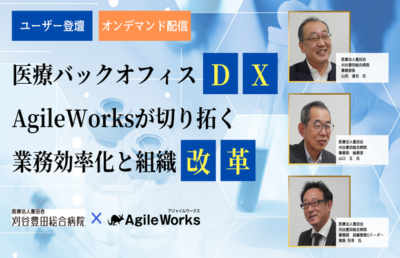

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。