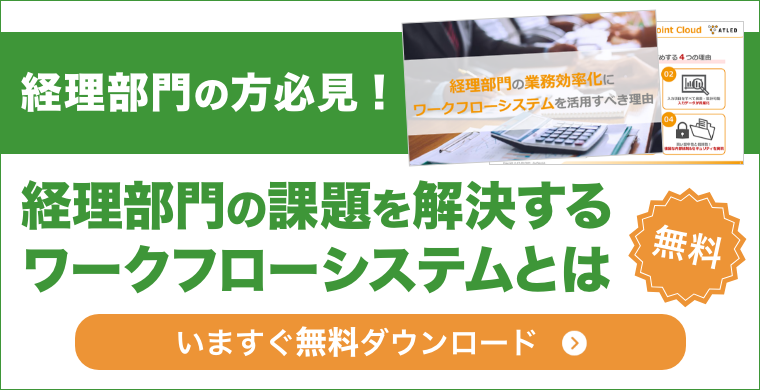決算とは?基礎知識や決算業務を効率化するポイントを解説!
- 更新 -
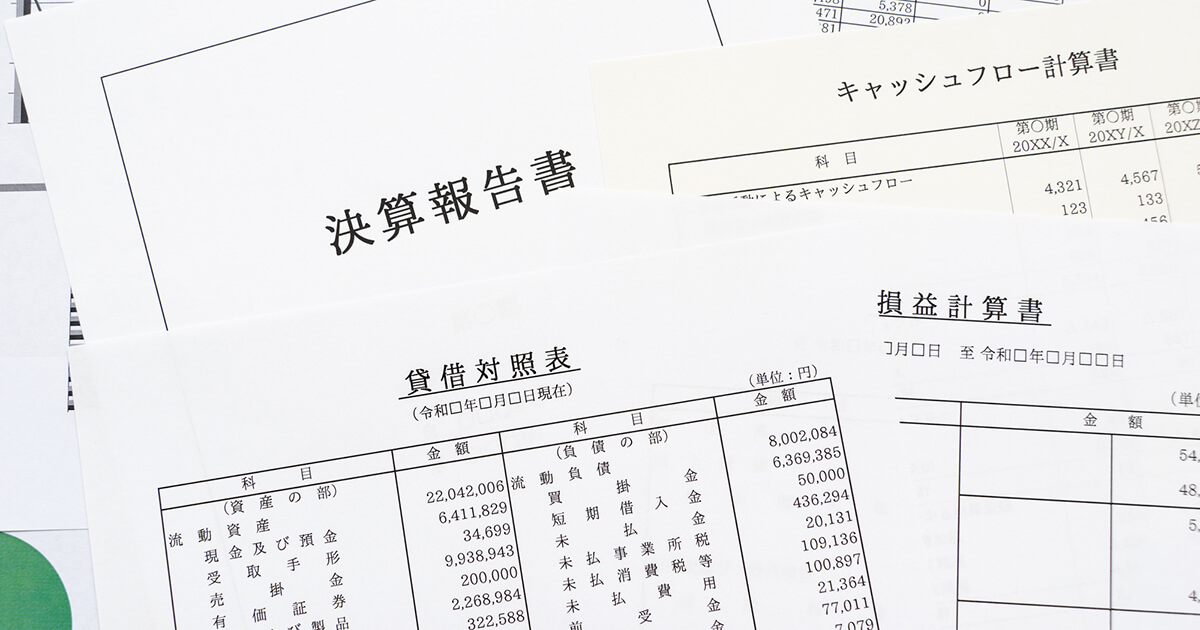
業種業界を問わず、あらゆる企業にとって欠かせない重要な業務のひとつに「決算」があります。
経営状況を適切に把握・報告するためには決算を行うことが不可欠ですが、
「決算の意味や必要性は?」
「決算で作成する書類は?」
「決算業務を効率化するには?」
といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、決算にまつわる基礎知識や主な決算書の種類、決算業務を効率化するポイントについて解説します。
決算業務の効率化を実現した事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
決算とは?

決算とは、事業年度における損益を算出し、決算日時点での資産や負債といった財務状況を確定する一連の手続きです。
株式会社においては、会社法で「決算公告」が義務付けられており、定時株主総会の終結後速やかに決算公告を行わなければなりません。
また、上場企業は3か月ごとの四半期決算の開示が義務付けられていたり、財務状況をより綿密に把握するために1か月ごとの月次決算を実施している企業も珍しくありません。
まずは基礎知識として、決算を行う理由や決算時期について確認していきましょう。
決算を行う理由
企業が決算を行う理由として、大きく以下3点を挙げることができます。
- 財務状況の把握
- ステークホルダーへの情報開示
- 納税額の確定
それぞれ詳しく見ていきましょう。
財務状況の把握
決算を行う理由のひとつとして、財務状況の把握を挙げることができます。
決算によって自社の財務状況を正確に把握することは、客観的な意思決定を行う上で非常に重要です。
反対に、財務状況を正しく把握していなければ、新規事業への参入や不採算事業の整理といった重大な経営判断を下すことは困難だと言えるでしょう。
ステークホルダーへの情報開示
決算を行う理由として、ステークホルダー(利害関係者)への情報開示という側面もあります。
企業は、株主や債権者、投資家などのステークホルダーに対して利益を還元する責任があり、その責任を果たすには適切な情報開示が不可欠です。
会社法で「決算公告」が義務付けられているように、企業は決算で確定した財務状況をステークホルダーに対して公開・報告する必要があるのです。
納税額の確定
決算を行うことは、納税額を確定する意味でも必要です。
企業や個人事業主は、決算日の翌日から2か月以内に確定申告によって納税額を報告し、納税を完了しなければなりません。
そして、納税額を算出するためには、決算で確定した財務状況を基に計算する必要があります。
決算の時期とは?
次は、1年に1度の年次決算、いわゆる「本決算」の時期について確認していきましょう。
法人の場合、事業年度の最終月が「決算期(決算月)」となります。
事業年度は任意で設定することができるため、企業によって決算のタイミングが異なります。
たとえば、事業年度が「4月1日から3月31日まで」の企業であれば、毎年3月が決算期です。
国税庁が公表しているデータによれば、3月決算の法人がもっとも多く、次いで9月決算の法人が多いことが示されています。
(参照:(3)決算期月別法人数|国税庁)
一方で個人事業主の場合は、確定申告の対象期間が1月1日から12月31日の1年間と定められているため、決算期は必然的に12月となります。
決算書とは?
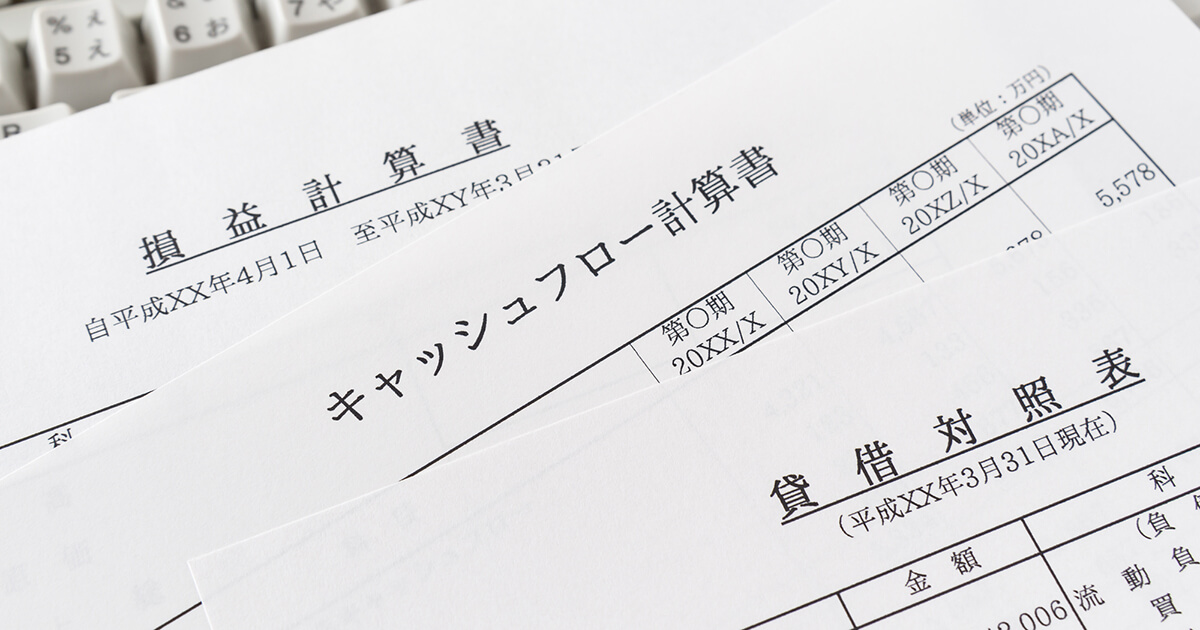
決算業務では、さまざまな書類を作成する必要があります。
決算の際に作成する書類を総称して「決算書」や「財務諸表」と言いますが、なかでも重要な役割を果たすのが「財務三表」と呼ばれる以下の3つです。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- キャッシュフロー計算書
では、主な決算書の概要について確認していきましょう。
損益計算書(P/L)
損益計算書は、当該事業年度における利益を把握するための書類のことで、「P/L(Profit and Loss Statement)」とも表記されます。
損益計算書は、利益や損失の原因を読み解く際に役立てることができます。
貸借対照表(B/S)
貸借対照表とは、決算日における財政状況を示す決算書で、「B/S(Balance Sheet)」とも表記します。
貸借対照表は、会社が保有する「資産」および返済義務がある「負債」、返済義務がない「純資産」などの把握に役立ちます。
キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書は、当該事業年度の現金の流れを把握するための書類で、「C/F(Cash Flow Statement)」とも表記されます。
営業活動による現金の増減、投資活動による現金の増減、営業活動や投資活動を維持するための現金の増減を、キャッシュフロー計算書から読み解くことができます。
決算業務の基本的な流れ

決算業務は、以下のような流れで行います。
決算業務の基本的な流れ
- 決算残高の確定
- 税金の計算
- 決算書の作成・承認
- 税金の申告・納付
詳しく確認していきましょう。
決算残高の確定
経理業務を担当する部門では、日々の取引を記録して、総勘定元帳や仕訳帳といった会計帳簿を作成しています。
決算業務では、事業年度における全期間の記帳をとりまとめ、決算残高を確定する必要があります。
すべての勘定科目について、実際の残高と一致しているかを確認し、減価償却費や棚卸差額の計上といった「決算整理仕訳」を行います。
会計帳簿に記載されている情報が正確でない場合、決算残高の確定作業に多くの工数を要してしまいます。日々の帳簿作成業務を正確に行うことが大切だと言えるでしょう。
税金の計算
決算残高が確定したら、消費税や法人税などの税金の計算を行います。
消費税については、売上取引で預かった消費税から仕入取引で支払った消費税を差し引いて消費税額を計算します。確定した消費税額は、未払消費税額として後述する決算書に計上します。
次に、法人税や法人住民税、事業税などの税金を計算しますが、会社の規模や利益によって税率が異なるため注意が必要です。
これらの税金の計算は専門性が高いため、税理士などの外部専門家に依頼するケースも多いです。
決算書の作成・承認
次に、確定した決算残高を基に決算書を作成します。処理方法の変更などがある場合には、注意事項としてその旨を記載する必要があります。
作成した決算書は、取締役会や監査役、会計監査人などによる承認を経て、株主総会に提出・報告します。
税金の申告・納付
確定した決算書を基に各種税金の申告書を作成し、確定申告を行います。
申告期限は決算日(事業年度の最終日)の翌日から2か月以内となっているため、遅延がないよう速やかに取り掛かりましょう。
決算業務を効率化する鍵は帳票の電子化

ここまでは、決算の基本的な知識や決算書について解説してきました。
決算業務は、財務・経営状況を正確に把握するために不可欠であり、正確性が求められます。
また一方で、決算時期は決まっているため遅れは許されず、多くの書類を作成しなければならないため、決算業務はタイトなスケジュールとなってしまいがちです。
そうしたなか、正確かつ迅速に決算業務を遂行する鍵となるのが、帳票の電子化です。
決算業務では、日々の金銭の動きを記録した帳票類の情報を基に決算書を作成していく必要があります。
帳票を電子データとして運用する場合、取引先名や取引年月日、金額などの情報で検索することが可能になり、必要な情報を速やかに参照することが可能になります。
紙ではなくデータであれば、決算業務の担当部門に帳票を集約することも容易なので、決算のための帳票処理がスムーズになるでしょう。
また、帳票内の情報をテキストデータとして扱えるので、コピー&ペーストでミスのリスクを軽減しつつ効率的に会計システムに入力することができます。会計システムとデータ連携すれば、入力作業を自動化することも実現できるでしょう。
ワークフローシステムが決算の効率化に役立つ理由

次は、帳票の電子化、そして決算業務の効率化を実現する具体的なソリューションとして、ワークフローシステムをご紹介します。
ワークフローシステムとは、稟議・申請などの社内手続きを電子化するツールのこと。
では、ワークフローシステムが決算業務の効率化・迅速化に役立つ理由を確認していきましょう。
/
サクッと学ぼう!
『1分でわかるワークフローシステム』
無料ダウンロードはこちら
\
決算書の基となる各種帳票を電子化
ワークフローシステムでは稟議書・申請書だけでなく、入出金伝票や経費精算書などの会計関連帳票を電子化することが可能です。
先述の通り、決算業務では日々の金銭の動きを記録した帳票を基に決算書を作成します。
ワークフローシステムで帳票類を運用することで、目視による確認や手作業による入力よりも経理関連業務の効率性・正確性を高めることができるでしょう。
決算関連の帳票の社内承認を効率化
決算関連の帳票のなかには、社内承認を必要とする帳票も少なくありません。
たとえば、経費申請書や仮払精算書などの経費精算関連の帳票は、然るべき承認を経て処理する必要があります。
ワークフローシステムで帳票を運用している場合、事前に設定したルールに基づき、適切な承認ルートを自動判別して速やかに回付することができます。
また、承認が滞っている承認者に対して督促通知を送ることもできるため、決算関連の社内承認を効率化することができるでしょう。
外部システムとの連携でさらに利便性向上
ワークフローシステムは、外部システムとの連携によって利便性をさらに高めることが可能です。
たとえば、ワークフローシステムと会計システムと連携することで、ワークフローシステムで処理した帳票データを会計システムに取り込み、決算書の作成を効率化・自動化することが可能です。
以下の記事では、ワークフローシステムと好相性なシステム・ツールを紹介しています。あわせてお読みください。
ワークフローシステムで決算の効率化・早期化に成功した事例
最後に、ワークフローシステムを利用して決算の効率化・早期化を実現した事例をご紹介します。
申請処理を約4割削減し、決算の早期化も実現
一般社団法人KEC関西電子工業振興センターは、申請業務の効率化を図りワークフローシステムを導入しました。
同法人では従来、社内稟議や各種申請、経費精算などを紙ベースで運用しており、書類作成や回付の手間、そして処理業務が大きな負担となっていました。
とくに会計関連の申請書は会計システムへの転記が必要で、一人あたり年間200時間以上が費やされていました。
そこで同社はワークフローシステムを導入し、各種申請の電子化に着手しました。
ワークフローシステムの導入から約2年間で17種類の申請書を電子化し、現在は年間約5000件の申請をワークフローシステムで処理。
さらに、ワークフローシステムで処理したデータを会計システムに連携することで、手作業や目視による転記・ダブルチェックも不要になりました。
その結果、申請書の処理業務が従来よりも約4割削減されたほか、導入以前よりも早期の月次決算が可能になるなど、大きな効果を実感されています。
基幹会計システムへのデータ連携で月次決算を早期化
総合物流会社である株式会社ギオンは、ワークフローシステムの導入によって月次決算の早期化を実現しています。
同社では従来、取引先への債権計上(請求書)および債務計上(支払依頼書)、従業員の経費精算(立替金精算/仮払金精算)などに関わる帳票を各事業所で作成し、本社の経理課に提出する運用方式を採用していました。
しかし、これらの債権・債務や経費精算の情報を基幹会計システムに入力するためのオペレーション業務が膨大に発生していました。
そこで同社は、ワークフローシステムを導入して債権・債務計上および経費精算を処理する仕組みを構築。
これにより、各事業所で作成した債権・債務や経費精算のデータを直接期間会計システムに連携することができるようになり、本社経理課に集中していた膨大なオペ―レーション業務の工数が削減され、月次決算の早期化を実現しました。
まとめ
今回は、決算の基礎知識や決算書の書き方、決算業務を効率化するポイントを解説しました。
記事内でも触れた通り、決算は経営状況を把握するために不可欠であり、正確さだけでなく迅速さも求められる業務です。
そして、決算業務を効率化するには、帳票の電子化が重要な鍵となります。
今回ご紹介した情報も参考に、ワークフローシステムで帳票の電子化、そして決算の効率化・早期化を目指してみてはいかがでしょうか。
もっと知りたい!
続けてお読みください

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。