会社で扱う書類の保管期間は?文書保存に関するルールと効率化のポイントを解説!
- 更新 -

業種・業界を問わず、会社ではさまざまな書類を扱うことになります。
書類の保管は整理の手間やスペースの確保が必要になるため、できることならば過去の書類を処分したいと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、会社で扱う書類のなかには保存期間が定められている文書もあるため、知らずに処分してしまうと法律違反となってしまう可能性もあります。
そこで今回は、会社で扱う書類の保存期間について詳しくご紹介します。
\ワークフローシステムで書類の保存・保管が効率化/
申請書作成・運用が劇的に楽になるワークフローシステム
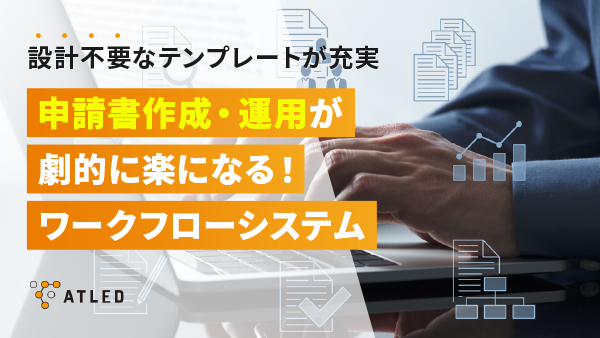
こんな人におすすめ
・新しく帳票を設計するのが大変
・自社のプロセスに合うテンプレートが見つからない
・担当者によって申請書ひな形がバラバラ
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
- 会社で扱う書類には保存期間が定められている
- 保存期間別に文書の種類を紹介
- 保存期間が定められていない文書の扱い
- 保存期間を過ぎた書類の廃棄方法
- 会社文書を保管・管理する方法
- 書類を電子化するメリット
- 書類の電子化にワークフローシステムを活用!
- まとめ
もっと見る
会社で扱う書類には保存期間が定められている
会社で扱う文書の多くは、会社法や法人税法をはじめとした各種法律で保存期間が定めれらています。
法律で定められた保存期間を満たさずに文書を廃棄してしまうと、過料が課せられるほか、企業としての信頼を失いかねません。
一方で、保存期間を過ぎた文書を廃棄せずに残していると、次第に保管スペースが圧迫されてしまい、コストや管理負担の増加を招く恐れがあります。
そのため、適切なタイミングで文書を廃棄するためにも、文書の種類ごとの保存期間を理解したうえで文書管理に取り組む必要があります。
保存期間別に文書の種類を紹介

ここでは、保存期間別に主な会社文書の種類を確認していきましょう。
永久保存する必要がある文書
- 定款
- 株主名簿・新株予約権原簿・端株原簿・社債原簿・株券喪失登録簿
- 登記・訴訟に関する書類
- 官公署への許認可関係の届出書類および重要文書
- 社規・社則に関する通達文書
- 効力が永続する契約にまつわる文書
- 権利や財産に関する書類
- 製品開発・設計に関する重要文書
- 重要な人事に関する書類
- 労働組合との協定書
これらの文書は、法令により永久保存が義務付けられているわけではありませんが、文書の性質上、永久保存が必要だと考えられています。このほか、株主総会や取締役会などの議事録や、稟議書・決裁文書などは法定の保存期間を超えて永久保存している企業が多くあります。
10年間保存する必要がある文書
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 重要会議記録
- 満期もしくは解約となった契約書
- 決算書
- 貸借対照表・損益計算書などの計算書類や附属明細書
- 総勘定元帳・各種補助簿などの会計帳簿や事業に関する重要書類
7年間保存する必要がある文書
- 仕訳帳・現金出納帳など取引に関する帳簿
- 決算に関連して作成された書類
- 領収書・預金通帳・手形控・振込通知書・請求書・契約書・見積書
- 扶養控除等(異動)申告書
- 源泉徴収簿
5年間保存する必要がある文書
- 従業員の身元保証書、契約書
- 産業廃棄物管理票
4年間保存する必要がある文書
- 雇用保険の被保険者に関する書類
3年保存する必要がある文書
- 労働者名簿
- 雇入れ・解雇・退職に関する書類
- 災害補償に関する書類
- 郵便物等の発受信簿
2年保存する必要がある文書
- 健康保険・厚生年金保険に関する書類
保存期間が定められていない文書の扱い
法律で保存期間が定められていない文書は、自社で独自に保存期間を決めて管理する必要があります。
保存期間を決定する際は、以下の観点から期間を検討してみるとよいでしょう。
- 業務を遂行する上での必要性
- トラブル・訴訟時に立証するための必要性
- 会社の歴史上の重要性
保存期間を過ぎた書類の廃棄方法

会社文書のなかには、個人情報や機密情報が記載されているものも少なくありません。
そのため、保存期間を過ぎた会社文書は適切な方法で廃棄する必要があります。
次は、保存期間を過ぎた会社文書の主な廃棄方法について見ていきましょう。
シュレッダーによる廃棄
会社文書の主な廃棄方法のひとつが、シュレッダーによる廃棄です。
文書が少量であれば、業者を使わずオフィス用のシュレッダーで処分することができます。一方、文書を大量に処分する場合、手間と時間が大きくなってしまいます。
また、目の粗さによっては書類が復元されてしまう可能性があるため注意が必要です。
溶解処理による廃棄
業者に依頼して溶解処理を行う方法もあります。
段ボールに書類を詰めたまま回収してもらえるので、大量の文書であっても手間がかからないのがメリットです。
ただし、回収から溶解処理までの間に情報漏洩が発生するリスクがあるため、信頼できる業者を選ぶことが重要になります。
会社書類を保管・管理する方法
次は会社で作成したり受領した書類(文書)を保管・管理する方法について確認していきましょう。
書類を保管・管理する方法は、以下の2パターンに大別することができます。
- 紙媒体で保管・管理
- 電子データとして保管・管理
それぞれの方法について確認していきましょう。
帳簿書類は紙媒体での保存が原則
会社で扱う帳簿書類は、紙媒体での保存が原則とされています。
紙媒体で書類を保管しておく場合、文書の「種類」や「発行日(もしくは受領日)」、「取引先名」などで分類・ファイリングし、キャビネット(棚)に収納します。
第三者による閲覧や持ち出し、改ざんなどの不正を防ぐためにも、鍵付きのキャビネットを利用したり、保管場所への入室を管理したりといったセキュリティ対策が必要です。
また、必要な文書を速やかに参照したり、保存期限を把握するために、書類管理台帳を作成しましょう。
先述した「種類」「発行日(もしくは受領日)」「取引先名」のほか、「保管場所」や「保管期限」、「廃棄方法」についても入力項目を設けて記入しておくことをおすすめします。
一定の要件を満たせば電子保存も可能!
先述したように、原則として帳簿書類は紙媒体で保存することが義務付けられてますが、「e-文書法」(※1)や「電子帳簿保存法」(※2)の要件を満たしている場合には文書の電子保管することができます。
書類を電子データとして保存・管理する方法には後述する多くのメリットがあるほか、電子帳簿保存法の改正によって対応要件が緩和されたこともあり、近年は帳簿書類の電子化に着手する企業が増えてきています。
※1:e-文書法とは、2005年に施行された「文書の電子保存」について定めた2つの法律の総称。「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の2つを指す。(参照:e-文書法の施行について|高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部)
※2:電子帳簿保存法とは、1998年に施行された「国税関係帳簿書類の電子保存」について定めた法律。(参照:電子帳簿保存法関係|国税庁)
書類(文書)を電子化するメリット
次は、書類(会社文書)を電子化する主なメリットについて確認していきましょう。
書類を電子化するメリット
- 業務効率化
- コスト削減
- セキュリティの強化
業務効率化
書類を電子化するメリットとして、業務効率化を挙げることができます。
紙媒体での書類保管・管理では、文書の種類などに応じて仕分けを行いファイリングし、書庫などに格納しなければなりません。
また、保存している文書を取り出す際には、大量の書類のなかから当該の文書を探し出す手間も発生します。
一方、電子データとして書類を保管・管理していれば、上記のような作業をデバイス上で完結することができます。
ファイル名や文書内の情報で検索できるため、保管している書類について社内外から問い合わせがあった際や、監査で帳票の提出を求められた際も、スムーズに対応することができるでしょう。
コスト削減
書類を電子化することは、コスト削減の面でも有効です。
紙媒体での書類を運用している場合、保管場所の確保が必要になるだけでなく、複合機などの印刷設備やファイルやキャビネットなどの備品が必要になります。
また、拠点間や企業間で書類のやり取りがある場合、郵便代や封筒代などの発送コストも必要になるでしょう。
電子データとして書類を運用していれば、保管のためのスペースや設備・備品が不要で、メールやクラウドサービスで共有・伝達することができるため発送コストもかかりません。
さらに、先述した業務効率化によって作業工数が削減されれば、人的コストの削減にもつながるでしょう。
セキュリティの強化
書類の電子化は、セキュリティの強化にも効果が期待できます。
保存が義務付けられている書類は、保存期間中に破損や紛失、情報の改ざんといった不正が発生しないように対策を施す必要があります。
また、会社が扱う書類のなかには機密情報が含まれる文書も多く存在するため、閲覧権限についても適切に管理する必要があります。
書類を電子化していれば、システム上で証跡(操作ログなど)を確認したり、タイムスタンプや電子署名で改ざんを検知・防止したりといった対策が可能になります。
また、ファイルごとにパスワードを設定したり、システム上で個別に閲覧権限を設定することもできるため、紙媒体の書類保管・管理よりも強固なセキュリティを実現できるでしょう。
申請書作成・運用が劇的に楽になるワークフローシステム
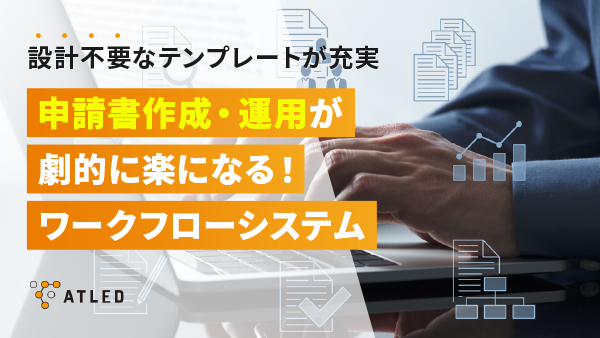
こんな人におすすめ
・新しく帳票を設計するのが大変
・自社のプロセスに合うテンプレートが見つからない
・担当者によって申請書ひな形がバラバラ
書類の電子化にワークフローシステムを活用!
書類(文書)を電子化するメリットをお伝えしましたが、具体的に何から着手すればよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そのような場合、ワークフローシステムの導入から始めてみることをおすすめします。
ワークフローシステムとは、各種申請書や稟議書などの社内文書を電子化するシステムで、近年では多くの企業で導入が進められています。
では、ワークフローシステムが会社の書類の電子化に役立つ理由を見ていきましょう。
/
サクッと学ぼう!
『1分でわかるワークフローシステム』
無料ダウンロードはこちら
\
社内文書の電子化を実現
ワークフローシステムの導入により、社内文書の電子化を促進することができます。
たとえば、会社の重要な意思決定の際に用いられる稟議書や申請書は、破棄することなく保存しておくべき文書です。
しかし、事業を続けていくとそうした稟議書や申請書が累積的に増え続け、保存・管理の負担も大きくなってしまいます。
ワークフローシステムを用いることで、稟議書や申請書をはじめ、社内業務で用いられるさまざまな文書の電子化を実現可能です。
社内での回覧や承認・決裁のための押印などをシステム上で再現できるほか、ワークフローシステムで作成・決裁した書類データはシステム上に保存され、速やかに検索・参照することができます。
また必要に応じてCSVファイルやPDFファイルとしてデータ出力したり、紙媒体に印刷することができる製品も存在します。
これらの特徴により、社内文書の電子化および管理負担の軽減を実現することができるでしょう。
システム連携で電子化の範囲を拡張可能
ワークフローシステムは、他システム・ツールと連携することでさらに利便性を高めることができます。
たとえば、電子取引システムや電子契約システムと連携することで、請求書や契約書といった対外的な文書の電子化を推進可能です。
ワークフローシステムと並行してOCRツールを活用すれば、すでに紙媒体で保管している書類をデータ化することもできるでしょう。
とくに、電子帳簿保存法の要件を満たす「JIIMA認証」製品であれば、帳簿書類の電子保存に必要な要件を満たす運用が可能です。
このほか、グループウェアなどのコミュニケーションツールや、会計システムや人事システムなどの基幹システムと連携すれば、文書管理に限らずさまざまな業務を効率化していくことができるでしょう。
ワークフローシステムで書類の電子化を推進した事例
次に、ワークフローシステムを活用して書類の電子化を推進した事例を見ていきましょう。
10万枚以上の用紙を削減し、書類の保管量も大幅圧縮
日油グループの一角として化学品・化学薬品の研究・製造・販売を担う油化産業株式会社は、紙の申請書に起因する課題解消のためにワークフローシステムを導入しました。
従来の紙ベースの決裁は、意思決定の遅れや機会損失の要因となっていたほか、決裁後の書類は外部倉庫で保管しており、管理工数の面でもコストの面でも負担となっていました。
これらの課題を解消するため、同社はワークフローシステム「X-point」を導入し、その後クラウド型の「X-point Cloud」へとバージョンアップ。
導入から8年間で10万枚以上の用紙を削減し、外部倉庫に保管していた書類の量が大幅に圧縮することに成功しています。
監査業務の効率化にも効果を発揮
稟議書や申請書などの決裁業務について、ワークフローシステム導入以前は複写式の専門用紙に手書きしていたという株式会社明光商会。
決裁に時間がかかるだけではなく、書類の紛失や書類の進捗が把握できない、過去の決裁済みの処理を探すのに手間がかかるなど管理の面でもさまざまな課題を抱えていました。
ワークフローシステムを導入したことにより、書類をデータベースとして取り扱うことができるようになったため、決裁の迅速化に加え正確性や透明性、検索性が向上し、監査業務の効率化や会社全体としての内部統制の強化を実現しました。
まとめ
今回は、会社で扱う文書の保存期間についてご紹介しました。
普段何気なく扱っている文書であっても、知らずに廃棄してしまうと大きなトラブルに発展してしまう恐れがあります。
今回ご紹介した情報も参考に、会社文書の管理方法を見直してみてはいかがでしょうか。
もっと知りたい!
続けてお読みください
書類作成の手間を大幅削減!
申請書作成・運用が劇的に楽になるワークフローシステム
エイトレッドのワークフローシステムは、1,000以上の申請書テンプレートと、ノーコードで簡単に申請書を作れる設計ツールで、申請書作成・運用の課題をまとめて解決します!
こんな人におすすめ
・新しく帳票を設計するのが大変
・自社のプロセスに合うテンプレートが見つからない
・担当者によって申請書ひな形がバラバラ
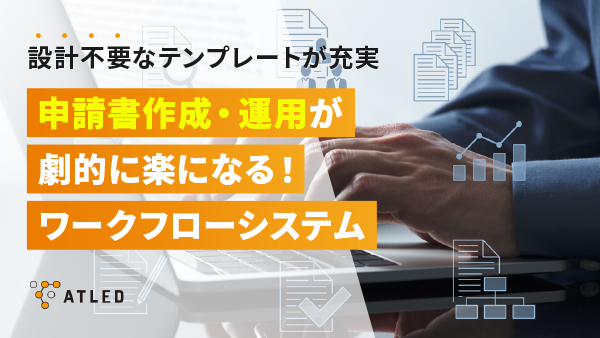

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。








