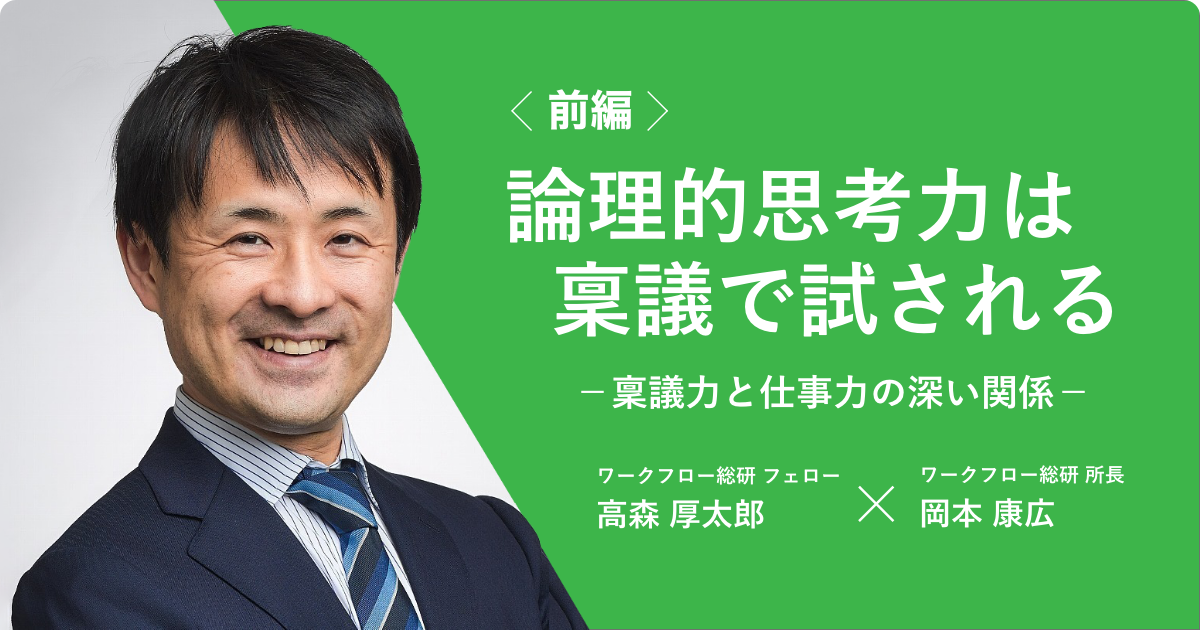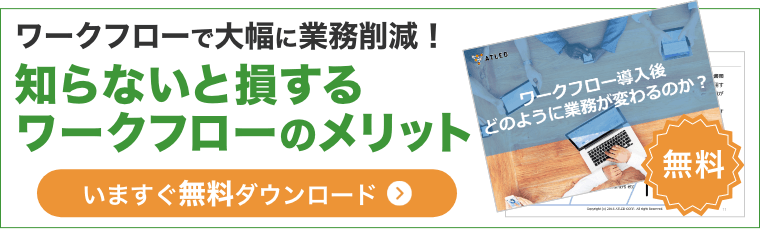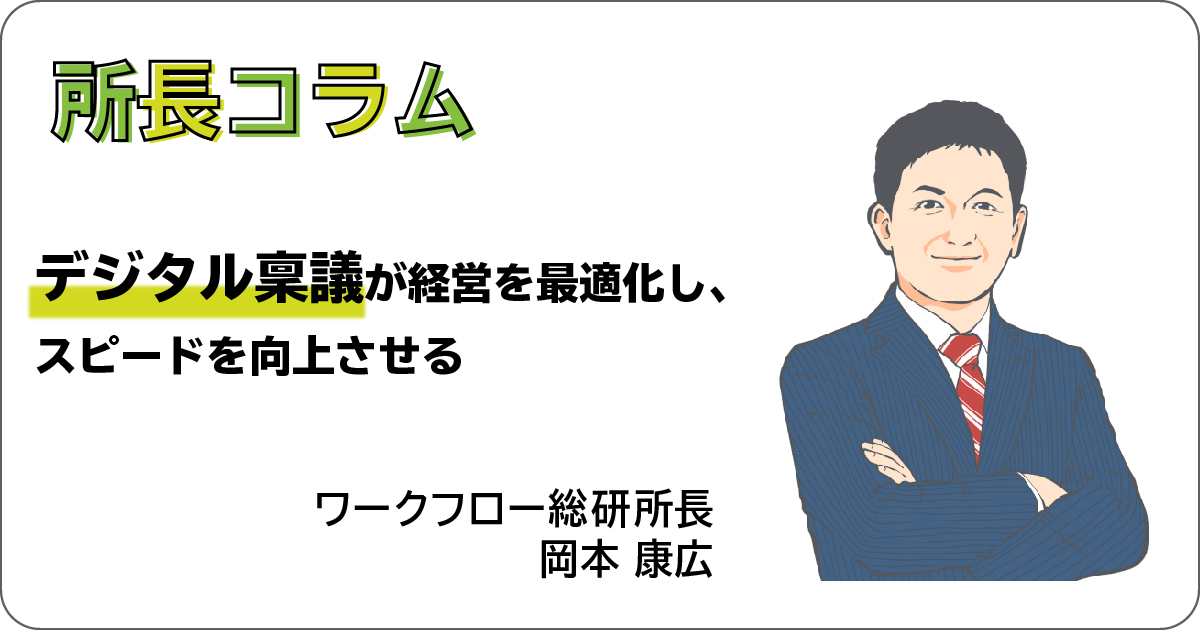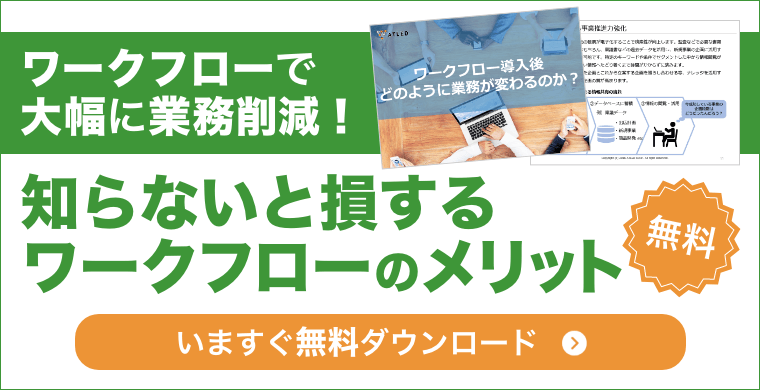過去の成功と国民性に学び、現代日本に必要な稟議の姿を考える
- 更新 -

前回は思考力と稟議というテーマでお話ししました。
ある意味、日本特有ともいえる稟議はどのような歩みをたどり、どんな役割を果たしてきたのか。そんな歴史的な観点から、今回は稟議を掘り下げていこうと思います。
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
稟議制は日本文化にフィットしていた
稟議は官僚制と密接な関係にあります。たとえば、政治学者の故・辻清明氏による「新版・日本官僚制の研究」(東京大学出版会、1969)では、明治以降の近代国家で用いられてきた稟議制に触れられています。
本研究論文では、稟議制に対し批判的な文脈で述べられています。実際、意思決定に時間がかかる、責任の所在が曖昧、経営層や上長への忖度文化など、よく批判されます。
しかし、果たして本当に稟議にはこれら負の側面しかないのか。もしそうだとすれば、非合理的な制度として、時代の流れの中で廃れているはずです。
しかし、未だに稟議制は官僚機構や企業の意思決定システムとしてメジャーな存在です。
とすれば、稟議制の本質的な意味を捉えることが大切です。
例えば、文書で残すためコンセンサスをとりやすい、一回決定すればその後の実行が早い、意思決定に現場スタッフが関与できるという正の側面があげられます。
現場を起点としたボトムアップのプロセスなので、組織全体を巻き込みやすい点もあげられます。
そんな稟議制、実は日本特有のものです。諸外国ではほとんど見られません。なぜ稟議制が日本で発明され、現代日本で根強く使われているのでしょうか。
そこには日本独自の地理や文化、国民性も影響していると考えられます。
島国であるため、外敵に侵略される恐れが他国より少なかった日本は、農耕民族としての文化を育みました。
国のトップ(天皇)と統治実務(政治・行政)は切り離されており、統治実務サイドでも歴史上目立った独裁者がいない合議制の国です。
強固なトップダウンの統治実務者は、後醍醐天皇、織田信長くらいで、統治機関も短ければ、全国をあまねく統治したというわけでもありません。
むしろ、徳川家康のようなリーダーが天下太平の世を全国に長く築いていることから見ても、ボトムアップ型の国と言えるでしょう。
また、庶民文化との関係性も見逃せません。江戸時代幕末期に日本の識字率が世界一だったことは有名ですが、つまりは庶民でも文書によるコミュニケーションができたのです。
これが、文書で意思決定をして記録に残す稟議制とフィットしていたとも考えられます。
高度経済成長は稟議制が支えた
日本企業の経営者はサラリーマン社長で、リーダーとして頼りないと言われることをよく耳にします。
しかし、それでも世界的に日本企業のブランドは根強く、経済大国でもあります。これを支えているのは現場力でしょう。
現場が優秀で勤勉で、しっかりモノを作り、こつこつ売ってきた。この現場の強さに、ボトムアップの稟議制が大きく貢献できていると言えるのではないでしょうか。企業の意思決定に現場が主体として起案できて、社内を巻き込める。
決裁おりたら、コンセンサスを元に、全社一丸で実現に取り組めるということですから。戦後復興や高度経済成長を支えた根幹に、現場力と併せて稟議制もあったのだと私は考えています。
仮に、もし日本に稟議制がなかったらどうなるか。思考実験をしてみます。日本で稟議制がなかったら、史実がことわざにもなっている「小田原評定」のようなことが起こると考えられます。
これは、小田原城主だった北条氏が豊臣秀吉に攻め込まれた際、トップが優柔不断かつ家臣のコンセンサスがうまくとれないので議論がまとまらず、その間に大軍に包囲され敗北したという故事です。
つまりボトムアップ型は仕組みや決め事がないと合意形成が難しく、何も実行されない、何も変わらない側面をもっているとも言えます。
経営と現場の創発による意思決定「ネオ稟議」が今後の日本に必要だ
最後に、現代にフィットした稟議のあり方についても考えてみましょう。前段で、高度経済成長期と稟議制について述べましたが、現代とは状況が大きく異なります。
現代日本は成熟社会であり、低成長社会です。社会環境も大きく変わり多様化・複雑化しています。
企業も日々改善を行っていますが、それぞれの現場が関わる範囲は狭いので、どうしても従来の延長線上の施策になります。
モノづくりが主流だった頃、この延長線上の改善の積み重ねで大きく成長することができました。しかし、環境が昔と変わった現在では、これでは大きな成長は望めません。
では、トップダウンがいいのかというと、日本は欧米ほど革新的施策を打ち出せるトップのパイプライン(人材層)があまり見受けられません。
リーダー文化の違いによるアレルギーもあり、トップダウン型はうまくいかないでしょう。
「失われた平成の30年」と揶揄される、なんともいえない停滞感は、国家や企業の意思決定システムの目詰まり(ボトムアップが結果出せず、かといってトップダウンもワークしない)、だったのではないでしょうか。
では、これからの、令和の意思決定はどうすればよいか。日本は欧米と比べた場合、良くも悪くも経営と現場では、それぞれの能力や報酬、身分にそこまで差がありません。
しかし、持っている情報は、立場の違いから違う。とすると、経営陣と現場が意思決定を共に考え創発していけばいいのではないでしょうか。
話は嚙合わせることができる、話せばわかるのですから。具体的には、現場がタッチできない経営側の情報をうまくすり合わせることです。このすり合わせを、「稟議」の活用で行うのです。
本来の稟議は、現場の起案がそのままトップに持ち上がって決裁されるわけではありません。途中でアドバイスが入ったり、突き返されたりして起案の質が高まっていくことが理想です。
間のプロセスがあるからこそ、現場も多くの経営側の視点が入ってきますし、経営としてみれば生々しい現場で行っていることを事業にダイレクトに反映ができます。
稟議を積極的に活用することで、こういった経営と現場の創発による意思決定が、これからの日本の企業に必要だと思います。
本来的にはこのようなプロセスが稟議そのものですが、制度が形骸化し、これまでなかなかここまで活用されていませんでした。
今後はデジタル化されて利便性が高まるという側面もあります。どのような企業でも、工夫次第で稟議をアップデートすることが可能です。この新しい稟議は「ネオ稟議」ともいえるでしょう。
もっと知りたい!
続けてお読みください
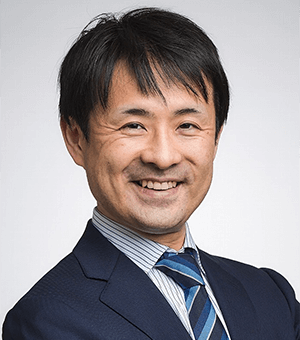
フェロー
高森厚太郎
一般社団法人日本パートナーCFO協会 代表理事
東京大学法学部卒業。筑波大学大学院、デジタルハリウッド大学院修了。日本長期信用銀行(法人融資)、グロービス(eラーニング)、GAGA/USEN(邦画製作、動画配信、音楽出版)、Ed-Techベンチャー取締役(コンテンツ、管理)を歴任。現在は数字とロジックで経営と現場をナビゲートするプレセアコンサルティングの代表取締役パートナーCFOとして中小・ベンチャー企業などへの経営コンサルティングのかたわら、デジタルハリウッド大学院客員教授、グロービス・マネジメント・スクール講師、パートナーCFO養成塾頭等も務める。2020年9月にはワークフロー総研のフェローに就任。著書に「中小・ベンチャー企業CFOの教科書」(中央経済社)がある。