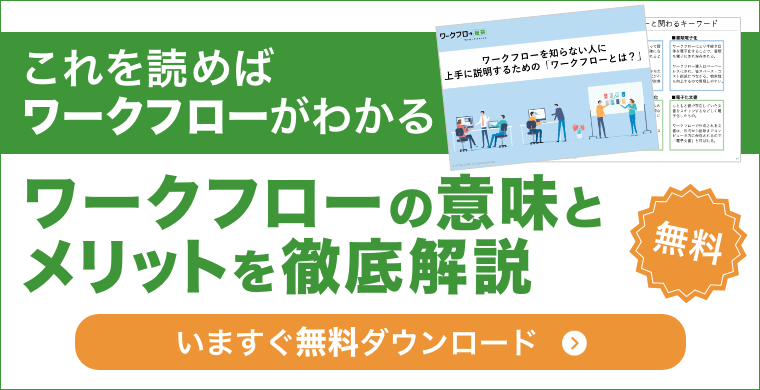個人・個性が仕事の主人公に。これからの時代に必要な「コラボレーション型」組織とは
- 更新 -

今回は私が考える、これからの時代に必要な組織の在り方、組織の考え方についてお話しします。それは「コラボレーション型」です。
これはトップダウンやボトムアップ、またティール型といった組織とは少々違ったものであり、その概念やワークスタイルなどをお伝えしたいと思います。
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
\入力時間30秒/
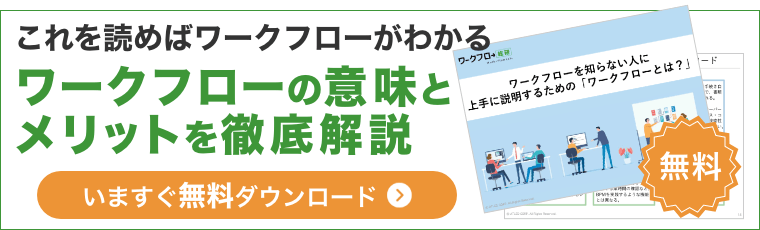
ワークフローシステムから生まれる自由なコラボレーション
従来の日本の働き方はピラミッド型であり、上意下達のトップダウンが一般的でした。しかし現代のようにITによる情報化や働き方改革、ニューノーマル化が進み、スピーディかつ正確な意思決定や激的な変化が求められる社会では、もはや従来型の組織では追い付いていけません。
旧式の働き方、そしてスピーディかつ正確な意思決定を妨げる大きな要因が、紙と押印ベースの仕事のやり方です。このことは、昨今のコロナ禍でテレワークが浸透する中「ハンコ問題」として弊害が大きく取り上げられていたことからも明らかです。
テレワーク、また場所や時間にとらわれないコミュニケーションの形はより浸透していくでしょう。そしてコミュニケーションや意思決定は、仕事のうえでも特に大切な要素です。こういった仕事の根幹を、書類の電子化によってイノベーティブにしていくものがワークフローです。
また、アナログなあり方は、「情報やナレッジへのアクセス」が極めて非効率になります。知見が溜まった稟議を全体で共有できれば自ずとアイデアは広がるでしょう。役職や部署に関係なくナレッジにアクセスできるというのは、コラボレーションの土台になります。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が叫ばれていますが、コラボレーションをする上でもDXが必須です。
そして、時間と距離の壁を取り払い、メンバーとチームをつなげていく。そのうえでコミュニケーションを活発化させ、今までになかった発想やコラボレーションを生みだせるシステムがワークフローなのです。
縦横や社内外の枠組みを超えるコラボレーション型組織
「メンバーとチームをつなげる」「今までになかった発想やコラボレーション」と述べましたが、これは社内はもちろん、社外の組織や人との自由なコミュニケーションも含みます。
社内外の人とすばやくつながり、協働して価値創出や課題解決していくワークスタイルが「コラボレーション型」。この、社内外という視点が「コラボレーション型」の新しさであり特徴だといえるでしょう。
縦軸はもちろん横軸との連携はもはや当たり前で、役職や所属企業の枠組みを超えてプロジェクトごとに提携、協業してチームを組織。それぞれの得意分野を活かして仕事を補完するスタイルです。
これからは、組織の中に絶対的な答えがない時代だといえるでしょう。そこでは情報共有の在り方も、クローズされた逐次共有の形ではなくオープン型になることが重要であり、求められていくはずです。
情報や働く環境を広くオープンにし、ワークフローのあるべき姿である“集合知”を駆使。ある人のアイデアをまったく別の会議で活用したり、ある人は社外の組織や外部の人と連携して、新たなビジネスを生み出していったりする。
ここで言う「ある人」は、役職や部署にとらわれません。バックオフィスの方はもちろんのこと、その道に長けていれば新入社員でもいいわけです。垣根を超えて得意分野や個性などを活用し、今までになかった発想を生み出していくインタラクティブなワークスタイルが「コラボレーション型」なのですから。
「強み」や「弱み」といった「個性」によるコラボレーションを実現するには
コラボレーション型組織の根底には、マネジメントの在り方も変わっていくべきだという考えがあります。従来は、上司の管理・監視下でなければ部下は動かないという性悪説の考え方。しかし、あるべき姿は逆であり、性善説です。
性悪説から性善説のマネジメントへ――。この在り方は、テレワークと同様に昨今飛び交うようになったジョブ型雇用の概念とも似ています。
ジョブ型雇用においては年齢や社歴などではなく真のスキルが重視され、評価は明確な成果で判断されますから、信頼で成り立つ性善説の考え方です。
組織の制度や風土も横並び主義ではなく、違いを認めて活かしていくため、個人のパーソナリティが重視される関係性となるのです。つまり、コラボレーション型とは個人の特性を生かして組織の潜在能力を引き出すワークスタイルで、それぞれの個性を配置したりつなぎ合わせたりするのが企業の役割となるのです。
一般的に、人には強みと弱みがあるといわれますが、私はそうは思いません。見え方によって弱みは強みになる。強みと弱みは紙一重であり、どちらも個性なのです。どういうことか。強みと弱みは、前提や比較対象、状況などによって都度変わるものだと考えています。
相手や仕事によって、強みは弱みにも変われば、逆に弱みだと思い込んでいたことが強みになることもあります。例えば、とても慎重な性格の人がいたとして、グイグイ攻めていくベンチャー企業において、慎重さが強い人はスピードについていけず、性格が弱みとして出てしまうかもしれません。
一方で、命を守るような鉄道などのインフラ系の企業であれば、その慎重さは極めて重要であり、強みになります。
現在では、AIが登場するなどシステムや環境は進化していますが、それらをコントロールして意思決定をするのは人。また、コミュニケーションとは人と人とのつながりであり、人には誰にでも個性があります。
コラボレーション型の組織においてはプロジェクトごとにメンバーが変わるでしょうし、人数の大小も多種多様。その都度チームが組織されることもあり、働き方やコミュニケーション方法は複雑かもしれません。
しかし、その複雑な働き方に合致するのが、場所や時間を問わずに集合知によってすべての仕事を網羅するワークフローシステムなのです。
今回、様々な観点から「コラボレーション型」の組織や働き方について論考させていただきました。新しいワークスタイルかもしれませんがこれからもワークフロー総研はじめ、さまざまな場所で発信していきたいと思います。
もっと知りたい!
続けてお読みください

ワークフローシステムを開発・提供する株式会社エイトレッドの代表取締役社長も務める。ワークフローを出発点とした働き方の見直しが意思決定の迅速化、組織の生産性向上へ貢献するという思いから、ワークフローの普及を目指し2020年4月、ワークフロー総研を設立して現職。エイトレッド代表としての知見も交えながら、コラムの執筆や社外とのコラボレーションに積極的に取り組んでいる。