物流DXとは?業界特有の課題や2024年問題への対策・取り組み事例を徹底解説!
- 更新 -

昨今、重要性が高まった戦略の1つとしてDX推進が挙げられます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「データとデジタル技術を活用してビジネスモデルを変革し、競争上の優位性を確立すること」を指しますが、いま最もDX推進が求められている業界の1つが物流です。
そこで今回は、なぜいま物流業界でDXが必要とされているのかや物流DXの取り組み事例、物流DXを加速させる方法などについて解説します。
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
業界特有の課題を解決!
物流DXを加速させるならワークフローシステム
本書では、物流DXの基礎知識やワークフローシステムが物流DXに役立つ理由についてわかりやすくまとめています。
こんな方におすすめ
・物流DX何からはじめていいのか分からない
・物流の2024年問題について知りたい
・物流DXに役立つツールを知りたい

物流業界が抱える課題

まずは物流業界が現在抱えている課題について整理しましょう。
EC市場の成長に伴う小口配送の急増
大手通販会社の台頭やコロナ禍の外出自粛などの影響で、EC市場が急成長したことで個人宅への小口配送が急増しました。
経済産業省が公表している「電子商取引に関する市場調査の結果」によれば、物販系分野のBtoC-EC市場規模は、2019年から2021年の3年間で以下のように推移しています。
物販系分野のBtoC-ECの市場規模
- 2019年:10兆515億円
- 2020年:12兆2,333億円
- 2021年:13兆2,865億円
このようにBtoC-EC市場規模は年々成長を続けており、小口多頻度納品が急激に増加しているのです。
小口配送の急増はトラック積載率の低下や、倉庫内での在庫管理の複雑化を招き、結果として業務全体の効率悪化を招いてしまいます。
人手不足の顕在化
以前からドライバーの高齢化問題が指摘されていた物流業界でしたが、先述したEC利用の急拡大が人手不足にさらに拍車をかけることになりました。
たとえば、国道交通省が公開している資料「最近の物流政策について」によれば、令和2年6月時点の貨物自動車運転手(パート含む)の有効求人倍率は1.92倍であり、全職業(パート含む)の0.97倍と比べても労働力不足の度合いが高いことがわかります。
また、道路貨物運送業の従事者の年齢構成は、全産業平均より若年層の割合が低く、高齢層の割合が高いことが指摘されています。
過酷な労働環境
「小口配送の急増」や「人手不足の顕在化」の影響により、物流業界では以前にも増して長時間労働が常態化しています。
先述した資料「最近の物流政策について」では、トラック運送業は全職業平均よりも労働時間が約2割長く、年間賃金は約1~2割ほど低いというデータが示されています。
また、燃料コストの高騰や各社の価格競争などが原因で賃金を上昇させることができず、物流業界の従業員は過酷な環境での労働を強いられています。
2024年問題の対応
物流業界の課題として、忘れてはいけないのが「2024年問題」です。
働き方改革関連法の施行により、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から「時間外労働時間の上限規制」が適用されました。
物流業においては「時間外労働の上限規制」に5年間の猶予期間が設けられていますが、その猶予期間も2024年3月に終了します。
そして、猶予期間が終了する2024年4月1日からは、自動車運転業務における時間外労働時間は年960時間までという上限規制が適用されます。
2024年4月から適用される「時間外労働の上限規制」に対応するためにも、業務効率化や人材獲得・定着の促進、そして労働環境の改善などの取り組みが必要になるでしょう。
課題解決の鍵はDX推進

それでは、物流業界が抱える課題を解決するにはどうすればいいのか。その答えがDX推進です。
物流DXとは
それでは、物流業界におけるDXについて詳しくみてみましょう。
物流DXの定義
物流DXとは、国土交通省が公開している資料『最近の物流政策について』(2021年1月22日)の中で、「機械化・デジタル化を通じて物流のこれまでのあり方を変革すること」と定義されています。
物流DXを実現する手段
また同資料の中では物流DXを推進する手段として「物流分野の機械化」と「物流のデジタル化」を挙げており、これらを相互に連携させることで情報やコストが可視化され、業務プロセスが標準化されるとしています。
物流分野の機械化(例)
- ドローン配送
- 自動運航船
- 倉庫内作業の自動化
- 自動配送ロボ
物流のデジタル化(例)
- 手続きの電子化
- 配車管理のデジタル化
- トラック予約システムの導入
- AIを活用したオペレーションの効率化
物流DXの目的
そして、DXを推進するうえで特に気を付けたいのがデジタル化との混同です。
システムや機械を導入すること自体が目的となってしまうケースがよくありますが、機械化やデジタル化はあくまでDX実現の手段であり、DXの目的はあくまでもビジネスモデルの変革です。
物流DXにおいてもそれは同様で、同資料の中でも「既存オペレーションの改善・働き方改革を実現」「物流システムの規格化などを通じ物流産業のビジネスモデルそのものを革新」の2つが目的として掲げられています。
物流DXの取り組み事例
次は主な取り組み事例についてみてみましょう。
日本航空株式会社×KDDI株式会社
航空運輸事業を中心に事業を展開する日本航空株式会社と大手電気通信事業者のKDDI株式会社は、両者が持つノウハウやテクノロジーを活用し、全国規模でドローン運航を管理する体制を構築することを発表しました。
現在は、2023年のサービス商用化を目標に、離島での実証などの取り組みが行われています。
参考:KDDIとJAL、ドローンの社会インフラ化に向け、1対多運航の実現を目指す取り組みを開始 | 2022年 | KDDI株式会社
ヤマト運輸運輸株式会社
宅配便事業を行うヤマト運輸株式会社では、「YAMATO NEXT 100」の基本戦略の中で、「データドリブン経営への転換」を掲げ、積極的にDX推進を行っています。
具体的な取り組みとしては、AIの活用が挙げられ、AIで荷物量や全国に点在する各営業所の業務量を算出することにより、経営資源の配置とコストの最適化を図っています。
物流DX最初の1歩はワークフローシステム
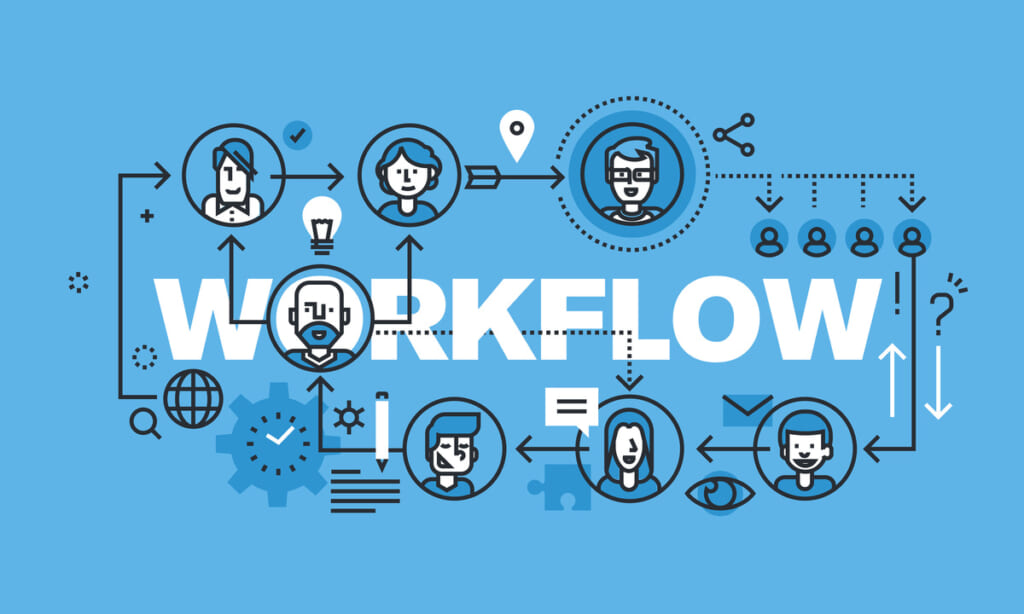
さて、物流DXの概要が分かったものの、「なにからはじめたらいいのかわからない」、「機械の導入や一部の業務のデジタル化をしたものの効果が感じられない」という人もいるのではないでしょうか。
そんな人たちに物流DXの最初の1歩としておすすめしたいのがワークフローシステムです。
ワークフローシステムとは、稟議をはじめとした業務手続きを電子化するシステムで、導入することでさまざまな効果を得ることができます。
/
サクッと学ぼう!
『1分でわかるワークフローシステム』
無料ダウンロードはこちら
\
ワークフローシステムが物流DXに役立つ理由
ワークフローシステムが物流DXの推進に役立つ理由は以下の3つです。
ワークフローシステムが物流DXに役立つ理由
- 配送手続きのデジタル化
- 従業員管理のデジタル化
- DX基盤の構築
1.配送手続きのデジタル化
ペーパーレスの気運が高まる昨今ですが、物流業界ではいまだ多くのやり取りが紙の書類で行われています。
とくに、倉庫業務では伝票や送り状をはじめ多くの紙が取り扱われているため、業務効率の低下の原因となっています。
ワークフローシステムを導入し、紙ベースで行われていた配送手続きをデジタル化することで、管理の手間やコストの大幅な削減が見込めます。
2.従業員管理のデジタル化
物流DXを推し進める上で、適切な従業員管理は必要不可欠だといえます。
たとえば、長時間労働を防止するためには、従業員の勤怠状況や日々の業務内容を正確に把握し、必要に応じて業務効率化を図らなくてはなりません。
また、低賃金を解消するためにも、従業員を公平に評価する必要があるでしょう。
ワークフローシステムを導入すれば、勤怠状況や日報による業務報告をデータとして活用・管理することが可能です。
たとえば、時間外労働が多い従業員に対してアラートを出したり、データを集計することで、業務におけるボトルネックを洗い出すことができます。
3.DX基盤の構築
申請や承認といった業務手続きは、サプライチェーンのあらゆる業務に紐づくため、ワークフローシステムを導入することで、「物流のデジタル化」の基盤を構築することができます。
また、ワークフローシステムは他の業務システムやツールと連携することでさらに利便性を高めることが可能です。
ワークフローシステムと各種システム・ツールの連携により、業務手続きだけに留まらず、さまざまな業務のデジタル化を推進していくことができるでしょう。
\5分で学べるホワイトペーパー/ 物流DXを加速させる!最初の1歩はワークフローシステム
ワークフローシステムを活用し物流DXに成功した事例
では、実際にワークフローシステムを活用して物流DXの推進に成功した企業事例を見ていきましょう。
130拠点約2000台の車両運用を効率化
従業員規模1000人以上の企業Aは、従来、車両管理に関連する申請業務を紙で行っていたため、担当者に申請書が届くまでに時間がかかる、データ入力や書類管理に追われ情報のとりまとめに時間がかかるなどの課題を抱えていました。
そこで、ワークフローシステムと車両管理のデータベースを連携させることで車両管理システムを構築し、承認期間の大幅な短縮、リアルタイムに近い車両データの把握に成功しました。
物流DXにおけるワークフローシステム導入のポイント
物流業界のDXが他業界と比べて遅れている背景に、これまでデジタル技術を活用しなくても業務がまわっていたため、触れる機会がほとんどなかったということが挙げられます。
そのため、物流業界は全体的にITに関連する知識が不足している可能性があり、ワークフローシステムを導入する場合は、これらの課題を解消する機能が備わっているものを選択した方がいいと言えます。
ポイント1:使い慣れたUI
ワークフローシステムの中には、紙やexcelのフォーマットをそのまま表現できるものがあります。
これまでとのギャップを最小限に抑えることで、現場からの反発を防ぎ浸透しやすくなるでしょう。
ポイント2:ノーコード
デジタルに不慣れな物流業界でいきなり高度なプログラミングが要求されるシステムを導入してしまうと、使いこなすことができず効果を実感できなかったり、逆に業務効率の低下を招いてしまう可能性があります。
また、ワークフローの開発を外部委託するという方法も考えられますが、これだと膨大な外注費がかかってしまいます。
その一方で、専門的な知識を必要としないノーコードのシステムであれば、内製することも可能なので、外注にかけるコストを削減することができます。
ポイント3:スマホ対応
ほとんどの時間をオフィスや営業所以外で過ごすドライバーにとって、業務手続きのためにPC環境の整った場所に立ち寄ることは大きな負担になります。
その点、スマートフォン対応の機能があれば、勤怠や日報の申請をどこからでも行うことができるので、負担を軽減することができるでしょう。
\物流DXにおすすめのワークフローシステム/
ギャップをなくし現場にスムーズに浸透させるなら『Xpoint Cloud』
【デジタルに不慣れでも安心!】
★ノーコードなのでITの専門知識は一切不要
★紙のような入力フォームで誰でも直感的に使える
★初期費用0、1ユーザー月額500円だから気軽にはじめられる
★シリーズ累計4000社以上の安心の導入実績
『Xpoint Cloud』の資料を無料でダウンロード⇒こちらから
まとめ
今回の記事では、昨今物流業界が抱えている課題を解決する鍵として物流DXを、また物流DXを加速させるデジタルツールとしてワークフローシステムをご紹介いたしました。
ワークフローシステムなどのデジタルのツールを上手く活用し、物流DXを推し進めることで、コロナ禍以降の市場の拡大をピンチではなくチャンスに変えることができるのではないでしょうか。
業界特有の課題を解決!
物流DXを加速させるならワークフローシステム
本書では、物流DXの基礎知識やワークフローシステムが物流DXに役立つ理由についてわかりやすくまとめています。
こんな方におすすめ
・物流DX何からはじめていいのか分からない
・物流の2024年問題について知りたい
・物流DXに役立つツールを知りたい


「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。






