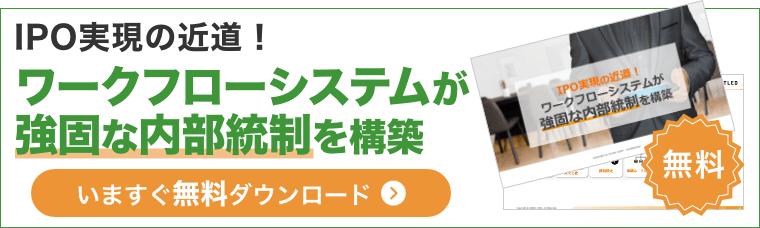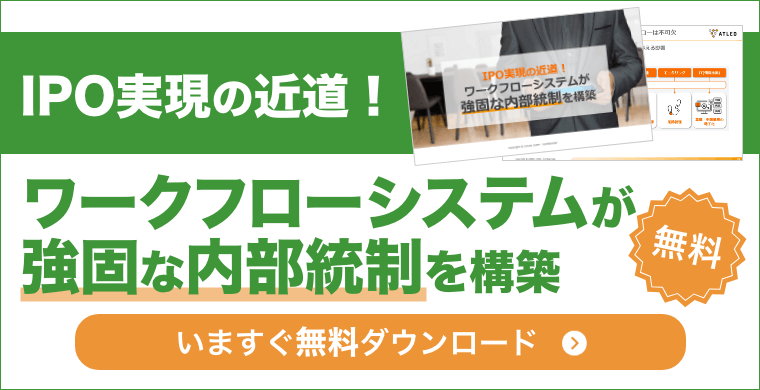IPOとは?メリット・デメリットや上場準備に役立つITシステムを解説!
- 更新 -

ビジネスシーンでは、「IPO」という単語を耳にする機会が少なくありません。
しかし、
「IPOはよく聞くけれど、意味はわからない…...」
「IPOにはどんなメリット・デメリットがあるの?」
「IPOまでの流れや期間、対応項目は?」
「IPO準備のポイントを知りたい!」
といった疑問やお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事ではIPOに焦点を当て、その意味やメリット・デメリット、IPO準備(上場準備)のポイントについてわかりやすく解説します。
IPO準備に役立つITシステムや成功事例についてもご紹介しているので、IPOについて知りたい方や、将来的なIPOを見据えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
IPOとは?

IPO(Initial Public Offering)とは、「新規上場株式」や「新規公開株」などと訳され、株式会社が証券取引所(市場)に上場し、投資家が自社の株式を購入できる状態にすることを指します。
株式会社は上場・非上場に関わらず株式を発行していますが、非上場企業においては株主が同族や特定の少数者に限定されているのが一般的です。
一方、IPOを果たした上場企業においては、株式が証券取引市場で公開・流通させることで、不特定多数の投資者に保有・取引されるようになります。また、上場企業は、金融商品取引法の規制に基づき、株式の投資判断のための情報開示を行います。
なお、IPOをするには証券取引所が定める上場基準を満たした上で、厳しい審査を通過する必要があります。
IPOのメリット・デメリットとは?
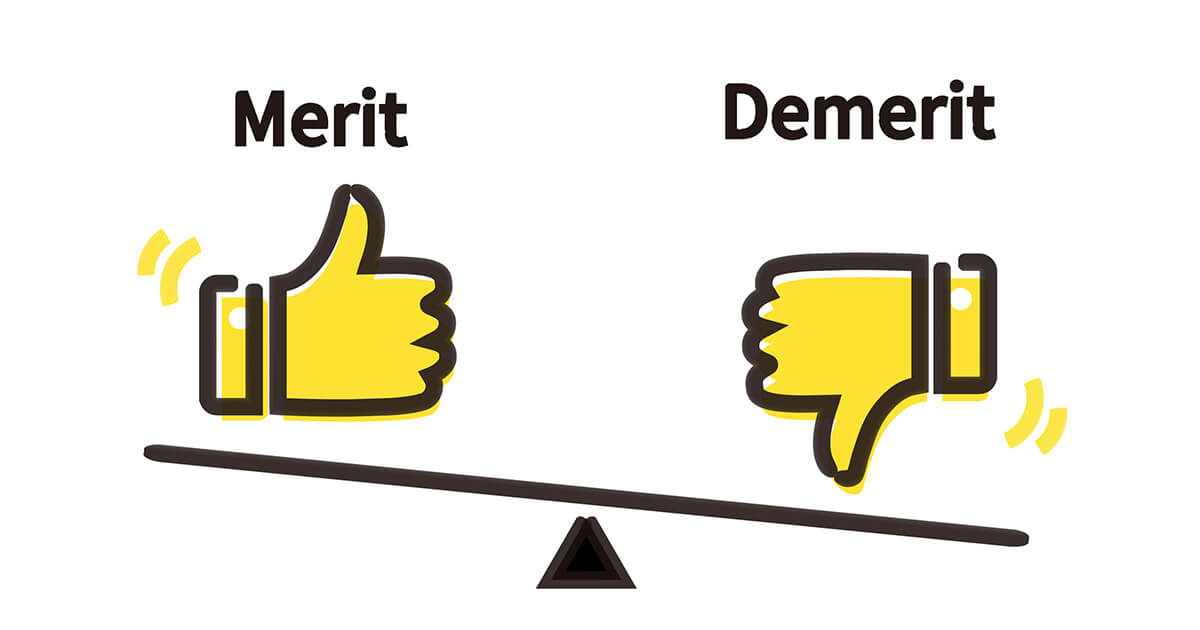
IPOを実現するには厳しい審査を通過する必要があるとお伝えしましたが、それでも多くの企業がIPOを目指しています。
企業がIPOを目指す理由には、IPOを実現した後に得られる大きなメリットの存在があります。
また一方で、IPOにはデメリットも存在します。
次に、IPOのメリット・デメリットについて確認していきましょう。
IPOのメリット
IPOの主なメリットとして、以下の3点を挙げることができます。
IPOのメリット
- 資金調達力の強化
- 信頼性の向上
- 優秀な人材の確保
各メリットについて詳しく確認していきましょう。
資金調達力の強化
IPOのメリットとして、資金調達力の強化を挙げることができます。
未上場企業の場合、資金調達の方法は金融機関からの借り入れなどが主になります。
一方、上場企業の場合、証券取引所を介して不特定多数の投資家から広く資金を調達することが可能です。
また、上場企業という信頼性から金融機関からの借入が容易になるほか、新たに株式を発行して資金調達を行う公募増資も可能になるため、資金調達の手段も多様になります。
信頼性の向上
信頼性の向上もまた、IPOのメリットだと言えます。
IPOを行い証券取引所で上場を実現するには、財務状況や内部統制などに関する厳しい審査を通過する必要があります。
つまり、上場企業は一定水準の財務状況・内部統制を満たしていることが担保された状態であり、金融機関や取引先から信頼を獲得しやすいと言えるでしょう。
優秀な人材の確保
IPOを実現することで、人材確保にも効果が期待できます。
未上場企業と比較して、上場企業の方が求職者の目に触れる機会は多いでしょう。
加えて、「上場企業」という信頼性は求職者にとって魅力的な要素であり、求職者の増加も期待できるでしょう。
IPOのデメリット
多くのメリットが期待できるIPOですが、以下のようなデメリットについても理解しておく必要があります。
IPOのデメリット
- 上場には多額のコストが必要
- IR活動の負担
- 買収リスク
では、IPOのデメリットを確認していきましょう。
上場には多額のコストが必要
IPOを行い上場するには、多額のコストが発生します。
たとえば、上場準備の段階では、監査法人や証券会社、コンサルティング会社などに支払うコストが発生します。
また、上場には上場審査料が必要で、上場後も年間上場料を支払う必要があります。
これらはIPOに必要なコストの一部であることから、多額のコストが必要であることがわかるでしょう。
IR活動の負担
IPOを行い上場すると、株主に向けたIR活動を行う必要が出てきます。
IR活動とは、株主向けに経営状態や財務状況、経営戦略などの広報を行う活動のこと。ホームページ上での情報開示や決算説明会の開催、各種資料作成やプレスリリースなど、行うべきことは多岐にわたります。
このようなIR活動の負担が発生するという点も、IPOのデメリットだと言えるでしょう。
買収リスク
IPOを行い上場することで、不特定多数の投資家が自社の株式を購入できるようになります。
そのため、株式の買占めにより経営権が奪われる可能性も否定できません。とは言え、買収によってさらなる事業成長が見込めるケースもあるため、必ずしもデメリットばかりではないという点も覚えておきましょう。
「証券取引所」とは?

IPOを語る上で欠かせないキーワードに、「証券取引所」があります。
証券取引所とは、上場企業の株式の売買が行われる市場のことを指します。
日本国内には、以下4つの証券取引所が存在します。
- 東京証券取引所(東証)
- 名古屋証券取引所(名証)
- 福岡証券取引所(福証)
- 札幌証券取引所(札証)
なかでも代表的な市場が東京証券取引所(東証)で、上場企業の大多数は東京証券取引所に上場しており、株式売買も東京証券取引所で行われるケースが一般的です。
東京証券取引所の市場再編
国内における株式売買の主戦場とも言える東京証券取引所ですが、2022年4月4日に市場再編が行われました。
従来、東京証券取引所の市場区分は以下の4つでした。
従来(~2022年4月3日)の市場区分
- 市場第一部(東証一部)
- 市場第二部(東証二部)
- マザーズ
- JASDAQ(スタンダード/グロース)
2022年4月4日以降、これらの市場は以下の3区分に再編されました。
再編後(2022年4月4日~)の市場区分
- プライム市場
- スタンダード市場
- グロース市場
プライム市場は、安定かつ優良な収益・財政基盤が構築されており、高いガバナンス水準を備える企業向けの市場です。
スタンダード市場は、安定した収益・財政基盤を持ち、基本的なガバナンス水準を備えている企業向け。
グロース市場は、高い成長可能性を示す事業計画があり、なおかつ成長段階を踏まえたガバナンス水準を有するものの、事業実績の面で上記の企業には至らない企業向けとされています。
また、上述した一般市場のほか、東京証券取引所にはTOKYO PRO Market(TPM)という市場もあります。
TPMはプロ投資家向けの市場であり、「J-Adviser」という資格をもつ企業が主幹事業務を行う点が特徴です。
IPOを目指すなら市場選びも重要
上記のように、株式市場にはそれぞれ特徴があり、上場審査基準も異なります。
そのため、IPOを実現するためには、どの市場での上場を目指すのかも重要になります。
たとえば、短期でのIPO実現を目指すのであれば、早ければ約2年での上場が見込めるTPMが選択肢に入ってくるでしょう。
経営戦略や財務状況、ガバナンス体制など、自社の状況やビジョンを考慮して株式市場を選択しましょう。
IPO(上場)は少なくとも3年程度の準備期間が必要
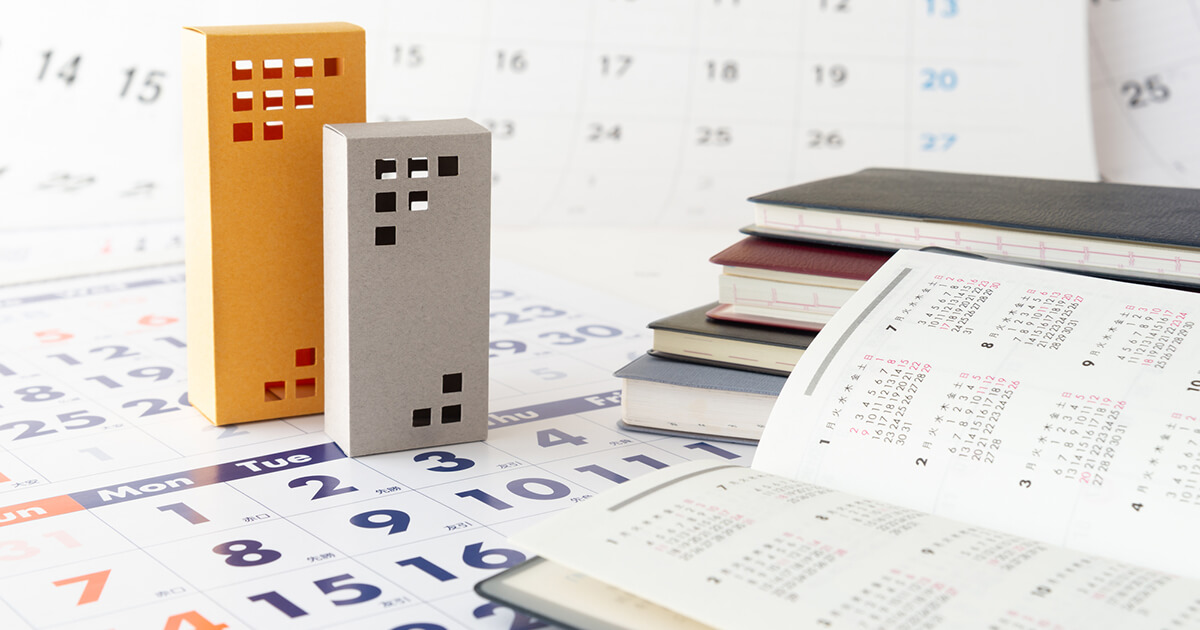
IPO(株式上場)までには少なくとも3年程度の準備期間が必要だとされています。
上場審査では、申請期の2期前までの監査証明の提出が求められます。
また、監査を受けるにあたり社内体制を整え、監査法人によるショーとレビューを受ける必要があるため、少なくとも申請期の3期前から準備を進める必要があります。
一般的に、申請期(n)を起点に1期前を直前期(n-1期)、2期前を直前々期(n-2期)、3期前を直前前々期(n-3期)と呼びます。
IPO準備(上場準備)の流れと対応事項

次に、上場準備の大まかな流れとして、「直前前々期(3期前)」以前から「申請期」までの対応事項を確認していきましょう。
直前前々期(3期前)以前
申請期の3期前にあたる「直前前々期」は、IPOに向けた意思決定および直前前期から始まる監査に対応する体制を整備する期間です。
具体的には、以下のような準備・対応を進める必要があります。
直前前々期の対応事項
- IPOに関する意思決定
IPOの実現可能性や、IPOのメリット・デメリットを考慮し、IPOを実施するか否か意思決定を行います。 - プロジェクトチームの編成・体制整備
IPO準備を主導するプロジェクトチームを編成し、監査に向けた社内体制の整備に取り掛かります。 - 監査法人の選定
申請期の2期前(直前々期)から監査法人による監査を受ける必要があるため、3期前(直前前々期)には監査法人を選定する必要があります。
近年、監査法人がなかなか見つからないケース、いわゆる「IPO監査難民」が多々発生しているため、できるだけ早めに監査法人の選定に着手しましょう。 - 監査法人によるショートレビュー
財務やガバナンスについて監査法人のチェックを受け、改善点を抽出してアドバイスを受けます。 - 事業計画の策定
監査法人のアドバイスを受けつつ事業計画を策定します。策定した事業計画は、引受審査や上場審査で内容を精査されます。 - 監査法人による予備調査
IPO監査の受け入れ体制が整っているかを判定してもらうため、監査法人による予備調査を受けます。
直前々期(2期前)
申請期の2期前にあたる「直前々期」は、いよいよ監査法人によるIPO監査(準金商法監査)が始まるため、上場企業と同程度の体制を整え、運用できる段階まで仕上げる期間です。
具体的には、以下のような準備・対応を進める必要があります。
直前々期の対応事項
- 監査法人による予備調査および監査契約の締結
直前前々期の期末から引き続き、監査法人による予備調査を受けます。
予備調査で問題がなければ、監査法人との間で監査契約を締結します。 - 主幹事証券の選定
上場に関するアドバイスやサポートを行ってくれる主幹事証券会社を選定します。 - 監査法人によるIPO監査(準金商法監査)
金融商品取引法第193条の規程に基づき、監査法人によるIPO監査(準金商法監査)を受けます。
直前期(1期前)
申請期の1期前である「直前期」は、上場企業と同等の体制整備が完了し、上場後を見据えた運用を行う試運転期間と言えます。
具体的には、以下のような準備・対応が必要になります。
直前期の対応事項
- 監査法人によるIPO監査(準金商法監査)
直前々期と同様、監査法人によるIPO監査(準金商法監査)を受けます。 - 上場申請書類の作成
上場先の規則に従い、申請書類の作成・準備を進めます。 - 社外取締役の選任
会社法の規定に従い、社外取締役を選任・設置します。
申請期
実際に上場申請・審査を行う「申請期」は、IPO準備の最終局面と言える期間です。
IPO実現に向けて、以下のような準備・対応を行います。
申請期の対応事項
- 定款変更
IPOにあたり、株式取得に関する定款の変更が必要になります。
株主総会特別決議で定款変更を決定後、変更登記を行います。 - 主幹事証券による引受審査
事業の成長性や内部統制などについて、主幹事証券会社による引受審査を実施します。 - 証券取引所への上場申請・審査
必要書類を証券取引所に提出し、上場申請を行います。
申請後、2~3か月程度にわたって上場審査が実施され、問題がなければ申請が承認されます。
IPO準備(上場準備)のポイント

市場によって上場審査基準が異なるとお伝えしましたが、どの市場を選ぶにしても統制環境や社内体制の面で一定以上の水準が求められます。
次は、IPO準備の際に重要になるポイントをご紹介します。
内部統制の強化
IPOを目指す上でもっとも重要なポイントのひとつが、内部統制の強化です。
なぜなら、内部統制は上場時の審査基準のひとつであり、上場企業は金融商品取引法で定められている内部統制報告制度(J-SOX法)に対応する必要があるためです。
内部統制が正常に機能していない場合、不正リスクが高まるだけでなく、業務の有効性や財務報告の信頼性が担保されないため、IPOの実現は不可能だと言えます。
文書管理の仕組み化
IPO準備においては、文書管理の仕組み化も重要なポイントです。
IPO準備の段階から上場後まで、数多くの書類を作成・提出することになります。
しかし、文書管理が仕組み化されていない場合、書類作成が非効率になったり、作成した書類の管理が煩雑化してしまったりと、IPO準備を進める上で大きな負担となってしまう恐れがあります。
IPOを目指すのであれば、文書管理を効率的に行うための仕組みづくりが必要になるでしょう。
業務の効率化
IPOを果たすには、業務の効率化も必要不可欠だと言えます。
先述の通り、IPOを行うには内部統制強化の取り組みや、数多くの書類を作成していく必要があります。また、主幹事証券会社と株式事務代行機関などとのやり取りや、監査対応も必要になります。
これらの作業を通常業務と並行して行うためには、ワークフローを見直して無駄やボトルネックを改善し、業務の効率化を図る必要があるでしょう。
ワークフローシステムがIPO準備に効果的な理由

IPO準備のポイントについてご紹介しましたが、何から手を付けるべきか分からないという企業も多いことでしょう。
そのような場合、ワークフローシステムの導入からIPO準備に着手してみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステムとは、社内で行われる申請や稟議などの手続きを電子化するITシステムで、近年多くの企業で導入されています。
次は、ワークフローシステムの導入がIPO準備に効果的な理由を確認していきましょう。
/
サクッと学ぼう!
『1分でわかるワークフローシステム』
無料ダウンロードはこちら
\
強固な内部統制構築に効果的
ワークフローシステムの導入は、IPOを目指す上で避けて通れない内部統制強化に効果を発揮します。
ワークフローシステムでは、申請手続きの種類や内容によって承認ルートを自動的に判別することが可能です。
そのため、紙の申請手続きで起こり得る、適切な承認ルートを経ずに決裁されてしまうリスクを防ぐことが可能です。
文書管理の仕組み化を実現
ワークフローシステムを導入することで、文書管理の仕組み化にもつながります。
社内手続きをシステム上で一元管理することができるため、申請フォーマットの属人化を防ぎ、申請から承認・決裁、保管という一連の作業を効率化することができます。
また、過去に申請・決裁された文書はシステム上で保存され、「誰が・いつ・何を決裁したのか」という証跡も記録されます。
これにより、必要な文書をすぐに参照することが可能になり、監査などで書類の提出を求められた際もスムーズに対応することができるでしょう。
継続的な業務効率改善につながる
ワークフローシステムの導入により、継続的に業務効率を改善するための基盤が整います。
ワークフローシステムを導入する際は、既存の業務の流れを整理し、システム上で再現していきます。この過程で、業務の流れのなかで非効率な作業やボトルネックになっている作業を発見することができます。
また、ワークフローシステムによって業務の流れが可視化されるため、継続的に業務を評価・改善するための基盤を整えることができるでしょう。
ワークフローシステムでIPOを実現した事例
次に、実際にワークフローシステムを導入し、IPOを実現した事例をご紹介します。
株式会社ニーズウェル様の事例
金融系システム開発を中心としたシステムインテグレータである株式会社ニーズウェル様は、紙の申請・稟議に起因する各種課題を解消するためにワークフローシステムを導入。
ワークフローシステムの導入により、社内手続きのペーパーレス化が促進され、業務プロセスの可視化や決裁スピードの向上を実現しています。また、内部統制強化や監査効率改善にもつながり、IPOに向けた取り組みとしても成果を実感されています。
琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社様の事例
プロスポーツチームの運営など、スポーツ関連事業を展開する琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 様は、IPOに向けた内部統制強化の一環としてワークフローシステムを導入。
導入以前、人員不足に起因する業務ミスが多く、ワークフローが定型化されていないなどの課題が顕在化していました。
ワークフローシステムを導入したことで、業務フローが標準化され人的ミスも軽減。内部統制が強化され、2021年3月にTOKYO PRO Marketへの上場を達成しています。
まとめ
今回は、IPOの意味やメリット・デメリット、IPO準備の流れやポイントについてご紹介しました。
IPOの実現には多くのハードルが存在しますが、上場することによって得られるメリットも大きいです。
将来のIPOを見据えている企業は、今回ご紹介した情報も参考に、ワークフローシステム導入からIPO準備に着手してみてはいかがでしょうか。
もっと知りたい!
続けてお読みください

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。