BPRとは?意味や推進のポイント、成功事例をわかりやすく解説!
- 更新 -

深刻化する少子高齢化や国際市場での労働生産性の低迷などを背景に、近年「BPR」というキーワードに注目が集まっています。
しかし一方で、
「そもそもBPRとは?」
「なぜBPRが注目されているの?」
「企業がBPRに取り組むメリットや手順は?」
といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、BPRの意味や注目を集める理由、メリット、推進方法についてわかりやすく解説します。
BPRの推進に役立つITシステム・ツールや成功事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
ペーパレス化だけでは不十分!
ドキュメントDX(文書業務のデジタル化)が業務工数を大幅に削減
社内文書のペーパーレス化により業務効率や生産性を向上するためのポイントや役立つソリューションについてご紹介しています。
こんな人におすすめ
・ペーパーレス化したのに業務効率が上がらない。
・社内文書に紐づく業務が負担になっている。
・社内文書の何から電子化していいのか分からない。
が業務工数を大幅に削減.pptx-3.png)
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
BPRとは?
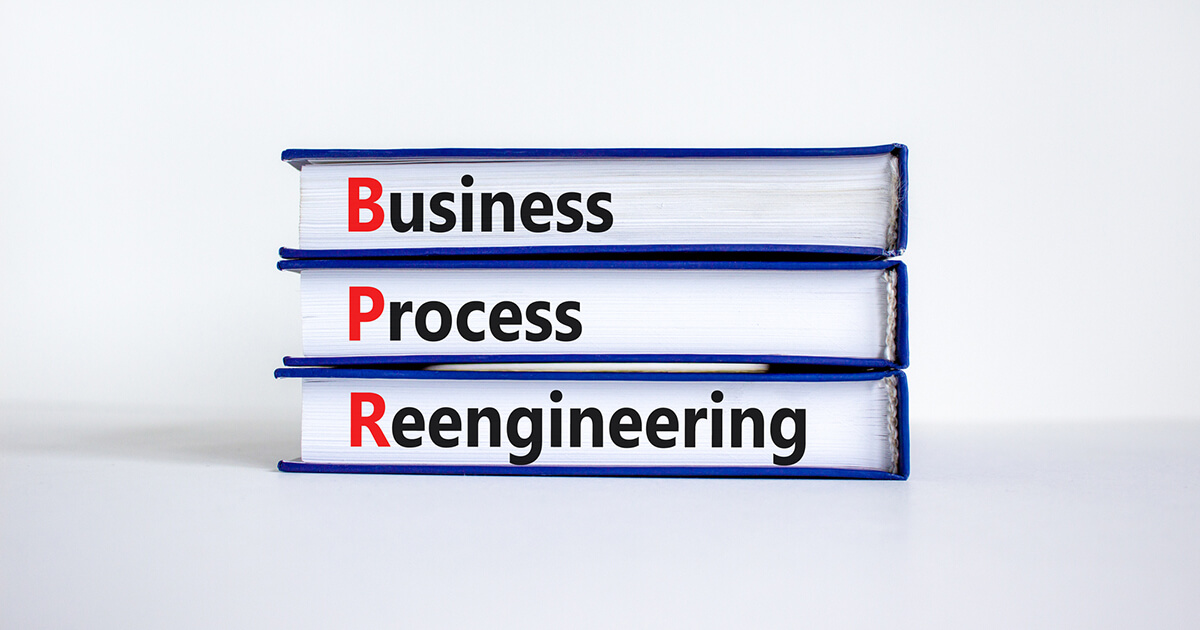
BPR(読み方:ビーピーアール)とは、「Business Process Re-engineering(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)」の頭文字を取った用語で、日本語では「業務改革」と訳されます。
まずは、BPRの意味を確認するとともに、混同しやすい業務改善やDXとの違いを解説していきます。
BPRの意味
BPRは、「プロセスの観点から業務全体を抜本的に見直し再構築すること」を意味します。
BPRの最大のポイントは、「抜本的に見直し再構築する」という点です。
抜本的な見直し・再構築を行うことで、既存の業務フローや組織構造にとらわれることなく、業務の全体最適化を図ることが可能になります。
業務改善との違い
BPR(業務改革)としばしば混同される用語に、「業務改善」があります。
先述の通り、BPRは「業務全体を抜本的に見直して再構築する」のが特徴です。
一方で業務改善とは、「現状の業務の流れを維持しつつ生産性向上やコスト削減を図ること」を意味します。
つまり、BPR(業務改革)と業務改善は「既存の業務プロセスを維持するか否か」が最大の違いと言えるでしょう。
DXとの違い
物事を変革するという意味では、「DX(読み方:ディーエックス)」も「BPR」と近しい用語だと言えます。
DXとは、「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略語で、「デジタル技術による生活やビジネスの変革」を意味します。
BPRがプロセスを変革するのに対し、DXはビジネスモデルなども含めてより広範囲な変革を目的としている点が大きな違いと言えるでしょう。
BPRが注目を集める背景

じつは、BPRという概念がはじめて登場したのは1990年代初頭であり、アメリカ・マサチューセッツ工科大学の教授であるマイケル・ハマー博士が発表した論文のなかで提唱されました。
その後、1993年に刊行された『Reengineering the Corporation』をきっかけにBPRは広く認知され、バブル崩壊後の日本でも一時期注目を集めました。
そして近年、BPRが再び注目を浴びています。
その背景には、深刻化する少子高齢化や国際市場における労働生産性の低迷といった要因が存在しています。
あらゆる業界で人手が不足しているなか生産力を高めていくためには、既存の業務プロセスでは対応することが困難になりつつあります。
加えて、働き方の多様化やデジタル技術の発展といった社会環境の変化も重なり、企業はもちろん、自治体などにおいてもBPRの取り組みが重要視されているのです。
とくに自治体においては、2020年頃に発生した新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけにBPRの必要性が急速に高まりました。
コロナ禍においては自治体経由で住民への支援が数多く行われましたが、書面の手続きや署名捺印といったアナログな業務が多いことで、自治体職員の負担増加が重大な課題として顕在化しました。
これにより、自治体における業務改革、つまり自治体BPRや自治体DXの必要性が高まっているのです。
BPRに取り組むメリット

再注目を集めているBPRですが、取り組むことでどのようなメリットが期待できるのでしょうか。
次は、BPRに取り組むメリットとして以下の5点を紹介します。
BPRに取り組むメリット
- ワークフローの最適化
- 生産性の向上
- 無駄なコスト削減
- 意思決定の迅速化
- 顧客や従業員の満足度向上
ワークフローの最適化
BPRに取り組むことで、業務の流れ、つまりワークフローの最適化につながります。
BPRに取り組み現状の業務全体を見直すことで、無駄な業務や非効率な業務、ボトルネックとなっている工程を洗い出すことができます。
そこで洗い出した無駄や非効率、ボトルネックの解消を図ることで、組織にとって最適化されたワークフローに近づけることができるでしょう。
生産性の向上
BPRの取り組みは、生産性の向上に寄与します。
先述したワークフローの最適化により、無駄や非効率、ボトルネックを排除することで、生産力を維持・向上しつつ労働時間を削減することが可能です。
これにより、時間当たりや一人当たりの労働生産性が高まり、市場における競争力強化にもつなげることができるでしょう。
無駄なコストの削減
BPRの取り組みにより、無駄なコストの削減にもつなげることができます。
BPRで見直しの対象となる無駄な業務や非効率な業務の例として、紙ベースの業務手続きを挙げることができます。
紙ベースの業務手続きでは、書面の印刷コストや拠点間の配送コスト、保管コストなどが発生します。
BPRの取り組みで無駄・非効率な業務を刷新することで、上記のような不要なコストを削減できるだけでなく、先述した労働時間削減により人件費の節約にもつなげることができるでしょう。
意思決定の迅速化
BPRの取り組みは、意思決定の迅速化という面でも効果的です。
組織の意思決定においては、起案・承認・決裁という一連のプロセスが存在します。
しかし、先述した紙ベースの業務手続きを例に出すと、稟議書を手渡しで回覧したり別拠点に郵送したりといった工程に多くの時間を要し、承認者の外出やテレワークなどで意思決定プロセスが停滞してしまうケースが多々あります。
BPRに取り組み、上記のような無駄・非効率な工程を排除することで、起案から決裁までの期間を短縮し、スピーディーな意思決定につなげることができるでしょう。
顧客や従業員の満足度向上
顧客や従業員の満足度向上につながる点も、BPRに取り組むことのメリットだと言えます。
BPRに取り組み、サービスの質や提供スピードが改善することで、顧客や取引先の満足度向上が期待できます。
また、BPRの取り組みで業務効率化や多様な働き方に対応する体制を整えることができれば、従業員のモチベーションや満足度の向上にもつながるでしょう。
BPRの進め方

BPRの進め方は、大きく以下の5ステップに分かれます。
- 検討
- 分析
- 設計
- 実施
- 評価
各ステップについて詳しく確認していきましょう。
1.検討
BPRの取り組みを意味あるものにするためにも、目的や目標をしっかりと検討することが大切です。
組織として掲げる企業戦略に沿う形で、できるだけ具体的に目的・目標を設定しましょう。
目的・目標が決まったら、BPRの対象となる業務範囲を決定します。
目的・目標を達成するうえで、優先的に取り組むべき業務範囲をBPRの対象にすることがポイントです。
2.分析
BPRの対象に設定した業務範囲を分析し、現状の業務プロセスの課題を洗い出します。
まずは現状の業務プロセスの棚卸しを行い、一連のプロセスの中で「誰が・いつ・何をするのか」を把握しましょう。
そのうえで、無駄や非効率、ボトルネックになっている工程がないかを確認し、現状の課題を抽出します。
3.設計
洗い出した課題を解決するための戦略・方針を設計します。
現状の課題に対してどのような解決策が考えられるのかを検討し、戦略・方針を策定しましょう。
また、戦略・方針が決まったら、それを実行するための組織体制やフロー、ルールなどを整えます。
4.実施
いよいよ、ステップ1~3までの準備を行動に移す段階です。
ステップ3で策定した戦略・方針に基づき、新たな体制・フロー・ルールで業務を遂行します。
BPRの推進担当者は、戦略・方針が想定通りに機能しているか、ステップ1で決定した当初の目的・目標から外れていないかを適宜確認することが大切です。
5.評価
BPRの取り組みは、変革を実施して終わりではなく、継続的に評価・モニタリングを行うことが大切です。
設定した目的・目標は達成できているのか、戦略・方針通りに取り組みを実行することができたのかを評価し、次なる改善・変革につなげていきましょう。
BPRに有効な7つのフレームワーク
次は、BPRを推進する際に有効なフレームワークとして、以下の7パターンをご紹介します。
BPR推進に役立つフレームワーク
- ECRSの原則
- SWOT分析
- シックスシグマ
- AARRRモデル
- MECE
- 4P分析
- 4C分析
それぞれのフレームワークの概要について簡単に確認していきましょう。
ECRSの原則
「ECRSの原則」とは、「Eliminate(排除)」「Combine(結合)」「Rearrange(交換)」「Simplify(簡素化)」という4つのプロセスを通じて、既存の業務プロセスの課題抽出と改善を図るフレームワークです。
SWOT分析
「SWOT分析」とは、自社の内部環境と外部環境を「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」という4つの要素で分析し、既存のビジネスの改善点や伸ばすべきポイント、課題やリスクなどの発見につなげるフレームワークです。
シックスシグマ
「シックスシグマ」とは、データの散らばり具合を表す標準偏差「シグマ(σ)」の値を「6シグマ(6σ)」に抑えることを目指し、プロセスの最適化を図るフレームワークです。
AARRRモデル
「AARRRモデル」とは、ビジネスを「Acquisition(獲得)」「Activation(活性化)」「Retention(継続)」「Referral(紹介)」「Revenue(収益)」という5つのプロセスにわけて分析を行い、全体最適化を図るフレームワークです。
MECE
「MECE」とは、「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive(全体として漏れがなく、互いに重複していない)」の頭文字をとった用語で、ロジカルシンキング(論理的思考法)の基本的な概念であり、論理的な問題解決に有効なフレームワークです。
4P分析
「4P分析」とは、「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販促)」という4つの視点で多面的にビジネスを分析するためのフレームワークです。
4C分析
「4C分析」は、「Customer Value(顧客価値)」「Cost(コスト)」「Convenience(利便性)」「Communication(コミュニケーション)」という4つの視点でビジネスを客観的に分析するためのフレームワークです。
BPRの推進にワークフローシステムが役立つ理由

BPRの推進方法や手法について解説しましたが、具体的に何から着手すべきか迷ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合、ワークフローシステムの導入からBPRの取り組みを開始してみてはいかがでしょうか。
ワークフローシステムとは、社内で行われる各種手続きを電子化するシステムのこと。
業務手続きは組織内の全従業員に関係するプロセスであり、ワークフローを導入することで部署部門の垣根を超えて以下のようなメリットが期待できます。
BPR推進にワークフローシステムが役立つ理由
- ワークフローの可視化
- 業務工数やコストの削減
- 時間や場所の制約を解消
ではワークフローシステムがBPRの推進に役立つ理由を詳しく見ていきましょう。
/
サクッと学ぼう!
『1分でわかるワークフローシステム』
無料ダウンロードはこちら
\
ワークフローの可視化
ワークフローシステムを導入する際には、既存業務の棚卸しを行い、システム上に反映していく作業が発生します。
この過程で、ボトルネックになっている作業工程や無駄な業務の発見につなげることができ、ワークフローを可視化することが可能です。
これにより、継続的にワークフローを分析・評価する基盤が整い、BPRの推進に役立てることができるでしょう。
業務工数やコストの削減
ワークフローシステムで業務手続きを電子化することで、申請作業や承認作業が効率化され、意思決定のスピードアップが見込めます。
業務手続きに関わる作業工数が短縮するため、残業などによる人件費の削減にもつなげることができるでしょう。
また、業務手続きのためにわざわざ書面を印刷したり、他拠点に書類を郵送したりする必要もなくなるため、印刷コストや配送コストの削減にもつなげることができます。
こうして削減した業務工数やコストを、BPR推進のための投資に充てることで、取り組みをさらに推進することができるでしょう。
時間や場所の制約を解消
BPRを実現するには、時間や場所の制約を解消することも重要です。
モバイル対応のワークフローシステムであれば、ノートPCやタブレット、スマートフォンからも業務手続きを行えるため、在宅勤務等のテレワーク時や、出張や外回りなどの外出時でも申請や承認・決裁を行うことが可能になります。
これにより、時間や場所にとらわれることなく、あらたな業務体制を整えることができるでしょう。
ワークフローシステムでBPR推進に成功した事例
最後に、ワークフローシステムを活用してBPR推進に成功した事例を紹介します。
ワークフローシステムが社内の業務改革に貢献
シュレッダーのトップブランドとして知られる株式会社明光商会は、ワークフローシステム「X-point」を導入し社内の業務改革(BPR)を推進することに成功しました。
同社では従来、稟議書や決裁申請書・経費精算申請などの業務手続きを複写式の専用用紙に手書きしていました。
しかし、決裁までに時間がかかるほか、書類の紛失や進捗状況が把握できないなどの状況が発生していました。
また、同社には全国37か所に拠点があり、地域によっては数名の社員で業務を行っていたため業務負荷が大きいという課題も存在しました。
そこで同社は、これらの課題を解消するためにワークフローシステム「X-point」の導入を決定しました。
稟議書や決裁申請書、そして交通費精算書も電子化し、意思決定の迅速化や業務の正確性・透明性の向上を実感。
帳票フォームとワークフロー設計の内製化にも着手し、社内の業務改革(BPR)に迅速に対応できる体制構築に成功しています。
ワークフローシステムでBPRと内部統制強化を実現
アルミ、銅などの非鉄金属の輸入・販売を手がけるアルコニックス株式会社は、X-point Cloudを導入し、申請業務のデジタル化を中心に業務の刷新に成功しました。
同社は申請承認を紙で行っており、事業拡大に伴い申請業務に用いる紙の利用量が多くなりました。その結果、数多くのキャビネットの中に帳票類が保管されていました。
また、M&Aした子会社と申請業務のフローや決裁権限、申請書のフォーマットが異なるという内部統制上の問題も抱えていました。
そこで同社は「X-point Cloud」を導入することで、申請承認業務を電子化。
60種類以上の申請書のデジタル化に成功しました。これにより、オフィスのキャビネットの数が減りスペースを有効活用できるようになったほか、従来の1/3ほどの時間で決裁が得られるようになりました。
また17社の子会社での運用を統一することにも成功しており、ワークフローシステムによってBPRと内部統制の強化を促進しています。
まとめ
今回は、BPRの意味や推進方法、ワークフローシステムが役立つ理由や成功事例を紹介しました。
BPRは、組織全体の業務最適化を実現するうえで欠かせない取り組みだと言えます。
そして、ワークフローシステムを活用することで、BPRの取り組みを効果的に進めることが可能です。
これからBPRに取り組みたいと考えている企業や、BPRの推進に課題を感じている企業は、今回ご紹介した情報も参考にワークフローシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
もっと知りたい!
続けてお読みください
ペーパレス化だけでは不十分!
ドキュメントDX(文書業務のデジタル化)が業務工数を大幅に削減
社内文書のペーパーレス化により業務効率や生産性を向上するためのポイントや役立つソリューションについてご紹介しています。
こんな人におすすめ
・ペーパーレス化したのに業務効率が上がらない。
・社内文書に紐づく業務が負担になっている。
・社内文書の何から電子化していいのか分からない。
が業務工数を大幅に削減.pptx-3.png)

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。








