ダブルチェックとは?意味や見落とし対策、業務の信頼性を高める方法を解説!
- 更新 -
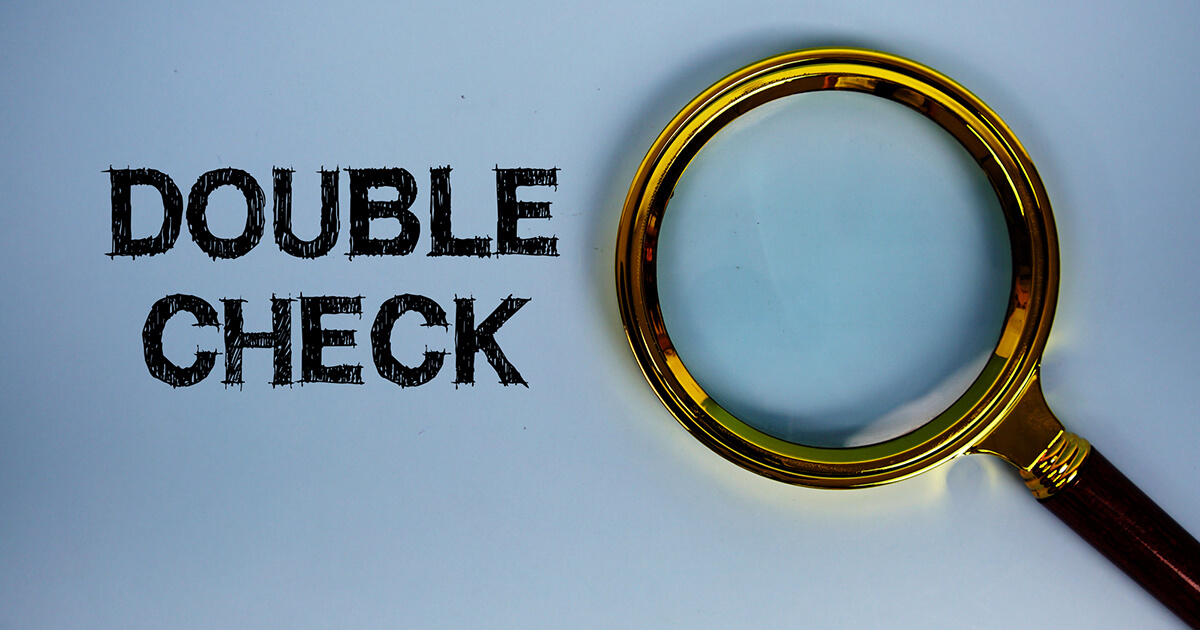
本記事では、ダブルチェックの意味や必要性、見落としを防ぐための対策について解説します。業務の信頼性を高めるツールやその導入事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
もっと見る
定型業務の無駄を削減!タイパ向上で利益最大化を目指そう!
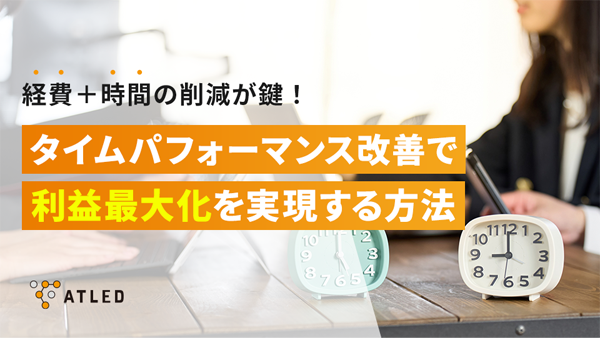
こんな人におすすめ
・「コスト削減」をしているが効果が限定的
・ 定型的なチェック作業で工数が圧迫されている
・ 業務の生産性を向上させたい
ダブルチェックとは?
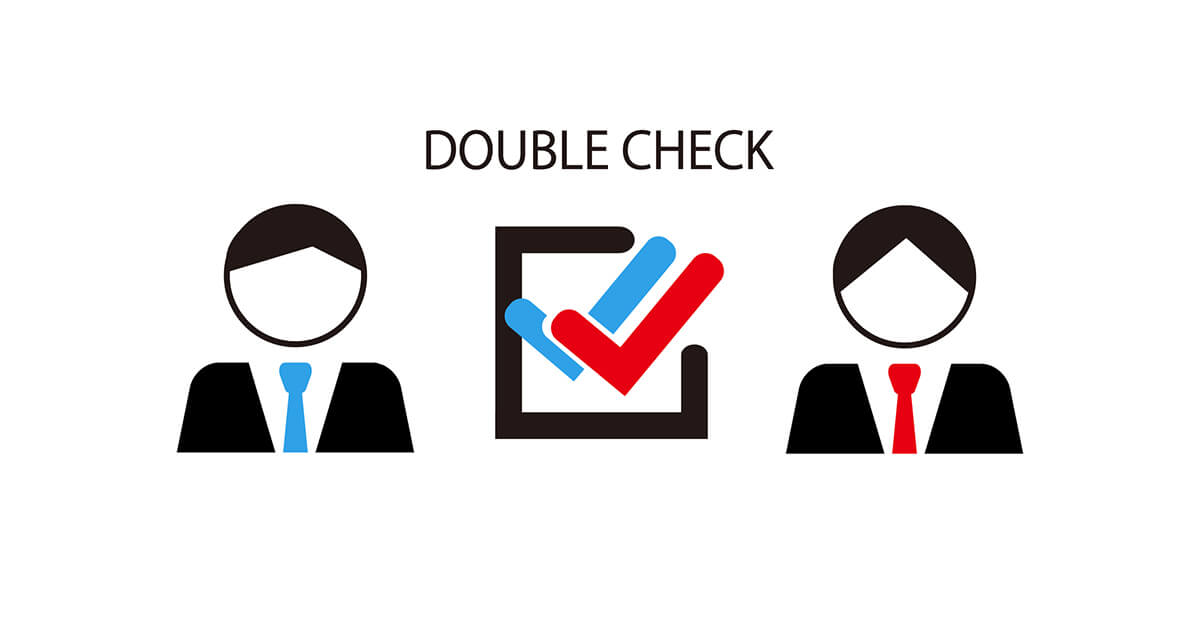
ダブルチェックとは、ある作業や成果物に対し、担当者本人とは別の人物が再度確認(チェック)を行うことを意味します。
二人体制で確認することで、一人では見落としがちなミスを発見し、業務の品質と正確性を高めることを目的とします。第三者の客観的な視点を入れることで、思い込みによる誤りや単純な見落としなど、さまざまなヒューマンエラーのリスクを抑えることができます。
また、ダブルチェックとよく似た用語にクロスチェックがあります。クロスチェックは、異なる知識や立場の担当者が多角的に検証することで、ダブルチェックでも行われることがあります。
ダブルチェックが「意味ない」と言われる理由
業務の品質や正確性を担保するために行うダブルチェックですが、実際の業務現場において「意味がない」と判断されてしまうケースも存在します。
ではなぜ、ダブルチェックは意味がないと感じられてしまうのでしょうか。その要因について見ていきましょう。
心理的要因で見落としが発生しやすい
ダブルチェックでよくある問題として、心理的要因による見落としが発生しやすいという点が挙げられます。
たとえば、複数人が関わることで、かえって一人ひとりの当事者意識が薄れてしまうケースが考えられます。「次の人がしっかり見てくれるはず」という無意識の甘えが確認の精度を低下させてしまいます。
また、確認作業が定型的に繰り返されるケースでは、脳への刺激が少なくなり、注意力を散漫にさせます。確認作業が「ただ目で追うだけ」のマンネリ化したタスクになってしまったり、「いつも問題ないから今回も大丈夫」という思い込みが働いたりして、ミスを見落としてしまうリスクが高まります。
プロセスが形骸化しやすい
ダブルチェックの仕組みそのものに問題があり、単なる形式的な作業になっているケースも少なくありません。
たとえば、ダブルチェックにおける確認項目や基準が明確に定義されていない場合、チェックの質が担当者によってバラついてしまいます。また、確認を行う担当者が当該業務の内容を深く理解していないと、専門的な内容の誤りや矛盾などに気付くことが難しくなります。
時間の浪費と生産性の低下
ダブルチェックは、作業者本人に加えて確認者も同じ内容に目を通す必要があるため、単純に工数が倍近くかかり、時間の浪費につながりやすいという側面があります。
業務全体のリードタイムが長くなるため、スピードが求められる業務や、タイムリミットが定められている状況においてはボトルネックになりやすいと言えます。
さらに、時間に追われた状態での確認作業は、丁寧さを欠き、ミスを見逃す原因となり得ます。
ダブルチェックでの見落としを防ぐ対策
ダブルチェックでのミスを防ぐには、どうすればよいのでしょうか。次は、ダブルチェックで見落としを防ぐための対策をご紹介します。
仕組み・ルールで標準化する
誰がダブルチェックを担当しても一定の品質を保てるように、チェックプロセスを仕組み化しましょう。
そのために、もっとも効果的で導入しやすいのがチェックリストの作成です。確認すべき項目を具体的にリストアップすることで、担当者のスキルに依存しない網羅的なチェックが可能になります。なお、作成したリストは定期的に見直し、常に実際の業務内容に合致した状態を保つことが重要です。
また、1人目と2人目で確認する観点を意図的に変えることも有効です。たとえば、1人目は「誤字脱字や形式面の正しさ」、2人目は「内容の論理構成や要求事項との整合性」といった形で役割を分担します。これにより、多角的な視点が生まれるとともに、各担当領域に対する責任感が生まれ、見落としのリスクを減らせます。
担当者の意識やチェック環境を改善する
ダブルチェックを行う担当者の意識や環境を改善することも大切です。
まず、「なぜダブルチェックが必要なのか」という目的をチーム全体で再認識しましょう。「品質を維持し顧客の信頼を得るため」といった共通認識を持つことで、確認作業への当事者意識が高まります。
また、チェックに集中できる時間と環境の確保も大切です。確認作業のための時間をあらかじめスケジュールに組み込み、他の業務に妨げられない環境を確保しましょう。
ツール・システムを活用する
人間の注意力には限界があります。定型的に繰り返されるチェック作業はツールに任せ、人はより高度な判断に集中するのが理想です。
たとえば、校正ツール・チェックツールの導入も一策です。誤字脱字や表記ゆれなどを自動検知する校正ツールは、文章作成業務において絶大な効果を発揮します。
また、近年では生成AIをはじめとしたAI技術の発展が著しく、業務での活用範囲も広がりつつあります。あくまで最終的な判断は人間が行う必要がありますが、確認作業をAIに補助してもらうのも有効な選択肢と言えるでしょう。
ワークフローシステムで業務の信頼性向上

ダブルチェックで見落としを防ぐ対策として、ツール・システムの活用を紹介しましたが、業務の信頼性を高める具体的なソリューションのひとつがワークフローシステムです。
ワークフローシステムとは、社内で行われる各種申請や稟議といった手続きを電子化するツールのこと。では、ワークフローシステムが業務の信頼性向上に役立つ理由を見ていきましょう。
/
サクッと学ぼう!
『1分でわかるワークフローシステム』
無料ダウンロードはこちら
\
適切な業務フローの徹底
ワークフローシステムは、申請から承認までの一連の業務手続きを電子化し、あらかじめ規定した業務フローを徹底することが可能です。これにより、然るべき人物の確認を経ずに業務が進行してしまうリスクを解消し、チェックプロセスの形骸化を防ぐことができます。
証跡管理による責任の明確化
ワークフローシステムには、「誰が、いつ、何を確認・承認したか」という証跡が記録されます。これにより、各担当者における確認作業への責任感が自然と高まり、万が一問題が発生した際も、記録を基に原因を迅速かつ客観的に特定することが可能になります。
タスクの可視化で遅延・漏れを防止
ワークフローシステムによっては、確認・承認待ちのタスクが一覧として表示されます。これにより、「確認を忘れていた」「申請に気づかなかった」といったヒューマンエラーによる業務の遅延や確認漏れを効果的に防ぎます。また、確認・承認が止まっている担当者に対して督促通知を送ることもできるので、チェックの迅速化・円滑化が見込めます。
業務の信頼性・正確性向上に成功した事例
次に、シリーズ累計5,000社超の導入実績を誇るワークフローシステム「X-point Cloud」と「AgileWorks」を活用して業務の信頼性・正確性を高めることに成功した事例をご紹介します。
ダブルチェックなどの定型業務を削減(加藤建設)
株式会社加藤建設は、「X-point Cloud」を導入して紙の申請業務を電子化することに成功しました。
同社では従来、ほとんどの業務で紙の書類が使われており、申請業務の過程ではミスによる手戻りやシステムへの転記作業といった非効率な作業が発生するなど、業務効率化を阻害していました。そこで同社はワークフローシステムによる申請業務の電子化を決断。製品選定の結果、申請フォームや承認ルートを細やかに設定可能な「X-point Cloud」の導入に至りました。
導入後、工事関係書類を含む約100種の申請業務のデジタル化を実現。承認ルートの自動分岐機能や関連書類機能を活用することで、大幅な業務効率化を実現しました。さらに同社は、他の業務システムとのデータ連携やRPAなどを駆使し、転記作業やダブルチェックなどの定型業務も削減することに成功しています。
確認作業を自動化し作業漏れやミスを防止(大和総研)
株式会社大和総研は、「AgileWorks」を導入して900種類にもおよぶ申請書を電子化。入力データを活用した業務効率化やリスク低減も推進しています。
「AgileWorks」の導入以前よりワークフローシステムを利用していた同社ですが、旧システムは利用範囲が限定されており、メンテナンスも難しいことから、全社展開には至っていませんでした。
そこで同社は、全社標準となるワークフローシステムの導入に向け製品選定を開始。検討の結果、各業務の所管部門がセルフ運用でき、操作性や信頼性に優れている「AgileWorks」の導入に至りました。
導入後、約900種類の申請書を「AgileWorks」上で運用しており、月間の処理件数は約2万5千件にものぼります。また、同社では申請・決裁業務をペーパーレス化するだけでなく、業務を自動化するための情報基盤としても「AgileWorks」を活用。たとえば、「AgileWorks」のデータを利用して「他システムへの連携指示」や「セキュリティールームの入室申請と利用実績の自動チェック」といった業務の自動化を推進しています。これにより、確認作業における漏れやミスを防止し、業務の省力化とリスク管理面の強化を実現しています。
まとめ
今回は、ダブルチェックの意味や必要性、見落としを防ぐための対策について紹介しました。
ダブルチェックは、適切に行うことで業務の信頼性や正確性を高めることが可能です。一方で、人手によるチェックではミスの発生を完全に防ぐことは困難であり、チェックプロセスが形骸化しやすいという課題も存在します。
ダブルチェックによる信頼性や正確性の担保に課題を感じている方は、記事内でご紹介したワークフローシステムの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
もっと知りたい!
続けてお読みください
ダブルチェックは無駄が多い!?
定型業務の無駄を削減!タイパ向上で利益最大化を目指そう!
利益最大化に欠かせない「タイパ向上」の方法とは?
こんな人におすすめ
・「コスト削減」をしているが効果が限定的
・ 定型的なチェック作業で工数が圧迫されている
・ 業務の生産性を向上させたい
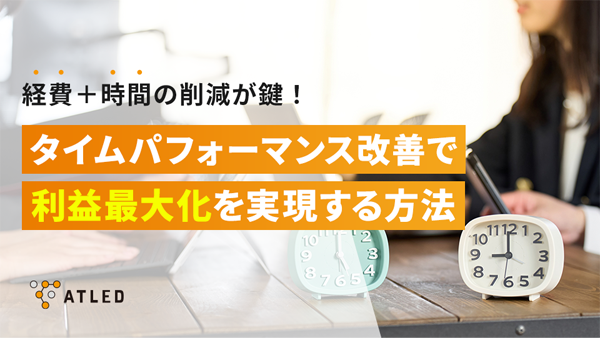

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。








