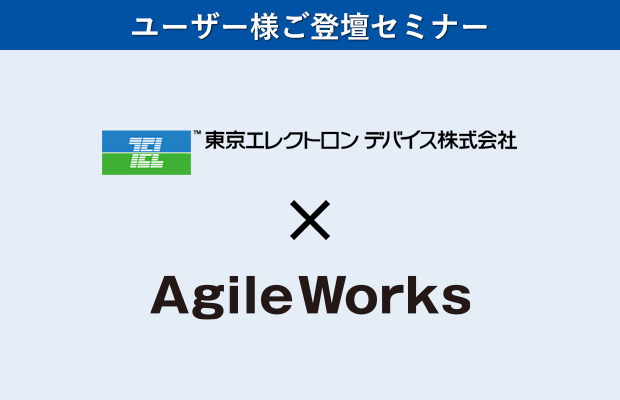クロスファンクショナルチーム(CFT)とは?意味やメリット、導入事例を紹介!
- 更新 -

本記事では、クロスファンクションやクロスファンクショナルチーム(CFT)の意味やメリットについてわかりやすく解説します。
クロスファンクション推進に役立つITシステムや導入事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
- クロスファンクションやクロスファンクショナルチームとは?
- クロスファンクショナルチームの導入メリット
- クロスファンクショナルチームを導入するポイント
- クロスファンクション推進にワークフローシステム
- ワークフローシステムによるクロスファンクション推進事例
- まとめ
もっと見る
クロスファンクションやクロスファンクショナルチームとは?
クロスファンクション(Cross Function)とは、部門の垣根を超えて組織横断でメンバーを招集し、全社的な課題解決を目指す取り組みのこと。
そして、クロスファンクションの観点で組成されたチームを指して、クロスファンクショナルチーム(CFT/Cross Functional Team)と呼びます。
クロスファンクショナルチームという概念は、1980年代に国際市場で高い競争力を誇った日本企業をモデルに、アメリカを中心に理論化・体系化され、その後グローバルに普及したと言われています。近年では、クロスファンクショナルチームを逆輸入のような形で取り入れる日本企業も増えつつあります。
クロスファンクショナルチームの導入メリット

次は、クロスファンクショナルチームを導入することのメリットについて見ていきましょう。
効率的な問題解決
クロスファンクショナルチームは、異分野のメンバーが集まることで多角的な視点で問題を分析することができ、迅速かつ効果的に解決につなげられる可能性が高まります。
各メンバーが持つ専門知識を活かし、複雑な問題にも効率的に対応できるのが大きな強みと言えるでしょう。
イノベーションの促進
企業がイノベーションを促進していくには、多様性が重要な要素となります。
クロスファンクショナルチームは、異なるバックグラウンドを持つメンバーが集まることで多様性が高まり、新たなアイデアや視点が生まれやすくなります。
コミュニケーションの活発化
クロスファンクショナルチームでは、異なる部門や専門分野のメンバーが相互に協力するため、社内コミュニケーションが活発になります。これにより、組織全体の情報共有やナレッジ交換が強化されます。また、相互の立場を理解し合うことで、チーム内の信頼関係も深まるでしょう。
クロスファンクショナルチームを導入するポイント
次に、クロスファンクショナルチームを導入する際に押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
チーム編成のポイント
クロスファンクショナルチームを編成する際は、部門の垣根を超えて多様なメンバーを招集することが大切です。多角的な視点から問題に取り組むためにも、異なる専門分野やバックグラウンドのメンバーを集めることを意識しましょう。
また、集めたメンバーのなかからチームをまとめるリーダーを選定します。リーダーはメンバー間の調整やサポートを行い、円滑なコミュニケーションを促進する役割を担います。
明確な目標設定が重要
クロスファンクショナルチームを有効に機能させるには、明確な目標設定が必要です。
チームの目標・ミッションを明確に定義し、メンバー全員で共有することで、一体感を持って取り組むことができます。
なお、目標は具体的かつ定量的に測定可能なものがよいでしょう。目標に対する進捗状況を定期的に確認し、アジャイル的思考でPDCAをスピーディーに回していくことが大切です。
コミュニケーションの仕組みを整備
メンバーそれぞれが異なる専門分野・バックグラウンドを持つチームだからこそ、コミュニケーションを活発化する仕組みを整えることが大切です。
定期的なミーティングで進捗状況の共有やフィードバックを行ったり、気軽に意見を交換できるプラットフォームを用意するなど、コミュニケーションの場を整えましょう。
また、コミュニケーションを円滑にするためにデジタルツールを活用するのもポイントです。グループウェアやプロジェクト管理ツールなどのツールを活用して、シームレスなコミュニケーションを促しましょう。
クロスファンクション推進にワークフローシステム

これまでに説明したように、クロスファンクションは組織横断の取り組みであり、多くの部署部門が相互に関わり合うことになります。そこで課題になりやすいのが、意思決定のプロセスです。
一般的に、意思決定に関わる関係者が増えるほど、決裁までの期間は伸びやすくなります。そのため、クロスファンクショナルチームの強みであるスピーディーかつ効率的な問題解決力を担保するには、円滑に意思決定を行える仕組みも合わせて整備することが重要だと言えます。
そこでおすすめしたいのが、ワークフローシステムです。ワークフローシステムとは、社内で行われる各種申請や稟議などの手続きを電子化するツールで、意思決定の迅速化や精度向上に効果的です。
では、ワークフローシステムがクロスファンクション推進に有効な理由を見ていきましょう。
/
サクッと学ぼう!
『1分でわかるワークフローシステム』
無料ダウンロードはこちら
\
部門の垣根を超えたスピーディーな意思決定を実現
ワークフローシステムを導入することで、部門の垣根を超えたスピーディーな意思決定が可能になります。
組織構造や職務権限をシステム上に反映することができ、部署部門をまたぐ複雑な意思決定プロセスであっても対応可能。申請・起案内容に応じて適切な承認ルートを自動判別し、即座に回覧を実行することができます。
また、ノートPCやタブレット端末、スマートフォンなどのデバイス上で申請・起案から承認・決裁まで完結することが可能。時間や場所の制約が解消されるので、回覧待ち・承認待ちによる停滞を防ぎつつ迅速な意思決定につなげることができます。
システム連携で各業務をつなぐハブとして機能
各種システムとの連携により利便性を高めていけるのもワークフローシステムの強みです。
クラウドサービス最盛の今、部門単位で業務システム・ツールを導入しているという企業は多いのではないでしょうか。部門ごとに個別最適化を進めた結果、クラウド乱立の状態に陥ってしまい、管理の負担が増大してしまったり、データのサイロ化が進んでしまうケースは少なくありません。
ワークフローシステムを各種システム・ツールと連携することで、システム・ツールごとに行われていた手続きをワークフローシステム上に集約し、二重入力や転記などの手間やデータのサイロ化を解消可能。マスタデータ連携によってメンテナンスを効率化することもできるでしょう。このように、ワークフローシステムと各種システムを連携することで、部門ごとに行われていた業務をつなぐハブとして活用することができるのです。
ワークフローシステムによるクロスファンクション推進事例
最後に、ワークフローシステムによるクロスファンクション推進事例を見てみましょう。
ここでは、シリーズ累計4,500社超の導入実績を誇るワークフローシステム「AgileWorks」を導入している企業のなかから、注目すべきクロスファンクション事例をご紹介します。
新商品発売プロジェクトのスピードアップを達成(えがお)
株式会社えがおは、「AgileWorks」の導入により申請業務やシステムの保守運用に費やすコストを大幅削減するとともに、多くの部門が関わる新商品発売プロジェクトのスピードアップを達成しました。
同社では以前より、経費精算などの金銭が絡む申請をワークフローシステムで運用していたものの、組織改編のたびに外部パートナーに改修依頼を行っており、コストや対応スピードの面で課題となっていました。また、当時のシステムは同社の組織構造や承認経路を再現することが難しく、機能面でも不満を抱えていました。
そこで同社は、これらの課題を解消するためワークフローシステムのリプレイスを検討開始。同社の組織構造や承認経路を柔軟に設計できる機能性や、GUIベースで操作できるメンテナンス性の高さを評価し、「AgileWorks」の導入を決めました。
「AgileWorks」へのリプレイス後、システムの保守運用作業は段階的に社内へと移管され、運用開始から数年後には完全内製化を実現。課題であった組織改編への対応が迅速化し、以前は3日ほどかかっていた改修作業も最短即日で完了できるようになりました。
また、「AgileWorks」は意思決定の迅速化にも寄与。たとえば、新商品発売プロジェクトには開発部門など7以上の部門が関わっており、関係するすべての部門による承認を経て決裁に至るには長期間を要していました。「AgileWorks」の導入によって各部門が並列で承認を行えるようになり、新商品発売プロジェクトにおける決裁期間は大幅に短縮されています。
クロスファンクション業務における円滑な申請・承認を実現(東京エレクトロンデバイス)
東京エレクトロンデバイス株式会社は、他社ワークフロー製品から「AgileWorks」へのリプレイスにより運用負荷を大幅に軽減することに成功。クロスファンクショナルな業務体制
かねてよりワークフローシステムを利用してきた同社ですが、当時利用していたシステムは老朽化が進んでおり、監査基準となる証跡管理への対応面で不足を感じていました。また、複雑な承認フローへの対応ハードルが高く、構築・運用の負荷が大きいことに加え、他システムとの連携による拡張性が課題となっていました。
これらの課題を解消するため同社はリプレイスを決断。組織・ユーザー・申請書・回付ルートのすべてを柔軟に設定でき、なおかつ履歴対応している点などを評価し「AgileWorks」の導入を決めました。
リプレイス後、同社の申請・承認に関連する業務全体が効率化されたほか、各部署で帳票の作成やフロー管理を行えるようになったことでIT企画部の負担が軽減。各種業務システムやSAPとの連携も可能になり、拡張性の課題も解消されています。
また、同社では別組織の一部申請を代理組織が行うクロスファンクション業務を実施。システム連携処理用のダミーユーザーによる申請や、承認役職をランク別にグループ化する機能を活用した承認ルート設定、細やかにコントロール可能な権限委譲設定を活用することで、クロスファンクション業務における円滑な申請・承認処理を実現しています。
まとめ
今回は、注目度が増すクロスファンクションやクロスファンクショナルチームの意味やメリット、導入のポイントについて解説しました。
クロスファンクショナルチームを導入することで、全社的な課題解決やイノベーションの創出、コミュニケーションの活発化など、多くのメリットが期待できます。
そして、クロスファンクションの推進に有効なITシステムのひとつが、記事内でもご紹介したワークフローシステムです。
クロスファンクショナルチームの導入を計画している方や、取り組みに課題を感じている方は、ワークフローシステムの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
もっと知りたい!
続けてお読みください

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。