起案とは?意味や起案書の書き方、運用を効率化するシステムを紹介!
- 更新 -
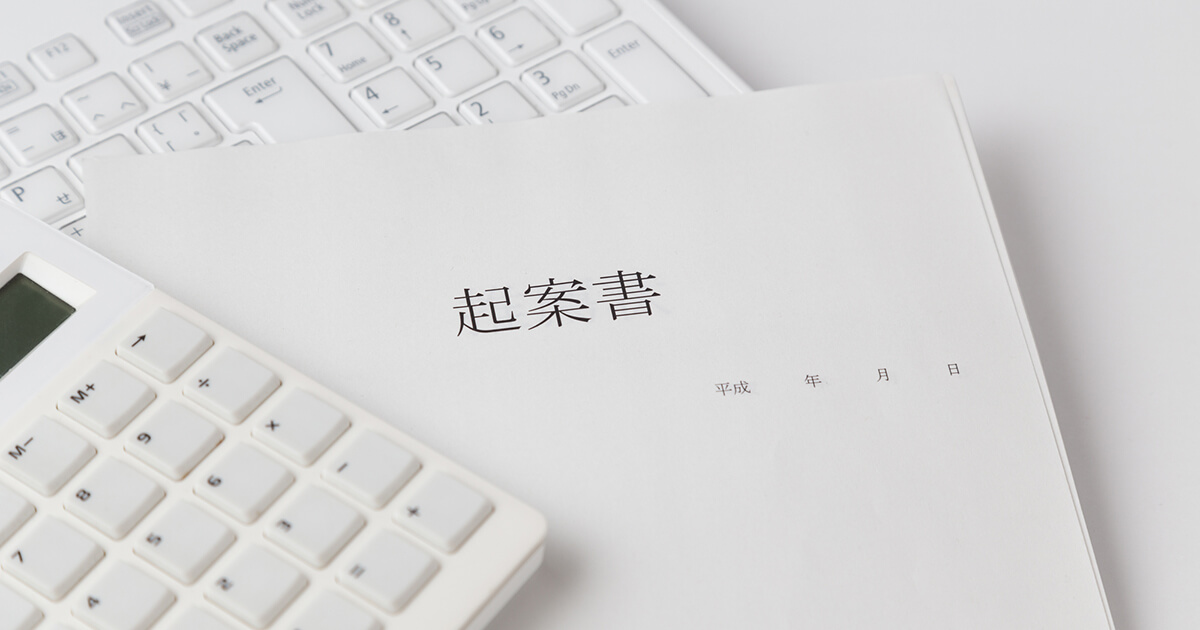
本記事では、起案の意味や起案書の書き方、起案から始まる一連の業務プロセスを効率化する方法までわかりやすく解説します。
起案文書の電子化や運用の効率化を実現した事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
もっと見る
設計不要な起案・申請テンプレートが充実しているワークフローシステム
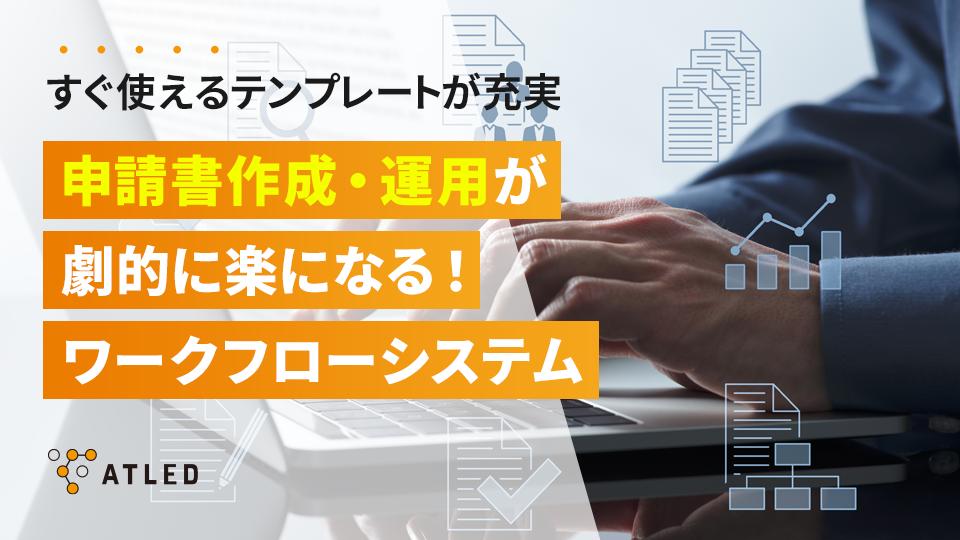
こんな人におすすめ
・新しく帳票を設計するのが大変
・自社のプロセスに合うテンプレートが見つからない
・担当者によって申請書ひな形がバラバラ
起案とは?

まずは、起案とはどのようなものなのか、意味や類似用語との違いについて見ていきましょう。
起案の意味
起案(きあん)とは、ある事柄について承認・決裁を得るための案を作成し、関係者に提起することを意味します。
起案の際には、承認・決裁を得たい事柄についての内容や理由などを記載した文書を作成するのが一般的であり、その文書のことを「起案書」や「起案文書」と呼びます。また、起案を行った者は「起案者」と呼ばれます。
組織が意思決定を行う際は、関係者の承諾を得たうえで、組織全体の総意として決定を下す必要があります。具体的には、「起案」⇒「回覧」⇒「承認・合議」⇒「決裁(最終承認)」というプロセスで意思決定を行うケースが一般的です。つまり起案は、意思決定プロセスの出発地点であり、厳正な組織運営に欠かせない工程だと言えるでしょう。
稟議との違い
ビジネスシーンでは、起案と間違えやすい用語がいくつか存在します。
なかでも混同しやすいのが、稟議(りんぎ)です。
稟議とは、ある事柄について関係者の承認を経て最終的な決裁を得るためのプロセスを指します。起案が意思決定プロセスの最初の工程であるのに対し、稟議は起案から決裁までの一連のプロセスを指している点が違いだと言えます。
なお、稟議の際に用いられる文書は稟議書と呼ばれますが、これは起案書や起案文書とほぼ同じ意味合いで使われるケースが多々あります。
そのほか、起案と似ている用語としては以下を挙げることができます。
- 提案:案や意見を提示すること。
- 計画:方法や順序などを考えること。
- 立案:案や計画を作ること。
- 企画:計画を立てること。
起案書の記載項目と書き方
次に、起案書の記載項目と書き方を見ていきましょう。
起案書の記載項目
起案書には決まった書式が存在するわけではありませんが、以下のような項目を記載するのが一般的です。
タイトル・件名
起案内容を簡潔に表す件名を記載します。
起案者の情報
起案者の情報として、氏名や所属部門などを記載します。
宛先
宛先として、起案書を受け取る人物の氏名や部門名を記載します。
起案日
起案書を作成・提出する日付を記載します。西暦・和暦のどちらでも問題ありませんが、社内で統一するようにしましょう。
起案内容
起案内容は、前文・主文・末文の三段構成で記載するケースが一般的です。
前文では、起案の概要を簡潔に示すとともに、背景や目的を説明します。
主文では、起案の詳細を記載します。計画や実施期間、必要な予算・リソースなどを具体的に示します。
末文では、起案内容の価値や必要性を再度強調します。起案内容が実現した場合の成果やメリットを示しましょう。
備考・その他
そのほか、申し送り事項や添付資料などがある場合にはその旨記載しましょう。
起案書の書き方のポイント
起案文書を作成する際は、関係者の承認・決裁を得るために押さえておくべき書き方のポイントが存在します。
まず、起案文書を書く際は要点を端的にまとめることが大切です。冗長な表現を避け、できるだけ簡潔にまとめるよう意識するとともに、必要に応じて箇条書きも使用しましょう。
また、わかりやすい表現であることも重要です。専門用語はできるだけ平易な言葉に置き換えたり、簡単な注釈を付けたりするなど、誰が読んでも理解できるような表現を心がけましょう。
起案を電子化し意思決定を効率化するならワークフローシステム

紙ベースで起案を行っている場合、起案文書の作成・印刷や手渡しによる回覧、ハンコでの押印といったアナログ作業が多数発生します。これらのアナログ業務は無駄・非効率を生む原因であり、意思決定の遅れや働く場所の制約を生んでしまいます。
これらの課題を解決し、起案から回覧、承認、決裁や管理まで、意思決定の一連のプロセスを効率化するのであれば、ワークフローシステムの導入が有効です。
では、ワークフローシステムの導入によって業務がどのように変わるのか見ていきましょう。
意思決定プロセスを一気通貫で電子化
ワークフローシステムは、社内で行われる各種申請・稟議などの手続きを電子化するITツールです。
起案から回付、権限者による承認、決裁まで一気通貫でシステム上で完結できるので、紙ベースの起案・稟議よりもスピーディーに意思決定を行うことができます。
たとえば、初期値の自動取得やマスタ参照入力といった起案文書の作成を効率化する機能や、起案内容に応じて適切な承認ルートを自動判別する機能を備えている製品も存在します。
また、承認状況をシステム上で確認したり、製品によっては外出先や在宅勤務でもノートPCやスマートフォンなどのモバイル端末からの起案・承認を行えるので、紙ベースの起案でありがちな遅延を防ぎ、迅速な意思決定につなげることができるでしょう。
ナレッジマネジメントや内部統制の観点でも有効
ワークフローシステムの活用は、ナレッジマネジメントや内部統制の強化という面でも有効です。
ワークフローシステムで処理された起案はデータとして蓄積され、さまざまな条件で検索したり、出力・集計したりすることが可能です。これにより、必要に応じて過去の意思決定データを参照し、より良い意思決定に役立てることができます。
また、「いつ・誰が・何を起案し、どのように処理されたのか」という証跡を管理でき、役職やグループごと、あるいは個別に閲覧権限を設定することもできるので、強固な内部統制の基盤としても機能します。
システム連携で業務効率化やデータ活用を加速
他システム・ツールとの連携により、デジタル化の範囲を拡張していける点も、ワークフローシステムの特徴です。
近年では、特定の業務領域に特化したシステム・ツールが多数登場しており、部署部門ごとにシステム導入を進めているという企業も多いのではないでしょうか。しかし、業務領域ごとに個別最適化が進んだ結果、システム乱立の状態に陥ってしまい、かえって利便性が低下してしまったり、メンテナンスの負担が増加したり、データのサイロ化が発生したりといった状況が発生してしまいがちです。
ワークフローシステムは、各種システムとシームレスにつながり、システム毎に行われていた手続きを集約したり、マスタデータ連携によりメンテナンスを効率化したりすることが可能です。ワークフローシステムが各種システムのハブとして機能することで、業務効率化やデータ活用を加速していくことができるでしょう。
ワークフローシステムで起案の電子化・効率化を実現した事例
では、ワークフローシステムで起案の電子化・効率化を実現した事例を紹介します。
起案から承認まで一気通貫でデジタル化(いえらぶGROUP)
株式会社いえらぶGROUPは、「X-point Cloud」を導入して起案から承認までをデジタル上で完結する体制を構築しました。
「X-point Cloud」の導入以前、同社では口頭やメールで起案・承認を行っていましたが、社員数や拠点が増加するにつれて決裁期間が長期化し、組織全体の生産性を引き下げる要因となっていました。
そこで同社は、「X-point Cloud」を導入して未整備だった申請業務をワークフロー化。承認権限の階層化にも取り組み、拡大中の組織にふさわしい業務体制を目指しました。
現在、同社では約60種類の申請書を「X-point Cloud」で運用しており、起案から承認までデジタル上で一気通貫に行える体制が完成。組織拡大により拠点や社員数が急増するなか、申請業務や意思決定は以前よりも円滑化されています。
起案文書の電子化で年間2,000時間の工数削減を達成(日鉄ソリューションズ)
日鉄ソリューションズ株式会社は、「AgileWorks」を導入して営業職が作成する起案文書を電子化しました。
「AgileWorks」の導入以前、同社では受発注などの申請業務は電子化していたものの、取引先との契約締結時の稟議申請については、営業職が紙の申請書で起案を行っていました。紙の起案文書は回付の手間が大きいだけでなく、リモートワークの普及に歯止めがかかる恐れもあることから、同社はワークフローシステムの導入を決定。検討の結果、導入しやすくユーザー側の負担軽減にも効果が期待できる「AgileWorks」の採用に至りました。
現在、同社では年間1,400件の稟議申請が「AgileWorks」で行われており、紙帳票による起案が不要になったことで、年間で約2,000時間の工数削減を達成。さらに、働き方改革の推進やコンプライアンスの強化にも効果を得るなど、大きな成果につながっています。
起案にまつわるよくある質問
ここでは、起案にまつわるよくある質問について簡潔に回答します。
Q.起案とはどんな意味?
A.起案とは、ある事柄について承認・決裁を得るための案を作成し、関係者に提起することです。
Q.稟議との違いは?
A.起案が意思決定プロセスの最初の工程であるのに対し、稟議は起案から決裁までの一連のプロセスを指している点が違いです。
Q.起案書とはどんな文書ですか?
A.起案書とは、起案の際に作成する書類であり、具体的な起案内容が記載されます。
Q.起案書の運用を効率化するには?
A.起案を効率化するには、電子化が有効です。とくに、ワークフローシステムで電子化することで、起案から決裁までの一連の意思決定プロセスを効率化することが可能です。
まとめ
今回は、組織における意思決定の出発地点である、起案に焦点を当てて解説してきました。
紙ベースで稟議を行っている場合、さまざまな無駄や非効率が生じてしまいがちであり、それらの課題を解消するには電子化が有効です。
起案文書の運用に課題を感じている企業や、意思決定の迅速化を目指している企業は、記事内でご紹介したワークフローシステム「X-point Cloud」や「AgileWorks」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
もっと知りたい!
続けてお読みください
起案書の運用を効率化!
設計不要な起案・申請テンプレートが充実しているワークフローシステム
エイトレッドのワークフローシステムは、1,000以上の申請書テンプレートとノーコードで簡単に申請書を作れる設計ツールで、申請書作成・運用の課題をまとめて解決!
こんな人におすすめ
・新しく帳票を設計するのが大変
・自社のプロセスに合うテンプレートが見つからない
・担当者によって申請書ひな形がバラバラ
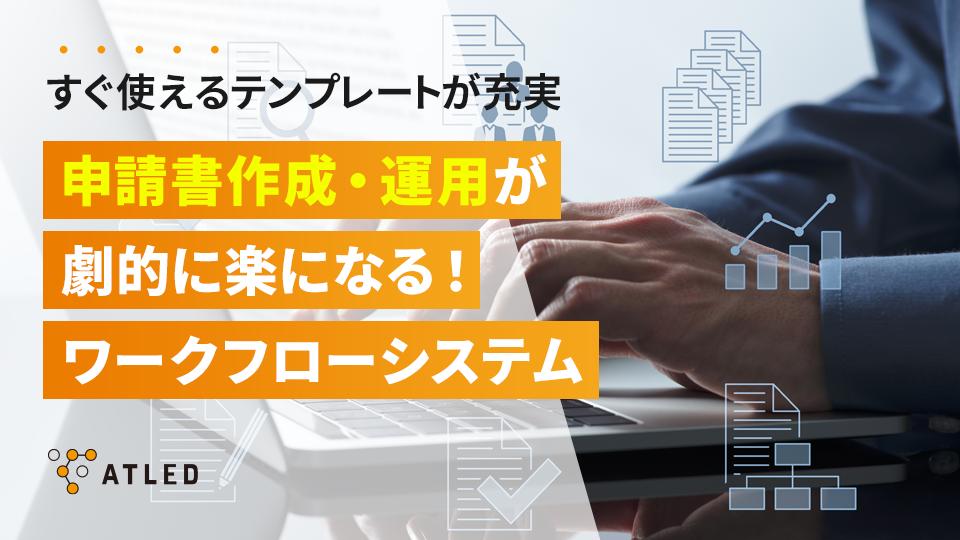

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。








