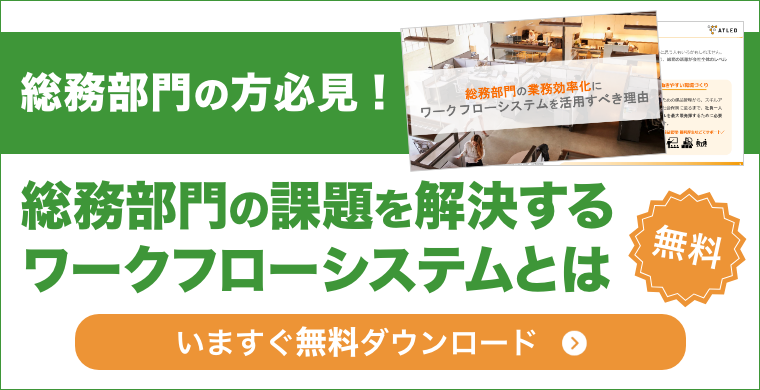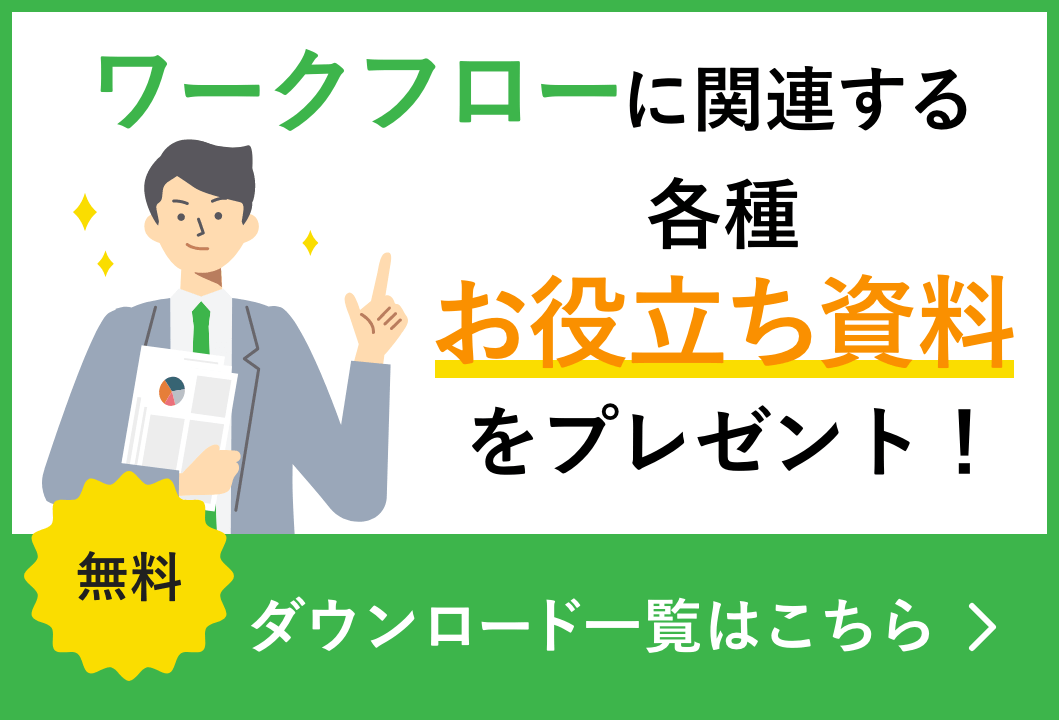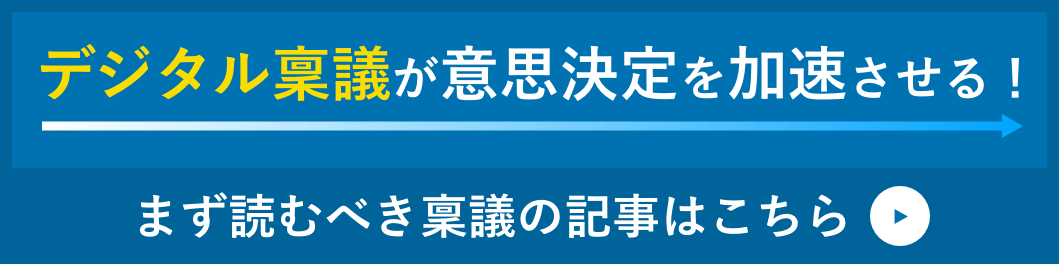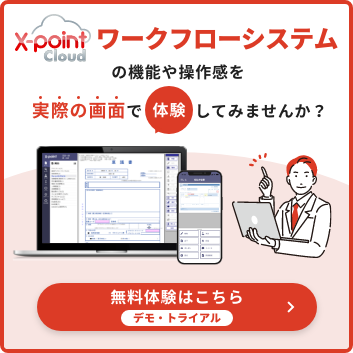目指すは攻めのバックオフィス~総務とワークフロー~(後編)
- 更新 -

本記事では前編・後編にわたって、ワークフロー総研 フェロー、『月刊総務』編集長 豊田 健一氏とワークフロー総研 所長 岡本との対談をお届けしています。
前編では総務はじめバックオフィスの皆さんが抱える課題感や感じているリアルなジレンマについてお話しました。
後編では、総務はじめバックオフィスはどのように変わっていけるか、未来の総務、バックオフィスのあり方とワークフローの関わりについて語ります。
\総務担当者必見!!総務部門効率化の鍵は、ワークフローシステム?/

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
\バックオフィスの効率化にDXは不可欠/
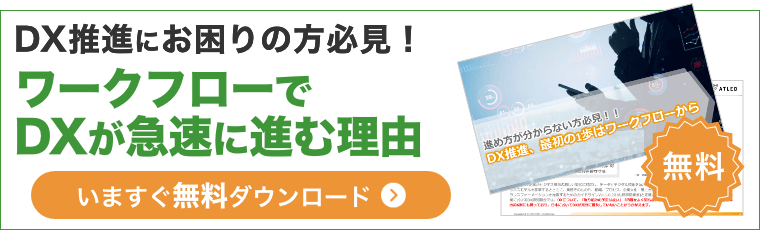
気づきをもたらすストーリーで、業務改善のアイデアを出してもらう

岡本:前半では、総務が経営者・現場双方の説得と納得を求められる立場にあること、そのための“武器”になるような事例やストーリーをワークフロー総研から提供できればというお話がありました。
この点をより深堀っていきたいのですが、具体的にどういったストーリーや内容のものがあると良さそうでしょうか?
豊田:製品の機能的な説明や、導入事例のように導入前後の部分的なお話だけでなく、社内の抵抗がどのように起きたのか、それに対してどういった対応をしていったのかなど、総務の方が直面するであろう場面を交えて提案できるといいのではないかと思っています。
また導入するまでも大事ですが、どう使ってもらっているかが重要ですので、社内説明会や社内広報の仕方、運用のプロセスも知りたい情報の一つでしょう。
岡本:確かに導入後の運営が本来の目的です。先々のプロセスまでを見据えて情報をお伝えできるといいですね。
個別のシーンだと、総務の皆さんはどういった業務でよくお困りなのでしょうか。
豊田:例えば備品の貸し出しはどうでしょうか。資産管理業務の一つですね。物の移動の管理は、大体総務が管轄するんじゃないでしょうか。
またそれが許可制であれば申請書が必ず発生しています。他にも車両管理や、最近だとテレワークの申請書なんかもありますよね。
岡本:確かに、最近はテレワークのための許可申請や、PCの持ち出し申請など多くの処理が発生していそうです。
ワークフローの流れとしてもシンプルですし、電子化しやすい業務と言えます。
豊田:大切なのは、こうした事例を見て「この業務が改善、あるいはDX(デジタルトランスフォーメーション)できるのであれば、この業務もできるかも?」と次々イメージしてもらうことなんです。
ITツールのメリットは理解できても具体的な着手にまで結びつかないと意味がありません。
イマジネーションや気づきにつながるストーリーをいかに提供できるかが肝になると思います。
岡本:それは重要ですね。ITツールは活用していただかないと意味がありません。システムの解約や乗り換えの理由でよくあるのが、導入したものの使えなかったという理由です。
しかしそれは技術的なハードルが高くて使いこなせなかったというより、活用できていないと感じたり、用途を広げることができなかったということなんですよね。
こういった理由で乗り換えをされる場合は、おそらく乗り換えたとしても同じシーンで・同じような使い方で利用されるはずなので、結局同じ壁にぶつかると思うんです。
それを防ぐためにも、用途開発を支援できるようなストーリーは積極的にワークフロー総研を通して共有していきたいですね。
\申請業務のDXはデジタル稟議!成功事例集プレゼント中!/デジタル稟議の特設サイトはこちら
豊田:はい。ぜひ取り組んでいきたいです。
モチベーションは変化することへのわくわく、期待感

岡本:ここまで業務改善に着手するまでの武器、情報はどのようなものが求められるのかについて議論を進めてきました。
その一方でこれは総務に限ったことではありませんが、働き方改革はツールやルールが整ったとしてもそれに付随してカルチャーも変わらないと、あるいは変えていかないと、進まない一面があります。
また最初は失敗もあるかもしれません。それでも負けずにバックオフィスの業務改善を推進し続けたり、総務であれば戦略総務を目指し続けるための、背中を押すきっかけやモチベーションは何か作れないものでしょうか。
豊田:おっしゃる通り、マインドを変えることは非常に大切です。これまで出会ってきた活躍される総務の皆さんの共通点としては、自身の成長意欲が高い、変化を恐れないといった特徴が見られました。
ご自身の成長意欲が高いので、あらゆる手段、それが従来のやり方を変えることだとしても、恐れずにその手段を選ぶことができます。
また、彼らの成長意欲は自己満足でなく会社の成長意欲にも結びついているんですね。視座が高く変化を恐れない、だからこそ変化に伴って起きうるハレーションも恐れずに物事を進めていけているのだと思います。
より根本的には、今の仕事が楽しいかどうかを振り返ってみるとよいのではないでしょうか。
つまらなさを感じているのであれば、目の前の業務の負担をどうやったら減らせるのか、楽しさを感じられるのかを考えて変えていってみてほしいです。
岡本:あるバックオフィスに関する調査レポートでは、自分の仕事が生産的でないと感じている割合が諸外国よりも高かったという結果が出ています。
これは逆に言えば改善の余地が大いにあるということですよね。生産性を高めることで仕事のやりがいが出てきてさらに前進させていきたいという意欲がわいてくると思います。
豊田:よく、総務の仕事は仕事をなくすことだと言っています。そのためにはまず目の前の仕事を棚卸して、効率化し、仕事をなくしていかなくてはいけません。
そうしてできた時間で、現場や経営とコミュニケーションをとるというように段階を踏んでいきます。
現場を声掛けして回る「ぶらぶら総務」という言葉もありますが、その時間を少しずつ増やせると、さらなる業務改善のきっかけを見つけ、社内営業の時間も確保することができ、好循環ができていくと思いますね。
この好循環が生まれれば周囲からの総務へのイメージも変わり、総務のあり方自体が変わっていくのではないでしょうか。
これからの総務とワークフローとの関わり
岡本:今日豊田さんとお話をしてみて、総務はじめバックオフィスの皆さんにこそぜひワークフローとワークフローシステムの活用方法を知っていただきたいと思いました。
出てきた課題をまとめると1)情報がない・武器がない、2)目の前の業務に忙殺されがち、という大きく2つがありました。
前半はワークフロー総研で導入前後の中長期的でリアルな課題に対して、一緒に解決できるような情報をお伝えできれば良さそうでした。
後半はワークフローシステムなど効果が分かりやすく、かつ目の前の業務に導入できるITツールで業務改善に取り組むのはどうかという流れでお話を進めてきました。
豊田:はい。まずはそういった活動を継続していきたいですね。さらに今後の活動でいうと、ワークフロー総研の取材等を通して、総務業務のベストプラクティスが見えてくるのではないかと期待しています。
ワークフローはどの組織や企業にも存在します。かつ多少差はありますが、業種や業界が異なっていても比較的総務は共通する業務も多いはずです。
そこで得た知見を発信するということができればさらに有益な情報を読者に提供できると考えています。
岡本:確かに、事例が蓄積されていけばそういったインサイトを得ることもできますね。
テレワーク申請をはじめとした申請処理のワークフローの作り方、システムの使い方といった具合ですね。
こうした他社がどうやっているのか、その中でもこういった場合にはこのパターンが成功する/失敗するというのは企業同士ですとなかなか情報交換するのは難しいでしょうから、貴重ですよね。
私たちのようなメディアからの情報発信をぜひ活用していただきたいです。
豊田:はい、製品や事例の話は外から得るしかありませんから。
元ソニー総務センター長の小山 義朗氏はセンター長になっても飛び込み営業の方にもとにかく会っていたと言います。
営業の方はある製品なりサービスなりの専門家ですから、最新の情報を持っているので、とにかく情報を求めて外部の方と会っていたのですね。
総務の仕事は内容が多岐にわたる割に、情報収集する先、機会やそのために充てる時間が普段とても少ないんです。
社内から要望が上がってくるのを待って初めて調べるのではなく、その時すぐ打ち返せるようにしなくてはいけませんが、そうした時間の確保にも、やはり目の前の業務改善に着手していただきたいです。
岡本:ワークフロー総研の役割は、そこですね。
モチベーションが継続するようなストーリーを伝えたり、手札になる情報や、いざ社内調整が発生した時には武器になる情報を提供したり。
ここまでは他の組織でもできることかもしれませんが、業務の棚卸に必要な「ワークフロー」という着眼点や、目の前の業務に導入しやすいワークフローシステムのナレッジや事例を豊富に提供できるのはワークフロー総研ならではないかと感じました。
総務はじめバックオフィスの皆さんの外部パートナーとして今後も有益な情報発信に注力していきたいと思います。
本日はありがとうございました。
豊田:ありがとうございました。
もっと知りたい!
続けてお読みください
<対談者プロフィール>
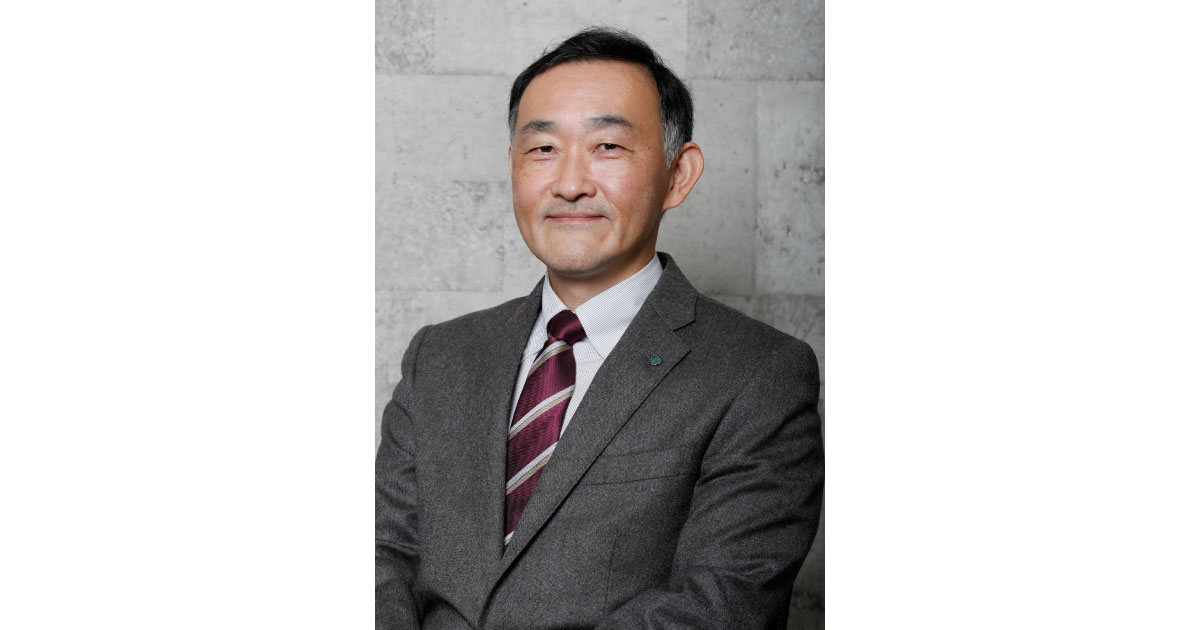
豊田 健一氏
ワークフロー総研 フェロー
株式会社月刊総務 代表取締役社長
『月刊総務』 編集長、戦略総務研究所 所長
早稲田大学政治経済学部卒業。株式会社リクルートで経理、営業、総務、販売会社の管理、株式会社魚力で総務課長を経験後、ウィズワークス株式会社を経て、株式会社 月刊総務へ。現在、日本で唯一の総務部門向け専門誌『月刊総務』の編集長、戦略総務研究所の所長。一般社団法人 ファシリティ・オフィスサービス・コンソーシアムの副代表理事やAll Aboutの「総務人事・社内コミュニケーション・ガイド」も務める。
プロフィールをもっと見る

ワークフロー総研 所長
岡本 康広
ワークフローシステムを開発・提供するエイトレッドの代表取締役社長も務める。
ワークフローを出発点とした働き方の見直しが意思決定の迅速化、組織の生産性向上へ貢献するという思いからワークフローの普及を目指し2020年4月、ワークフロー総研を設立して現職。エイトレッド代表としての知見も交えながら、コラムの執筆や社外とのコラボレーションに積極的に取り組んでいる。
プロフィールをもっと見る

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。